EC事業・D2C事業の株式譲渡を成功させる方法!M&Aのプロが徹底解説
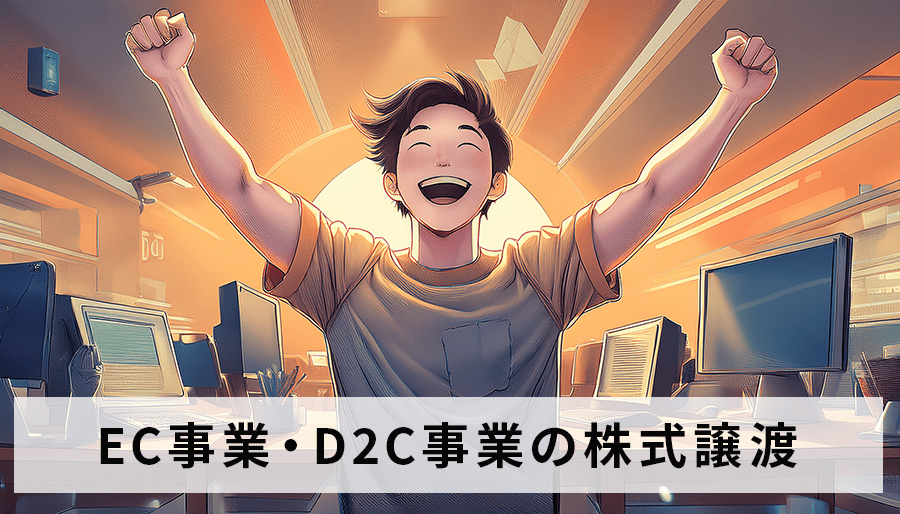
EC事業・D2C事業の株式譲渡を検討している経営者の方へ。売却を成功させ、最大限の利益を得るためには、M&Aのプロセスや注意点、税務、事業価値の評価方法などを理解することが不可欠です。
この記事では、M&Aのプロが、EC・D2C事業特有の株式譲渡のメリット・デメリット、事業譲渡との違い、M&Aのプロセス、成功のポイント、税務、そして実際の成功事例までを徹底解説します。
これを読めば、スムーズかつ有利な株式譲渡を実現するための道筋が明確になります。適切な準備と戦略で、あなたの事業の未来を最大化しましょう。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. EC事業・D2C事業の株式譲渡とは
EC事業・D2C事業の株式譲渡とは、事業を営む会社(株式会社または合同会社)の株式を売却することで、事業の所有権を移転させる取引のことです。
株式を譲渡することで、会社そのものの支配権が買い手に移り、事業の経営権も同時に移転します。EC事業やD2C事業においては、プラットフォームのアカウント、顧客データ、ブランド、ノウハウといった無形資産も重要な要素となるため、これらの資産を含めて会社全体の価値が評価され、株式の譲渡価格が決定されます。
株式譲渡には、事業譲渡と比較してメリット・デメリットが存在します。譲渡を検討する際には、それぞれのメリット・デメリットを理解した上で、自社にとって最適な方法を選択することが重要です。
1.1.1 メリット- 手続きが比較的簡便である
- 契約交渉がスムーズに進みやすい
- 従業員の雇用契約をそのまま引き継げる
- 許認可なども引き継げる場合が多い
- 負債も同時に引き継がれる
- 少数株主の同意が必要な場合がある
- 事業に不要な資産もまとめて譲渡することになる
EC事業・D2C事業の譲渡を考える際に、株式譲渡と事業譲渡のどちらを選択するかは重要なポイントです。それぞれの違いを理解することで、自社にとって最適な方法を選択できます。
| 項目 | 株式譲渡 | 事業譲渡 |
|---|---|---|
| 譲渡対象 | 会社の株式 | 事業に必要な資産・負債 |
| 手続き | 比較的簡便 | 複雑 |
| 契約 | 株式譲渡契約 | 事業譲渡契約 |
| 負債 | 引き継がれる | 選択的に引き継ぐ |
| 従業員 | 原則としてそのまま引き継ぐ | 個別に雇用契約を締結 |
| 許認可 | 原則としてそのまま引き継ぐ | 新規取得が必要な場合がある |
上記のように、株式譲渡と事業譲渡はそれぞれ異なる特徴を持っています。例えば、EC事業で重要な顧客データやプラットフォームアカウント、ドメインなどは、株式譲渡では会社とともに自動的に移転しますが、事業譲渡では個別に契約を締結する必要があります。
また、ブランドイメージも株式譲渡ではそのまま引き継がれますが、事業譲渡では新たに構築していく必要があるケースもあります。これらの点を踏まえ、自社の状況に合わせて最適な方法を選択することが重要です。
2. EC事業・D2C事業の譲渡におけるM&Aプロセス
EC事業・D2C事業のM&Aプロセスは、一般的に以下の段階を経て進みます。それぞれの段階で適切な対応を行うことが、M&Aを成功させる鍵となります。
【関連】通販事業の事業売却、成功させるための準備と戦略|M&A専門家による解説2.1 準備段階
M&Aを進めるにあたって、まず自社の現状を正確に把握し、譲渡目的を明確にする必要があります。財務状況の確認、事業計画の策定、譲渡価格の検討などを行い、M&Aの準備を整えましょう。
この段階で、M&Aアドバイザーを選定することも重要です。経験豊富なアドバイザーは、適切なアドバイスとサポートを提供し、M&Aプロセスをスムーズに進める手助けをしてくれます。
ノンネームクリアランスとは、買収候補先企業に、自社の概要や譲渡条件などを匿名で開示し、相手企業の関心度を探るプロセスです。秘密保持契約を締結した上で実施されます。買収候補先企業の反応を見ることで、M&Aの可能性を早期に判断することができます。
2.1.2 企業価値評価企業価値評価は、M&Aにおける価格交渉の基礎となる重要な要素です。DCF法、類似会社比較法、純資産法など様々な評価方法があり、事業の特性や状況に応じて適切な方法を選択する必要があります。客観的な評価を行うことで、売却側と買収側の双方が納得できる価格での取引を実現しやすくなります。
2.2 交渉段階買収候補先企業との交渉段階では、価格や条件、今後の事業展開などについて協議を行います。デューデリジェンスの実施もこの段階で行われ、買収候補先企業は詳細な情報を収集し、投資判断を行います。相互理解を深め、信頼関係を構築することが、円滑な交渉を進める上で重要です。
2.2.1 基本合意書(LOI)締結基本合意書(Letter of Intent)は、M&Aの基本的な条件を取りまとめた文書です。買収価格、譲渡対象、クロージング時期など、主要な事項が記載されます。法的拘束力がない場合もありますが、交渉の進捗をスムーズにするために重要な役割を果たします。
2.2.2 デューデリジェンスデューデリジェンスは、買収候補先企業が対象企業の財務状況、法務状況、事業状況などを詳細に調査するプロセスです。買収リスクを評価し、最終的な投資判断を行うために不可欠な手続きです。財務デューデリジェンス、法務デューデリジェンス、事業デューデリジェンスなど、様々な分野の専門家が関与します。
2.3 契約締結デューデリジェンスの結果を踏まえ、最終的な契約条件を交渉し、株式譲渡契約を締結します。契約書には、譲渡価格、譲渡株式数、表明保証、クロージング条件など、M&Aに関する重要な事項が詳細に記載されます。法的専門家のサポートを受けながら、契約内容を慎重に確認することが重要です。
2.3.1 最終契約書作成・締結最終契約書には、デューデリジェンスの結果を反映した最終的な合意事項が記載されます。売主と買主は、弁護士などの専門家の助言を受けながら、契約内容を精査し、署名・捺印を行います。この段階で、M&Aの条件が最終的に確定します。
2.4 クロージング株式譲渡契約に基づき、株式の所有権が売主から買主に移転します。代金決済、経営権の移行などが行われ、M&Aプロセスが完了します。クロージング後も、事業の統合やPMI(Post Merger Integration)など、新たな課題に取り組む必要があります。
2.4.1 株式譲渡実行・代金決済クロージング日には、株式譲渡契約に基づき、株式の所有権が正式に買主に移転します。同時に、買主から売主への代金決済が行われます。これをもって、M&A取引が完了します。
2.4.2 PMI(Post Merger Integration)PMIとは、M&A後の統合プロセスを指します。企業文化の融合、人事制度の統一、事業の再編など、様々な課題に取り組む必要があります。PMIの成否が、M&Aの最終的な成功を左右する重要な要素となります。
| 段階 | 主な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 準備段階 | 譲渡目的の明確化、事業価値評価、アドバイザー選定 | 自社の現状分析、適切なアドバイザー選び |
| 交渉段階 | 価格交渉、デューデリジェンス、基本合意書締結 | 情報開示、信頼関係構築 |
| 契約締結 | 株式譲渡契約締結 | 契約内容の精査 |
| クロージング | 株式譲渡実行、代金決済、PMI | 円滑な統合プロセス |
3. EC事業・D2C事業の株式譲渡でM&Aを成功させるためのポイント
EC事業・D2C事業の株式譲渡によるM&Aを成功させるには、綿密な準備と適切な戦略が不可欠です。譲渡価格の算定、デューデリジェンスへの対応、そして経験豊富なアドバイザーの選定など、様々な要素が成功を左右します。以下、主要なポイントを解説します。
3.1 事業価値の評価方法を理解するEC事業・D2C事業の価値評価は、一般的な製造業などと比べて複雑な側面があります。売上高や利益率といった財務指標に加え、顧客基盤の規模や質、ウェブサイトのトラフィック、ブランド力、リピート率、そして将来の成長性など、多角的な視点から評価を行う必要があります。主な評価方法としては、DCF法(ディスカウント・キャッシュ・フロー法)、類似会社比較法、純資産法などが挙げられます。
DCF法は、将来のキャッシュフローを現在価値に割り引いて事業価値を算出する方法です。EC・D2C事業特有の将来的な成長性を反映しやすい点がメリットですが、将来予測の精度が結果に大きく影響するため、慎重な分析が必要です。
類似会社比較法は、類似業種の株式市場における評価倍率を参考に事業価値を算定する方法です。市場の動向を反映した客観的な評価が可能ですが、真に比較可能な企業を見つけることが難しい場合があります。純資産法は、会社の資産から負債を差し引いた純資産額を基に事業価値を算定する方法です。
比較的シンプルな方法ですが、EC・D2C事業のように無形資産の価値が高い場合には、適切な評価が難しい可能性があります。
これらの評価方法を理解し、自社の事業特性に最適な方法を選択することが重要です。複数の方法を組み合わせて評価することも有効です。
【関連】EC事業・D2C事業の譲渡価格相場と企業価値算定方法|M&A成功の秘訣3.2 デューデリジェンスへの対応
デューデリジェンスとは、買収候補企業の財務状況、事業内容、法務状況などを詳細に調査するプロセスです。株式譲渡においては、買い手側がデューデリジェンスを実施し、隠れたリスクや問題点がないかを確認します。
スムーズな株式譲渡を実現するためには、事前に想定される質問事項や必要書類を整理し、迅速かつ正確な情報提供を行うことが重要です。特にEC・D2C事業においては、以下のような項目が重点的に調査される傾向があります。
| 調査項目 | 内容 |
|---|---|
| 顧客データ | 顧客数、属性、購買履歴、解約率など |
| ウェブサイト/プラットフォーム | アクセス数、コンバージョン率、システムの安定性など |
| 在庫管理 | 在庫状況、欠品率、ロジスティクス体制など |
| 知的財産権 | 商標権、特許権、著作権など |
| 法令遵守 | 特定商取引法、個人情報保護法などへの準拠状況 |
これらの項目について、事前に問題点がないかを確認し、必要に応じて改善策を講じておくことが、デューデリジェンスをスムーズに進める上で重要です。
3.3 適切なアドバイザーを選ぶM&Aは複雑なプロセスであり、専門的な知識と経験が必要です。M&Aアドバイザーは、事業価値の評価、買い手候補の探索、交渉、契約締結、クロージングに至るまで、M&Aプロセス全体をサポートします。適切なアドバイザーを選ぶことは、M&Aを成功させるための重要な要素です。
EC・D2C事業に精通した実績豊富なアドバイザーを選ぶことで、より有利な条件での譲渡を実現できる可能性が高まります。アドバイザー選定の際には、以下の点を考慮すると良いでしょう。
- EC・D2C事業のM&A実績
- 専門知識と経験
- ネットワーク
- 費用体系
- 相性
複数のアドバイザー候補と面談し、それぞれの強みや特徴を比較検討した上で、自社に最適なアドバイザーを選ぶことが重要です。信頼できるアドバイザーと二人三脚でM&Aプロセスを進めることで、成功の可能性を最大化できるでしょう。
【関連】EC事業・D2C事業のM&Aアドバイザー選びで失敗しないための3つのポイント4. EC事業・D2C事業の株式譲渡に関する税務
EC事業・D2C事業の株式譲渡を行う際には、譲渡益に対して税金が発生します。税率や控除などは、譲渡主が個人か法人か、株式の保有期間などによって異なります。事前に税務の知識を身につけておくことで、想定外の負担を避けることができます。
4.1 個人で譲渡する場合の税率個人で株式を譲渡した場合、譲渡益は「譲渡所得」として扱われ、所得税と住民税が課税されます。株式の保有期間によって税率が異なり、以下のようになります。
| 保有期間 | 税率(所得税+住民税) |
|---|---|
| 5年超 | 約20% |
| 5年以内 | 約39% |
5年超保有している株式を譲渡した場合、軽減税率が適用されます。また、一定の要件を満たせば、株式譲渡益控除などの特例も利用可能です。
4.2 法人で譲渡する場合の税率法人で株式を譲渡した場合、譲渡益は法人税の課税対象となります。法人税の基本税率は約23%です。地方税も加算されるため、実効税率は30%前後になることが多いでしょう。また、連結納税制度を採用している場合は、グループ全体の法人税額に影響を与える可能性があります。
4.2.1 税務上の注意点株式譲渡の際には、譲渡価額の算定方法や譲渡所得の計算方法など、複雑な税務上のルールが適用されます。税務調査が入る可能性も考慮し、適切な書類作成や記録保存を行うことが重要です。また、税理士などの専門家に相談することで、税務リスクを最小限に抑えることができます。
特に、EC事業・D2C事業特有の無形資産(ブランド力、顧客リスト、独自のプラットフォームなど)の評価は難しく、譲渡価額に大きく影響します。これらの評価方法を事前に理解し、適切な価格設定を行うことが重要です。
また、譲渡スキームによっては、税務上のメリット・デメリットが生じる場合があります。例えば、株式交換や合併などの組織再編スキームを利用することで、税負担を軽減できる可能性があります。
税務の専門家と連携し、事業の特性や譲渡条件を考慮した上で、最適な税務戦略を策定することが、株式譲渡を成功させるための重要なポイントとなります。
【関連】EC事業・D2C事業の売却価格相場とM&A成功の秘訣|高額売却を実現する方法5. EC事業・D2C事業の株式譲渡の成功事例
EC事業・D2C事業の株式譲渡を検討する上で、成功事例を知ることは大きな助けとなります。ここでは、実際に成功した事例をいくつかご紹介することで、具体的なイメージを持っていただくとともに、成功のポイントを探ります。
5.1 EC事業の株式譲渡 5.1.1 事例1:急成長ECプラットフォーム「A社」の株式譲渡A社は、独自のプラットフォームでニッチな市場をターゲットにしたEC事業を展開し、急成長を遂げていました。しかし、更なる成長のための資金調達と経営基盤の強化を目的として、大手IT企業B社への株式譲渡を決定しました。
B社はA社の持つ独自の技術と顧客基盤に魅力を感じ、高額での買収に至りました。A社はB社の傘下に入ることで、資金調達だけでなく、B社が持つ豊富なリソースを活用した事業拡大を実現しました。
長年地域に根ざしたEC事業を展開してきたC社は、後継者不足という課題を抱えていました。そこで、事業の継続と従業員の雇用を守るため、同業他社であるD社への株式譲渡を決定しました。D社はC社の持つ地域でのブランド力と顧客基盤を評価し、円滑な事業承継を実現しました。C社はD社の傘下に入ることで、事業の継続だけでなく、新たな経営資源の活用による事業活性化も期待されています。
5.2 D2C事業の株式譲渡 5.2.1 事例1:革新的D2Cブランド「E社」の大手企業への株式譲渡E社は、独自の商品開発力とSNSマーケティングを駆使したD2Cブランドを展開し、若年層を中心に高い人気を獲得していました。更なるブランド拡大と海外展開を視野に入れ、大手消費財メーカーF社への株式譲渡を決定しました。
F社はE社の持つブランド力と革新的なマーケティング手法に魅力を感じ、高額での買収に至りました。E社はF社の傘下に入ることで、資金調達だけでなく、F社が持つグローバルな販売網を活用した海外展開を実現しました。
G社は、特定の健康ニーズに応える商品を開発・販売するD2C事業を展開していました。しかし、競争の激化と更なる成長のための販路拡大を目的として、大手製薬会社H社への株式譲渡を決定しました。
H社はG社の持つ独自の商品開発力と顧客データに魅力を感じ、買収に至りました。G社はH社の傘下に入ることで、H社が持つ研究開発力と販売網を活用した事業拡大を実現しました。
| 企業 | 譲渡形態 | 譲渡先 | 主な目的 | 成功のポイント |
|---|---|---|---|---|
| A社 | 株式譲渡 | 大手IT企業B社 | 資金調達、経営基盤強化 | 独自の技術と顧客基盤 |
| C社 | 株式譲渡 | 同業他社D社 | 事業承継 | 地域でのブランド力と顧客基盤 |
| E社 | 株式譲渡 | 大手消費財メーカーF社 | ブランド拡大、海外展開 | ブランド力とマーケティング手法 |
| G社 | 株式譲渡 | 大手製薬会社H社 | 販路拡大、更なる成長 | 商品開発力と顧客データ |
これらの事例から、EC事業・D2C事業の株式譲渡を成功させるためには、自社の強みを明確にし、適切な譲渡先を選定することが重要であることが分かります。また、譲渡目的を明確化し、デューデリジェンスへの適切な対応を行うことも成功のポイントとなります。
【関連】EC事業・D2C事業 売却準備チェックリスト|高額売却を実現する秘訣6. まとめ
EC事業・D2C事業の株式譲渡は、事業拡大や事業承継など様々な目的で検討される手法です。M&Aプロセスを理解し、事業価値評価、デューデリジェンス、税務への適切な対応を行うことで、成功の可能性を高めることができます。
適切なアドバイザーを選ぶことも重要です。譲渡を検討する際は、メリット・デメリットを比較し、事業譲渡との違いも理解した上で、自社にとって最適な選択を行うようにしましょう。
本記事が、EC・D2C事業のオーナー様にとって、株式譲渡に関する意思決定の一助となれば幸いです。


