M&Aデューデリジェンス実践チェックリスト|買い手が見落とせない重要項目
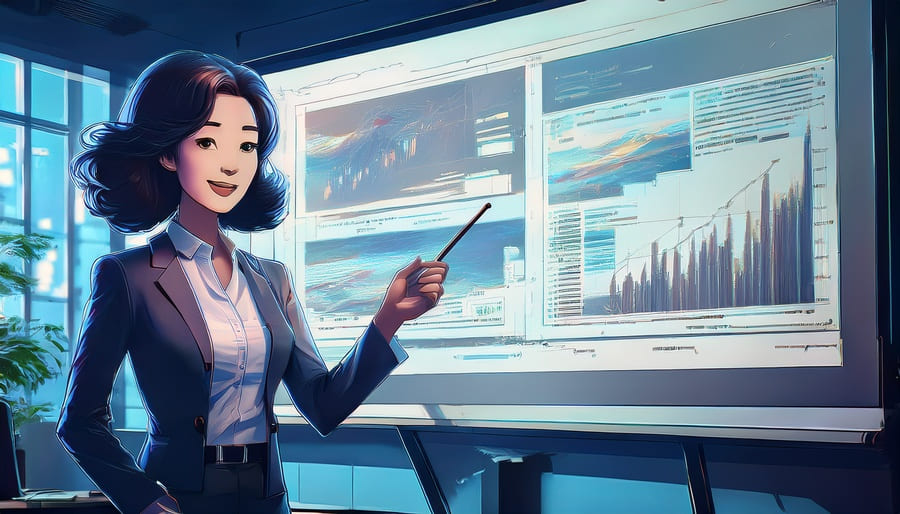
M&Aの成功は、網羅的で抜け漏れのないデューデリジェンスにかかっています。本記事では、買い手の実務担当者が見落としがちな重要項目を、財務・法務からビジネス・ITまで分野別に分け、実務でそのまま使える網羅的なチェックリストとして解説します。
このリストを活用すれば、潜在リスクを的確に洗い出し、M&Aの価値を最大化できます。準備段階からPMIを見据えた調査まで、成功への道筋が具体的にわかる完全ガイドです。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. 戦略的M&Aの基礎:デューデリジェンス準備チェックリスト
M&Aの成否を分けるデューデリジェンス(DD)は、単に対象企業のリスクを洗い出す作業ではありません。M&Aの目的達成、すなわち投資仮説やシナジー効果の実現可能性を徹底的に検証する戦略的なプロセスです。
この重要なプロセスを成功に導くためには、本格的な調査に入る前の「準備」が極めて重要となります。本章では、デューデリジェンスを効果的かつ効率的に進めるための、準備段階における実践的なチェックリストを解説します。
本格的なデューデリジェンスに着手する前に、まずは自社の戦略を再確認し、盤石な推進体制を構築する必要があります。目的が曖昧なままでは、調査の焦点がぼやけ、膨大な情報に振り回されてしまいます。ここでは、デューデリジェンス開始前に必ず確認すべき基本項目をチェックリスト形式でご紹介します。
1.1.1 M&Aの目的と投資仮説(シナジー)の明確化デューデリジェンスは、M&Aによって何を実現したいのかという「目的」と、なぜその企業を買収するのかという「投資仮説」を検証する場です。これらが明確でなければ、適切な評価はできません。以下のテーブルを用いて、自社のM&A戦略を具体的に言語化・数値化しましょう。
| チェック項目 | 具体的な確認ポイント |
|---|---|
| 経営戦略との整合性 |
|
| シナジー効果の具体化 |
|
| 投資仮説の検証可能性 |
|
M&Aデューデリジェンスは、財務、税務、法務、ビジネス、人事、ITなど多岐にわたる専門知識を必要とします。自社内の担当者だけで全てをカバーすることは困難であり、外部の専門家と連携したチーム組成が成功の鍵となります。各専門家の役割を明確にし、円滑なコミュニケーション体制を構築しましょう。
| 専門家 | 主な役割とチェックポイント |
|---|---|
| FA(ファイナンシャル・アドバイザー) |
|
| 公認会計士・税理士 |
|
| 弁護士 |
|
| その他専門家 |
|
社内の準備が整ったら、次は売り手側から提供される情報を基に、初期的な分析を進めます。この段階では、本格的なデューデリジェンスで深掘りすべき論点を効率的に絞り込むことが目的です。秘密保持契約の締結から、初期資料の精査まで、着実にステップを進めましょう。
1.2.1 IM(インフォメーション・メモランダム)の精査と初期的な論点の洗い出しIM(インフォメーション・メモランダム)は、売り手側が作成した対象企業の概要資料です。これはあくまで売り手側の視点で作成されたマーケティング資料であるため、内容を鵜呑みにせず、批判的な視点で読み解く必要があります。IMを精査し、デューデリジェンスにおける初期的な論点を洗い出しましょう。
- 事業の理解:事業モデルの強み・弱み、市場におけるポジション、競合優位性の源泉は何か?
- 財務状況の把握:過去の財務数値(売上高、EBITDAなど)の推移に不自然な点はないか?収益性やキャッシュフローの源泉は何か?
- 成長戦略の評価:IMに記載されている成長戦略や事業計画の実現可能性は高いか?その前提条件は何か?
- 自社戦略との適合性:対象企業の事業や強みは、自社が描くM&Aの目的や投資仮説と合致しているか?
- 疑問点のリストアップ:説明が不十分な点、追加で確認が必要な情報はないか?(これらが後のQ&Aの基礎となる)
IMの精査後、より詳細な調査に進む意向を示すと、通常はNDA(秘密保持契約)の締結を求められます。NDA締結後、売り手側はVDR(ヴァーチャルデータルーム)と呼ばれるオンライン上のプラットフォームに、デューデリジェンスに必要な詳細資料を開示します。このプロセスを円滑に進めるためのチェックリストは以下の通りです。
- NDA(秘密保持契約)の締結:
- 秘密情報の定義、目的外使用の禁止、開示範囲、契約期間など、自社にとって不利な条項がないか弁護士と共に確認する。
- 速やかに締結し、次のステップへ進めるように準備する。
- DDリクエストリストの提出:
- VDRが開設される前に、調査したい資料を網羅した「DDリクエストリスト」を準備し、売り手側に提出する。
- 財務、法務、税務、ビジネスなど、各分野の専門家と連携してリストを作成する。
- VDR(ヴァーチャルデータルーム)の準備:
- 売り手側にVDRの開設を依頼し、自社チームおよび外部専門家が必要なアクセス権限を得られるように調整する。
- VDRの操作方法を確認し、Q&A機能などを通じて効率的に質疑応答を行える体制を整える。
2. M&Aの価値評価を左右する財務デューデリジェンス実践チェックリスト
財務デューデリジェンス(財務DD)は、M&Aのプロセスにおいて最も重要な調査の一つです。
対象企業の財務諸表を精査し、その実態を正確に把握することで、企業価値評価(バリュエーション)の妥当性を検証し、買収価格の算定やディールストラクチャーの決定に不可欠な情報を提供します。ここでは、M&Aの成否を分ける財務DDにおける、具体的な実践チェックリストを詳細に解説します。
企業の価値は、将来生み出すキャッシュフローによって決まります。財務DDでは、過去の損益計算書やキャッシュフロー計算書を分析し、対象会社が持つ本来の収益力とキャッシュ創出力を見極めることが重要です。一過性の要因や会計処理の特殊性を排除し、M&A後の事業計画の基盤となる「真の姿」を明らかにします。
2.1.1 正常収益力(EBITDA)の分析と非経常的な損益の排除正常収益力とは、対象会社が経常的な事業活動から生み出すことができる、持続可能な利益水準を指します。
特に、金利・税金・減価償却費控除前利益であるEBITDAは、国による税制や会計基準の違い、あるいは企業の設備投資方針による影響を受けにくいため、企業の収益力を測る指標として広く用いられます。
財務DDでは、会計上の利益から非経常的・一時的な要因を排除(正常化)し、この正常収益力を精緻に分析します。
| チェック項目 | 主な着眼点・正常化調整の例 | 確認資料の例 |
|---|---|---|
| 役員報酬・役員退職慰労金 | オーナー経営者への過大な報酬や退職金の有無。M&A後の役員体制を想定した適正水準への調整。 | 役員報酬規程、株主総会議事録、役員退職慰労金規程 |
| 非事業用資産・負債に係る損益 | 事業と関連性の低い資産(遊休不動産、ゴルフ会員権、高級車等)から生じる収益・費用を排除。 | 固定資産台帳、賃貸借契約書、勘定科目内訳明細書 |
| 一過性の特別損益 | 固定資産売却損益、災害損失、訴訟関連費用、リストラ費用など、臨時的・偶発的に発生した損益を排除。 | 損益計算書(PL)、総勘定元帳、取締役会議事録 |
| 関連会社・グループ会社間取引 | グループ外の第三者との取引条件と比較し、取引価格が不自然に高く、または低く設定されていないか(移転価格税制のリスクも含む)。 | 関連当事者との取引一覧、取引契約書、価格算定根拠資料 |
| 会計方針の変更・見積り | 減価償却方法の変更、引当金の計上基準の変更など、会計方針の変更が利益に与える影響を分析。買い手側の会計方針との差異も確認。 | 会計方針に関する注記、監査法人への質問書回答 |
運転資本(ワーキングキャピタル)は、事業を円滑に運営するために必要な資金であり、一般的に「売上債権+棚卸資産-仕入債務」で計算されます。
運転資本の分析は、対象会社の資金繰りの実態を把握し、買収後に想定外の追加運転資金が必要になるリスクを回避するために不可欠です。過去の推移や季節変動を分析し、事業規模に見合った適正な水準を見極めます。
| 分析項目 | チェックポイント | 確認資料の例 |
|---|---|---|
| 売上債権(売掛金・受取手形) | 回転期間は適正か。長期滞留債権や回収不能債権は存在しないか。債権年齢(エイジングリスト)の分析。 | 売掛金元帳、債権年齢調べ(エイジングリスト)、貸倒引当金計算書 |
| 棚卸資産(在庫) | 回転期間は適正か。長期滞留在庫、陳腐化在庫、販売不能在庫は存在しないか。評価損は適切に計上されているか。 | 在庫一覧表(商品別・滞留期間別)、実地棚卸報告書、棚卸資産評価に関する社内規程 |
| 仕入債務(買掛金・支払手形) | 回転期間は適正か。支払遅延や取引先とのトラブルは発生していないか。主要な取引先との支払サイトを確認。 | 買掛金元帳、支払サイト一覧、主要な取引基本契約書 |
| 季節性・イベントによる変動 | 特定の時期(年末商戦、ボーナス時期など)に運転資本が大きく増減する傾向はないか。月次での推移を分析。 | 月次試算表(過去3年分以上)、資金繰り表 |
貸借対照表(BS)には、企業の財政状態が示されますが、帳簿に記載されている資産・負債がすべてとは限りません。特に、帳簿には現れない「簿外債務」や、将来的に債務となる可能性のある「偶発債務」は、M&A後に買い手の財務を大きく圧迫する重大なリスクです。BSの各項目を精査し、隠れたリスクを徹底的に洗い出します。
2.2.1 簿外債務・偶発債務(未払残業代、訴訟リスク等)の特定簿外債務や偶発債務は、財務諸表を一見しただけでは発見が困難なケースが多く、M&Aの交渉終盤やクロージング後に発覚すると深刻な問題に発展します。法務DDとも連携しながら、潜在的な債務を網羅的に特定し、その影響額を見積もることが極めて重要です。
| リスク項目 | 具体的な確認事項 | 関連部署・資料 |
|---|---|---|
| 未払残業代・未払賃金 | タイムカードやPCログと給与台帳を突合し、サービス残業の実態がないか。管理監督者の範囲は適切か。36協定の遵守状況。 | 人事・労務部、勤怠管理データ、給与台帳、労働基準監督署からの是正勧告書 |
| 退職給付債務 | 退職金規程の有無と内容。退職給付引当金の計算は妥当か。中小企業退職金共済(中退共)等への加入状況。 | 人事部、退職金規程、年金数理計算報告書 |
| リース債務 | ファイナンス・リースだけでなく、BSに計上されないオペレーティング・リースの契約内容と残存期間、解約不能期間を確認。 | 経理部、リース契約書一覧、リース資産管理台帳 |
| 訴訟・紛争リスク | 現在係争中の訴訟や、今後訴訟に発展する可能性のある紛争・クレームの有無。損害賠償請求を受ける可能性。 | 法務部、顧問弁護士へのヒアリング、取締役会議事録 |
| 債務保証・差入担保 | 他社(特に経営者個人や関連会社)のために債務保証を行っていないか。事業資産が担保提供されていないか。 | 経理部、契約書、金銭消費貸借契約書、登記簿謄本 |
| 環境債務 | 土壌汚染やアスベスト(石綿)など、不動産に起因する将来の浄化費用や除去費用の発生リスク。 | 総務部、不動産鑑定評価書、専門家による環境調査報告書 |
運転資本の構成要素でもある在庫(棚卸資産)と売掛金(売上債権)は、粉飾決算の温床となりやすい勘定科目です。これらの資産が過大に評価されている場合、買収後に多額の評価損を計上する必要が生じ、投資回収計画が大きく狂うことになります。帳簿上の金額を鵜呑みにせず、その実在性と評価の妥当性を厳しく検証する必要があります。
| 資産項目 | チェックポイント | 確認手法・資料 |
|---|---|---|
| 在庫(棚卸資産) | 長期滞留・陳腐化した不良在庫は存在しないか。評価損は適切に計上されているか。 | 実地棚卸への立ち会い、滞留在庫リストの分析、過去の廃棄損の実績確認 |
| 売掛金(売上債権) | 回収が困難な不良債権は含まれていないか。貸倒引当金の計上額は十分か。 | 債権年齢調べ(エイジングリスト)の分析、主要な取引先への残高確認、過去の貸倒実績の分析 |
| 架空売上や循環取引など、不正な取引は存在しないか。 | 売上計上基準の確認、出荷伝票・納品書・請求書など証憑類の突合、期末前後の売上計上の妥当性検証 | |
| 固定資産 | 減損の兆候はないか。帳簿価額は回収可能価額を上回っていないか。資産の実在性、遊休資産の有無。 | 固定資産台帳の現物確認、減損会計に関する検討資料、不動産鑑定評価書 |
3. 潜在リスクを見抜くM&A法務・人事デューデリジェンスのチェックリスト
財務デューデリジェンスで企業の「現在」の価値を評価する一方、法務・人事デューデリジェンスでは、M&A実行後に顕在化しうる「未来」のリスクを洗い出します。
契約違反による取引の頓挫、許認可の失効による事業停止、キーパーソンの流出による事業価値の毀損など、ディールブレーカー(取引中止要因)となり得る重大なリスクが潜んでいるため、専門家である弁護士や社会保険労務士と連携し、網羅的に検証することが不可欠です。
法務デューデリジェンスは、対象会社の事業活動が法的に準拠して行われているか、M&Aによって法的な問題が発生しないかを確認するプロセスです。特に、契約書に潜むリスクや、事業継続の根幹となる許認可、知的財産権の状況把握は極めて重要です。
3.1.1 重要契約書におけるチェンジオブコントロール(COC)条項の有無チェンジオブコントロール(Change of Control、以下COC)条項とは、企業の支配権に変動(例:株式譲渡による親会社の変更)があった場合に、契約の相手方が契約解除や取引条件の変更を要求できる権利を定めた条項です。M&Aの実行が、主要な取引先との契約打ち切りに直結する可能性があるため、最優先で確認すべき項目です。
具体的には、以下の契約書を精査し、COC条項の有無、および該当する場合の通知義務や事前承諾の要否を確認します。
- 主要顧客との販売基本契約・個別契約
- 主要サプライヤーとの仕入基本契約・購買契約
- 技術ライセンス契約、ソフトウェア利用許諾契約
- 不動産賃貸借契約(本社、工場、店舗など)
- 金融機関との金銭消費貸借契約(融資契約)
- 業務提携契約、代理店契約
COC条項が発見された場合、M&Aの実行前に契約相手方から承諾を得るなどの対応が必要となり、交渉が難航すればM&Aのスキーム変更や中止を検討せざるを得ないケースもあります。
3.1.2 許認可、知的財産権(IP)、訴訟・紛争の状況確認事業の根幹を支える権利や、潜在的な紛争も法務デューデリジェンスの重要な調査対象です。これらの項目に問題が見つかると、事業継続そのものが困難になったり、予期せぬ損害賠償責任を負ったりするリスクがあります。
| 調査領域 | 主なチェックポイント | 潜在的リスク |
|---|---|---|
| 許認可 |
|
事業停止、罰金、ブランドイメージの毀損 |
| 知的財産権(IP) |
|
権利失効による競争優位性の喪失、損害賠償請求、使用差止 |
| 訴訟・紛争 |
|
損害賠償による財務的損失、偶発債務の発生、レピュテーションリスク |
「企業は人なり」という言葉の通り、M&Aの成否は従業員の円滑な引き継ぎに大きく左右されます。人事・労務デューデリジェンスでは、人材という無形資産の価値を正しく評価するとともに、未払残業代などの「隠れた負債(簿外債務)」を特定し、M&A後の組織統合(PMI)を円滑に進めるための課題を抽出します。
3.2.1 キーパーソンの特定とリテンションプランの必要性キーパーソンとは、その人物が退職した場合、企業の事業価値が著しく低下する恐れのある重要な従業員を指します。経営幹部だけでなく、特定の技術を持つエンジニア、大口顧客との関係を構築している営業担当者、独自のノウハウを持つ職人なども含まれます。
M&Aによる環境変化への不安から、キーパーソンが離職してしまうリスクは決して低くありません。そのため、以下の点をチェックし、必要に応じてリテンションプラン(引き留め策)を検討する必要があります。
- 特定:事業継続に不可欠なキーパーソンは誰か
- 依存度:特定のキーパーソンへの事業依存度はどの程度か
- 意向確認:M&Aに対するキーパーソンの意向やキャリアプランはどうか
- 対策検討:M&A後も継続して勤務してもらうためのインセンティブ(役職、報酬、ストックオプション等)は必要か
キーパーソンの流出は、計画していたシナジー効果を失わせるだけでなく、事業計画そのものを根底から覆す可能性があるため、慎重な対応が求められます。
3.2.2 労働条件、退職給付債務、労使紛争リスクの洗い出し労働関連法規の遵守状況は、コンプライアンス上の重要課題であると同時に、簿外債務の温床となりやすい領域です。特に中小企業では、労務管理が不十分なケースも散見されるため、詳細な調査が必要です。
| 調査領域 | 主なチェックポイント | 潜在的リスク |
|---|---|---|
| 労働条件 |
|
多額の未払賃金請求(簿外債務)、労働基準監督署からの是正勧告 |
| 退職給付債務 |
|
買収価格の算定に影響、将来のキャッシュフロー圧迫 |
| 労使紛争リスク |
|
従業員の士気低下、訴訟リスク、PMIの阻害要因 |
これらの調査を通じて発見された問題点は、最終契約における表明保証条項や補償条項に反映させ、買い手のリスクを低減するための交渉材料とします。
【関連】M&Aデューデリジェンスの流れをステップごとに完全理解4. シナジー創出の鍵:M&Aビジネス・ITデューデリジェンスのチェックリスト
財務デューデリジェンスや法務デューデリジェンスが、対象企業の過去から現在におけるリスクを洗い出す「守り」の調査であるのに対し、ビジネス・ITデューデリジェンスはM&A成立後の事業価値向上、すなわちシナジー効果を最大化するための「攻め」の調査と位置づけられます。
買収後の統合(PMI)を見据え、事業の将来性やオペレーション上の課題を事前に把握することが、M&A成功の確度を大きく左右します。ここでは、M&Aの投資仮説を検証し、シナジー創出の実現可能性を探るための具体的なチェックリストを解説します。
ビジネスデューデリジェンスの中核は、対象企業の事業が将来にわたって持続的に成長できるかを見極めることにあります。売り手から提示される事業計画を鵜呑みにするのではなく、市場環境、競争優位性、顧客基盤といった多角的な視点からその妥当性を客観的に評価する必要があります。
4.1.1 事業計画の蓋然性とKPI(重要業績評価指標)の妥当性評価対象企業が策定した事業計画が「絵に描いた餅」で終わらないか、その実現可能性(蓋然性)を厳しく検証します。過去の実績との連続性や、市場の成長性といった外部要因との整合性を分析し、計画を支えるロジックを明らかにすることが重要です。
特に、計画の進捗を測るKPIが適切に設定・運用されているかは、経営管理能力を評価する上でも欠かせないポイントです。
| 評価項目 | 主なチェックポイント | 関連資料の例 |
|---|---|---|
| 事業計画の妥当性 |
|
中期経営計画書、年度予算書、取締役会資料、市場調査レポート |
| KPIの適切性 |
|
KPI管理シート、営業会議資料、経営会議資料 |
| SWOT分析 |
|
事業戦略資料、競合分析レポート |
特定の顧客やサプライヤー(仕入先)への依存度が高いビジネスは、M&Aをきっかけとした取引関係の変化によって事業基盤が揺らぐリスクを内包しています。主要な取引先との契約内容や関係性を精査し、M&A後も安定した取引が継続できるかを確認することは、事業の安定性を評価する上で極めて重要です。
| 評価項目 | 主なチェックポイント | 関連資料の例 |
|---|---|---|
| 主要顧客との関係 |
|
顧客別売上台帳、主要顧客との取引基本契約書 |
| 主要サプライヤーとの関係 |
|
仕入先別買入台帳、主要サプライヤーとの購買契約書、信用調査レポート |
| 契約内容の確認 |
|
各種契約書ファイル |
M&A後の統合プロセス(PMI)で最も時間とコストを要するのが、ITシステムと業務オペレーションの統合です。デューデリジェンスの段階でこれらの実態を正確に把握し、統合の難易度や潜在的な課題を洗い出しておくことで、PMIを円滑に進め、想定外のコスト発生を防ぐことができます。
4.2.1 基幹システム(ERP)の互換性と統合コスト・スケジュールの見積もり両社の基幹システム(ERP)が大きく異なる場合、その統合はPMIにおける大きな障壁となります。システムの構造やカスタマイズの状況、保守運用体制などを事前に評価し、統合に向けた具体的な計画(方式、コスト、スケジュール)を策定しておく必要があります。
| 評価項目 | 主なチェックポイント | 関連資料の例 |
|---|---|---|
| IT資産の棚卸 |
|
IT資産管理台帳、システム構成図、保守運用契約書 |
| システムの互換性と統合方針 |
|
システム仕様書、IT戦略資料 |
| 統合コストとスケジュールの試算 |
|
IT関連投資計画、ベンダーからの見積書 |
| 情報セキュリティ |
|
情報セキュリティ関連規程、インシデント報告書、Pマーク/ISMS認証の取得状況 |
システムだけでなく、日々の業務の進め方(業務プロセス)や組織文化の違いも、PMIを阻害する要因となり得ます。各部門の業務フローを可視化し、非効率な点や統合時のコンフリクトとなりうる点を事前に特定しておくことで、スムーズな組織融合とシナジーの早期実現を目指します。
| 対象領域 | 主なチェックポイント | シナジー創出/リスクの視点 |
|---|---|---|
| 販売・営業 |
|
クロスセルによる売上拡大の機会、営業部門の非効率な業務プロセスの可視化、ブランド戦略統合の課題 |
| 製造・購買 |
|
共同購買によるコスト削減、生産拠点の最適化、サプライチェーンの脆弱性リスク |
| 管理部門(経理・人事) |
|
バックオフィス業務の集約による効率化、人事制度の統一に伴うキーパーソンの離職リスク、ガバナンス体制構築の課題 |
5. まとめ
M&Aの成功は、網羅的で精密なデューデリジェンスにかかっています。本記事では、準備段階から財務、法務・人事、ビジネス、ITまで、買い手が見落とせない重要項目をチェックリスト形式で解説しました。
正常収益力や簿外債務の把握といった価値評価の根幹から、チェンジオブコントロール条項やPMIを見据えた課題抽出まで、多角的な視点での調査が不可欠です。このチェックリストを実践することで、潜在リスクを回避し、M&Aの成功確率を最大化できるでしょう。


