M&A デューデリジェンス 進め方:成功に導く完全ガイドと実践ロードマップ
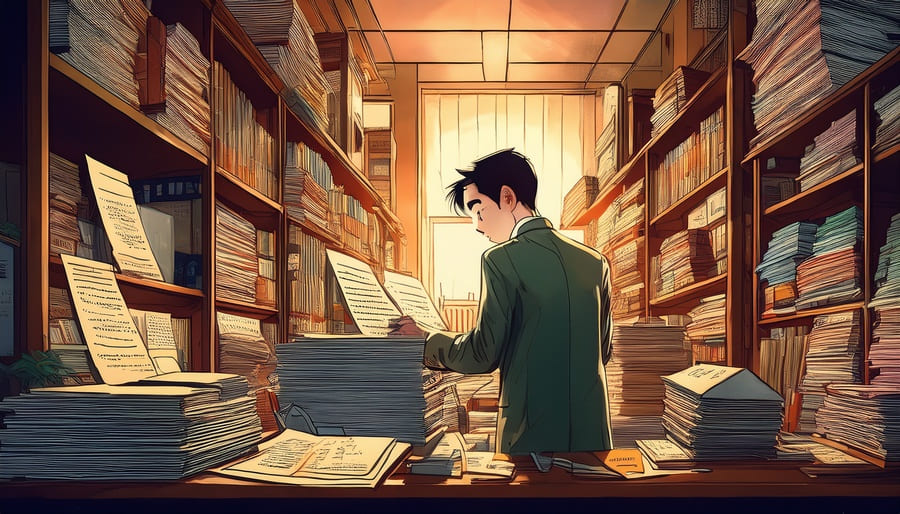
M&Aデューデリジェンスの進め方を網羅的に解説し、M&A成功への道筋を示す完全ガイドです。本記事を読めば、専門家チームの組成といった準備段階から、財務・法務・税務など分野別の具体的な調査プロセス、最終契約への反映、PMI計画への連携まで、一連の流れと実践的な手法が全てわかります。
このロードマップに沿って進めることで、潜在リスクを的確に把握し、企業価値の最大化を実現できます。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&A成功の基盤を築くデューデリジェンスの戦略的な進め方
M&Aにおけるデューデリジェンス(Due Diligence、以下DD)は、単なる買収対象企業の調査活動ではありません。M&Aの最終的な成功を左右する、極めて戦略的なプロセスです。
この初期段階の進め方次第で、リスクの発見精度や後の交渉、さらにはPMI(Post Merger Integration:M&A後の統合プロセス)の円滑さまでが決まります。ここでは、DDを本格的に開始する前の準備段階から、売り手からの初期情報開示を受けるまでの、成功の土台となる戦略的な進め方について具体的に解説します。
DDを成功に導くためには、実査に着手する前の周到な準備が不可欠です。この「キックオフ前」の段階で、調査の目的を明確にし、最適なチームを組成することで、DD全体の質と効率が飛躍的に向上します。場当たり的な調査に陥ることを避け、M&Aの目的達成に直結するDDを実現するための進め方を見ていきましょう。
1.1.1 専門家チームの組成と役割分担(FA、弁護士、会計士)M&AのDDは、財務、税務、法務、ビジネス、人事、ITなど多岐にわたる専門知識を要求されるため、自社リソースのみで完結させることは困難です。各分野のプロフェッショナルで構成される専門家チームを早期に組成し、明確な役割分担を行うことが進め方の第一歩となります。
主要な専門家とその役割は以下の通りです。それぞれの専門家が有機的に連携し、情報を密に共有する体制を構築することが、網羅的で精度の高いDDを実現する鍵となります。
| 専門家 | 主な役割 | 選定におけるポイント |
|---|---|---|
| FA(ファイナンシャル・アドバイザー) | M&Aプロセス全体の統括、DDのプロジェクトマネジメント、交渉戦略の立案、バリュエーション(企業価値評価)の実施、各専門家との連携調整。 | 対象業界におけるM&A実績、DD全体の管理能力、円滑なコミュニケーションを促進する調整力。 |
| 弁護士(法務DD担当) | 契約関係のレビュー、許認可の有効性確認、訴訟・紛争リスクの洗い出し、コンプライアンス体制の評価、チェンジオブコントロール条項の特定。 | M&A法務に関する深い専門知識、対象企業の事業に関連する法規制への精通度、契約交渉の実務経験。 |
| 公認会計士・税理士(財務・税務DD担当) | 財務諸表の信頼性検証、正常収益力の分析、ネットデットの算定、簿外債務や偶発債務の発見、税務申告の妥当性評価、タックス・ストラクチャリングの検討。 | 財務DDの実績、会計基準に関する深い知見、組織再編税制など複雑な税務リスクを評価できる能力。 |
効果的なDDを進めるためには、「なぜこのM&Aを行うのか」という買収目的を明確に定義することが不可欠です。例えば、新規事業への参入が目的なのか、既存事業とのシナジー創出が目的なのか、あるいは優秀な人材や特定の技術の獲得が目的なのかによって、DDで重点的に調査すべき項目は大きく異なります。
この買収目的を基に、DDの調査範囲である「スコープ」を具体的に設定します。スコープ設定では、以下の要素を決定します。
- 調査分野:財務、税務、法務といった必須分野に加え、ビジネス、人事、IT、環境など、M&Aの目的に応じてどこまで調査するかを決定します。
- 調査の深度:各分野について、どの程度詳細に調査を行うかを定めます。例えば、契約書レビューは全ての契約を対象とするのか、一定金額以上の重要な契約に限定するのか、といった基準を設けます。
- 重要性の基準(マテリアリティ):調査対象とする金額的な基準値を設定します。この基準を下回る軽微なリスクについては、報告を省略するなどして、重要な論点にリソースを集中させます。
- 調査対象期間:通常、過去3〜5年程度の財務諸表や議事録を調査対象としますが、事業の特性に応じて期間を調整します。
これらのスコープは、FAや各専門家と緊密に協議しながら文書化し、チーム全体で共有することが、手戻りのない効率的なDDの進め方につながります。
1.2 初期情報開示プロセスの進め方準備段階が完了すると、次はいよいよ売り手側から具体的な情報を入手するプロセスへと移行します。この初期情報開示が円滑に進むかどうかは、DDのスケジュールと質に直接的な影響を与えます。買い手として、売り手側の協力を得ながら、体系的かつ効率的に情報を収集するための進め方が求められます。
1.2.1 基本合意書(LOI)締結と要求資料リスト(RRL)の提示本格的なDDを開始する前提として、売り手と買い手との間で「基本合意書(LOI: Letter of Intent または MOU: Memorandum of Understanding)」を締結するのが一般的です。LOIには、現時点での買収価格の目線、今後のスケジュール、独占交渉権、秘密保持義務などが盛り込まれます。
法的拘束力は一部の条項に限られますが、この合意をもって売り手は本格的な情報開示に応じる意思を示し、買い手はDDに要するコストを投下する根拠を得ます。
LOI締結後、買い手側は速やかに「要求資料リスト(RRL: Request for Information List)」を売り手側に提示します。これは、DDを実施するために必要となる資料の一覧であり、通常はFAが全体を取りまとめ、法務、財務などの各専門家がそれぞれの分野で必要なリストを作成します。
RRLは、定款や登記簿謄本といった基本情報から、詳細な財務データ、重要な契約書、議事録、許認可関連書類まで、網羅的かつ具体的に作成することが重要です。このリストの質が、後の情報収集の効率を大きく左右します。
現代のM&Aでは、要求資料の開示は「VDR(ヴァーチャルデータルーム)」と呼ばれるセキュアなオンラインプラットフォーム上で行われるのが主流です。
VDRは、物理的な資料の閲覧に比べて時間や場所の制約がなく、複数の関係者が同時にアクセスできるほか、誰がいつどの資料を閲覧したかというログ管理も可能なため、情報管理の安全性と効率性を両立できます。
VDRは通常、売り手側が準備し、買い手側の関係者(経営陣、担当者、各専門家)にアクセス権を付与する形で開設されます。買い手としては、VDRのフォルダ構成が論理的で分かりやすいか、検索機能が使いやすいかなどを確認し、必要であれば売り手側に改善を要求することも進め方の一つです。
開示された膨大な資料を効率的にレビューするため、チーム内で誰がどのフォルダを担当するかを割り振り、発見事項や疑問点を共有する仕組みを構築することが、円滑なDDマネジメントの基礎となります。
2. 【分野別】M&Aデューデリジェンスの具体的な進め方と分析手法
M&Aのデューデリジェンス(DD)は、対象企業の価値とリスクを多角的に評価するため、専門分野ごとに深く掘り下げて進められます。特に重要となるのが「財務・税務」「法務」「ビジネス」の3分野です。
これらのデューデリジェンスは独立して進められるのではなく、相互に情報を連携させながら、対象企業の実態を立体的に浮かび上がらせていきます。本章では、それぞれの分野における具体的な進め方と主要な分析手法を詳細に解説します。
財務・税務デューデリジェンスは、公認会計士や税理士といった財務の専門家が主導し、対象企業の財務諸表に記載された数値の信頼性を検証するとともに、隠れた財務リスクや税務リスクを洗い出すことを目的とします。これは、適正な買収価格を算定し、買収後の想定外の損失を防ぐための根幹となるプロセスです。
2.1.1 正常収益力分析とネットデット(Net Debt)の算定財務デューデリジェンスの中核をなすのが「正常収益力分析」と「ネットデットの算定」です。これらは企業価値評価(バリュエーション)の基礎となる極めて重要な指標です。
正常収益力分析は、対象企業が将来にわたって安定的に生み出すと期待される本来の収益力(実力値)を把握するための分析です。
会計上の利益には、役員の個人的な経費や一過性の損益など、事業の本質とは関係のない要素が含まれていることが多いため、これらを排除・調整し、実態のEBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)を算出します。この分析により、買収価格の妥当性を判断する基準が明確になります。
| 調整項目の種類 | 具体例 | 調整の方向性 |
|---|---|---|
| 非経常的な損益 | 固定資産売却損益、災害損失、訴訟関連費用 | 一過性の要因として利益から加減算する |
| 会計方針の差異 | 減価償却方法の変更、棚卸資産の評価方法の差異 | 買手企業の会計方針に揃える形で調整する |
| オーナー関連費用 | 過大な役員報酬、オーナーの私的経費(交際費、車両費など) | 事業継続に不要な費用として利益に加算する |
| その他 | 研究開発費、広告宣伝費など、M&A後に方針が変更される費用 | 買収後の事業計画に基づき調整する |
一方、ネットデット(純有利子負債)の算定は、買収価格の決定に直接影響します。一般的に、企業価値からネットデットを差し引いたものが株式価値となるため、その正確な把握が不可欠です。
単純な借入金から現預金を差し引くだけでなく、貸借対照表に計上されていない「デットライクアイテム(負債類似項目)」を漏れなく特定することが重要です。これには、未払の退職給付債務や賞与、訴訟引当金、リース債務などが含まれます。
財務・税務デューデリジェンスでは、将来的に企業のキャッシュフローを悪化させる可能性のあるリスクを事前に特定することも重要な役割です。
偶発債務の洗い出しでは、現時点では債務として確定していないものの、将来的に発生する可能性のある「簿外債務」を調査します。代表的なものとして、係争中の訴訟における潜在的な損害賠償義務、過去の製品に対する保証義務、未払残業代などの労務リスク、土壌汚染などの環境債務が挙げられます。
これらのリスクは法務デューデリジェンスと緊密に連携しながら評価し、最終契約書の表明保証条項や価格調整に反映させます。
タックス・ストラクチャリングの検討は、M&Aの実行スキーム(例:株式譲渡、事業譲渡、合併など)が税務上どのような影響を及ぼすかを分析し、最も税効率の高い方法を模索するプロセスです。
例えば、対象企業が抱える繰越欠損金をM&A後も活用できるか、不動産取得税や登録免許税などの流通税がどの程度発生するか、消費税の課税関係はどうなるかなどを詳細に検討します。最適なストラクチャーを構築することで、M&Aに伴う税務コストを最小限に抑え、投資効果を最大化することが可能になります。
法務・ビジネスデューデリジェンスは、弁護士、経営コンサルタント、そして買手企業の事業担当者が連携して進めます。法務面では契約関係や許認可、コンプライアンス体制などの法的リスクを網羅的に洗い出し、ビジネス面では事業の競争優位性や市場環境、シナジー効果の実現可能性を検証します。
2.2.1 チェンジオブコントロール(COC)条項の確認とキーマン条項の分析法務デューデリジェンスにおいて、特に注意深く進めるべきなのが契約書のレビューです。中でも「チェンジオブコントロール(COC)条項」の確認は極めて重要です。
チェンジオブコントロール(COC)条項とは、企業の支配権(コントロール)に重要な変更が生じた場合、契約相手方が事前の同意なく契約を解除したり、取引条件の変更を要求したりできる権利を定めた条項です。
この条項が主要な顧客との取引基本契約や、事業継続に不可欠なライセンス契約、不動産賃貸借契約などに含まれている場合、M&Aの実行によってこれらの重要な契約が失効するリスクがあります。
デューデリジェンスでは、対象企業が締結している全ての重要な契約書を精査し、COC条項の有無、その内容、そしてリスクの大きさを評価します。リスクが高いと判断された場合は、クロージングの前提条件として、契約相手方からの事前同意の取得を売手側に求めるなどの対応が必要となります。
また、キーマン条項の分析も重要です。これは、特定の役員や従業員(キーマン)が退職した場合に、契約が終了する旨を定めた条項です。
特に、創業オーナーや特定の技術者が事業の中核を担っている企業の場合、M&Aを機にキーマンが流出すると事業価値が大きく損なわれる可能性があります。
キーマン条項の有無を確認するとともに、ビジネスデューデリジェンスと連携し、キーマンへの依存度を評価し、M&A後のリテンションプラン(引き留め策)を検討することが不可欠です。
ビジネスデューデリジェンスは、M&Aの成否を分ける「シナジー効果」の実現可能性と、M&A後の統合プロセス(PMI)を見据えた課題抽出に焦点を当てて進められます。
事業シナジーの定量評価では、M&Aによって創出される価値を具体的な数値に落とし込みます。シナジーは大きく「売上シナジー」と「コストシナジー」に分類され、それぞれについて実現可能性の高いアクションプランを策定し、その効果を金額として試算します。この定量評価は、買収価格の妥当性を検証する上で重要な根拠となります。
| シナジーの種類 | 具体例 | 定量評価の視点 |
|---|---|---|
| 売上シナジー | 両社の販路を活用したクロスセル・アップセル、ブランド力の相互活用、新規市場への共同参入 | 顧客基盤の重複度、市場規模、想定されるシェア拡大率、価格戦略などを基に、増加が見込まれる売上高と利益を試算する。 |
| コストシナジー | 原材料の共同購買による価格交渉力強化、管理部門(人事・経理等)の統合、生産拠点や物流網の統廃合 | 重複する業務や拠点の特定、規模の経済による単価低減効果などを基に、削減可能な固定費や変動費を具体的に算出する。 |
そして、デューデリジェンスの最終段階では、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)の課題抽出を行います。これは、財務・法務・ビジネスの各デューデリジェンスで明らかになった問題点やリスクを統合し、M&A後の統合プロセスで何をすべきかを明確にする作業です。
例えば、企業文化の大きな違い、基幹システムの非互換性、人事評価制度の差異、キーマンの退職リスクなどが課題として挙げられます。これらの課題を事前に洗い出し、優先順位を付けておくことで、M&A成立後、速やかに統合計画(100日プランなど)に着手し、シナジーの早期実現を図ることが可能になります。
3. M&Aを円滑にするデューデリジェンスのマネジメントと進め方
M&Aのデューデリジェンスは、単なる調査活動に留まりません。売り手企業、自社の経営陣、そして外部の専門家チームといった多数の関係者との円滑なコミュニケーションと、複雑なプロセスを的確に管理するプロジェクトマネジメント能力が、M&Aの成否を大きく左右します。
この章では、デューデリジェンスを円滑に進め、その結果を的確な意思決定に繋げるためのマネジメント手法と具体的な進め方について詳述します。
デューデリジェンスにおいて、VDR(ヴァーチャルデータルーム)で開示された資料だけでは把握できない情報は、Q&Aプロセスを通じて明らかにしていきます。売り手との質疑応答は、対象企業の深い理解を得るための生命線であり、このコミュニケーションの質がデューデリジェンスの精度を決定づけます。
3.1.1 効率的なQ&Aシートの運用と回答のトラッキングQ&Aプロセスを効率的に進めるためには、体系化されたQ&Aシートの運用が不可欠です。質問と回答を一元管理し、進捗状況を可視化することで、論点の抜け漏れを防ぎ、限られた時間の中で最大限の情報を引き出すことができます。
一般的に、Q&Aシートには以下の項目を設けて管理します。
| 管理番号 | 質問分野 | 質問日 | 質問者 | 質問内容 | 回答期限 | 回答内容 | ステータス | 論点・備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F-001 | 財務 | 2023/10/01 | 〇〇会計事務所 | 2022年度の売上高が前年比で20%増加した具体的な要因について、製品・サービス別の内訳を交えてご教示ください。 | 2023/10/05 | (売り手からの回答を記載) | 回答済み | 正常収益力の分析に影響 |
| L-001 | 法務 | 2023/10/02 | △△法律事務所 | 主要顧客A社との取引基本契約書において、チェンジオブコントロール条項の有無と、該当する場合の具体的な条文内容をご開示ください。 | 2023/10/06 | (売り手からの回答を記載) | 回答済み | クロージング後の事業継続リスク |
Q&Aプロセスを円滑に進めるためのポイントは以下の通りです。
- 質問窓口の一本化: 買い手側の質問はFA(ファイナンシャル・アドバイザー)などを通じて一本化し、売り手側の負担を軽減するとともに、情報の混乱を防ぎます。
- 質問の具体性: 「〇〇について教えてください」といった漠然とした質問ではなく、「△△の資料P.5にある××の勘定科目の内訳をご教示ください」のように、具体的かつ明確な質問を心がけます。
- 優先順位付け: 質問事項に重要度や緊急度を設定し、M&Aのディールに大きな影響を与える可能性のある論点から優先的に解消していきます。
- 回答のトラッキング: 回答期限を設定し、ステータスを継続的に追跡します。回答が不十分な場合は、深掘りするための追加質問を速やかに行います。
デューデリジェンスでは、財務諸表や契約書などの書面情報だけでは分からない「定性的な情報」の把握が極めて重要です。
経営者インタビューは、対象企業の経営陣から直接、事業戦略、組織文化、将来のビジョンなどをヒアリングし、事業の将来性や潜在的なリスクを見極めるための貴重な機会です。
経営者インタビューを成功させる進め方のポイントは以下の通りです。
- 事前の入念な準備: VDRの資料やQ&Aの回答を事前に読み込み、企業のビジネスモデルや業界動向を深く理解した上で、仮説に基づいた質問リストを作成します。
- 信頼関係の構築: 相手を問いただすような高圧的な態度ではなく、事業への敬意を示し、将来のパートナーとして共に成長を目指すという協調的な姿勢で臨むことが、本音を引き出す鍵となります。
- オープンな質問の活用: 「はい/いいえ」で終わる質問だけでなく、「事業を運営する上で最も重要視していることは何ですか?」といったオープンな質問を投げかけ、経営者の価値観や哲学を深く理解します。
- 議事録の作成と共有: インタビューの内容は詳細に議事録として記録し、専門家チームや社内関係者と共有することで、認識の齟齬を防ぎ、後の分析に活かします。
また、売り手側から買い手側に対して事業計画などを説明する「マネジメント・プレゼンテーション」が実施されることもあります。これは、売り手経営陣の事業への理解度や遂行能力、計画の実現可能性を評価する絶好の機会となります。
3.2 専門家レポートの活用と社内報告の進め方各分野の専門家が進めたデューデリジェンスの結果は、専門的なレポートとしてまとめられます。このレポートを正しく理解し、社内の意思決定プロセスに的確にインプットすることが、最終的な投資判断を下す上で不可欠です。
3.2.1 レッドフラッグ・レポート(速報版)の読解と論点整理デューデリジェンスの過程で発見された、M&Aの取引実行を中止させる可能性のある、あるいは取引条件に重大な影響を与えるリスク(ディール・ブレーカー)は、「レッドフラッグ・レポート」や「DD速報会」といった形で早期に報告されます。
この速報版レポートを読解する際の進め方のポイントは、単にリスクをリストアップするだけでなく、以下の視点で論点を整理することです。
- リスクの重要度評価: 発見されたリスクが、事業価値(バリュエーション)にどの程度の影響を与えるのか、定量的に評価を試みます。
- 原因の深掘り: なぜそのリスクが発生しているのか、根本的な原因を分析します。一過性のものか、構造的な問題なのかを見極めることが重要です。
- 対応策の検討: リスクをどのように軽減・回避できるか、具体的な対応策を検討します。価格交渉、最終契約書への条件反映(表明保証など)、PMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)での対応など、複数の選択肢を想定します。
レッドフラッグ・レポートの段階で専門家と密に議論し、論点を整理しておくことで、その後の最終報告や社内での意思決定をスムーズに進めることができます。
3.2.2 取締役会への報告と意思決定プロセスの確立デューデリジェンスの最終報告書が完成したら、その結果を基に、M&Aを実行するかどうかの最終的な意思決定を行うため、取締役会などの社内機関に報告します。この報告は、経営陣が十分な情報に基づいて合理的な経営判断を下すための重要なプロセスです。
取締役会への報告資料には、通常、以下の内容を盛り込みます。
- M&Aの目的と戦略的意義の再確認: 本件M&Aが自社の経営戦略においてどのような位置づけにあるのかを改めて明確にします。
- デューデリジェンスの実施概要: 調査の範囲(スコープ)、期間、体制などを簡潔に説明し、調査の網羅性と信頼性を示します。
- 主要な調査結果(リスクと機会): 財務、税務、法務、ビジネスなど各分野で発見された主要なリスクと、期待されるシナジー効果などの機会を要約して報告します。特に重要なリスクについては、その影響と対応策をセットで説明します。
- 買収価格の妥当性: デューデリジェンスの結果を反映した最終的な企業価値評価(バリュエーション)と、提案する買収価格の妥当性について説明します。
- 最終契約の主要条件案: 価格調整条項や表明保証など、デューデリジェンスの結果を反映した最終契約書の主要な条件について概説します。
- PMIの方向性: M&A成立後の統合プロセス(PMI)における主要な課題と、統合計画の骨子について言及します。
- 決議事項: 取締役会として承認を求める事項(最終契約の締結承認など)を明確に提示します。
デューデリジェンスのマネジメントとは、調査結果を右から左へ流すことではありません。専門家の知見を借りながらリスクと機会を多角的に分析し、それを社内の言葉に翻訳して経営陣の意思決定を支援する、極めて戦略的なプロセスなのです。
【関連】M&Aデューデリジェンスの必要書類 完全ガイド:準備から提出まで網羅4. M&A最終契約に向けたデューデリジェンス結果の反映と進め方
デューデリジェンス(DD)は、対象企業のリスクや課題を洗い出す調査で完結するものではありません。その真価は、調査結果をいかに最終契約条件に反映させ、M&Aの成功確率を高めるかにあります。
この章では、デューデリジェンスの結果を最終契約書(Definitive Agreement)に落とし込み、取引の実行(クロージング)からPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)へと繋げるための具体的な進め方を解説します。
デューデリジェンスで検出されたリスクは、主に「価格(取引価値)」と「将来のリスク分担」という観点から、株式譲渡契約書(SPA)や事業譲渡契約書(APA)などの最終契約書に織り込まれます。売り手と買い手の間で、リスクをどのように負担し合うかを交渉し、法的な拘束力のある文書に明記する極めて重要なプロセスです。
4.1.1 価格調整交渉とアーンアウト条項への落とし込みデューデリジェンスの結果、当初の想定よりも企業価値が低いと判断された場合、買い手は売り手に対して価格の減額交渉を行います。これを価格調整交渉と呼びます。
価格調整の根拠となり得るのは、以下のようなデューデリジェンスでの発見事項です。
- 正常収益力の下振れ:一過性の利益を除いた際の実質的な収益力が想定より低い。
- ネットデット(純有利子負債)の増加:未払残業代、退職給付債務、訴訟引当金などの簿外債務や偶発債務が判明した。
- 運転資本の不足:在庫の陳腐化や回収不能な売掛金の存在により、事業継続に必要な運転資本が想定より多い。
交渉は、デューデリジェンスレポートで示された客観的な事実と金額的影響を根拠に、FA(ファイナンシャル・アドバイザー)を介して行われるのが一般的です。論理的かつ冷静な交渉により、双方が納得できる着地点を探ります。
また、将来の業績の不確実性が高いと判断された場合には、「アーンアウト条項」が活用されます。これは、クロージング時点での支払額を抑え、M&A後の一定期間内に対象会社が特定の業績目標(例:EBITDA、売上高)を達成した場合に、追加の対価(アーンアウト対価)を支払う仕組みです。
これにより、買い手は将来の業績リスクを低減でき、売り手は自社の成長性を証明することで、より高い売却価格を得られる可能性があります。アーンアウトを導入する場合、業績目標の定義や測定方法について、契約書で極めて明確に定めておく進め方が不可欠です。
表明保証条項(Representations and Warranties、以下「R&W」)は、売り手が買い手に対し、対象会社の財務、法務、税務、事業などに関する特定の事項が、契約締結日やクロージング日において真実かつ正確であることを表明し、保証するものです。
デューデリジェンスで発見されたリスクは、このR&Wに具体的に反映させることで、リスクヘッジを図ります。
例えば、法務デューデリジェンスで特定の重要な契約に許認可が必要である可能性が指摘された場合、「対象会社は事業運営に必要な全ての許認可を有効に保有している」という表明保証を求めます。
万が一、この表明保証に違反する事実が後に発覚し、買い手に損害が生じた場合、買い手は売り手に対して契約に基づき損害賠償を請求できます。
近年、この表明保証違反のリスクをカバーするために「表明保証保険(W&I保険)」の活用が進んでいます。これは、表明保証違反による損害を保険会社が補填する制度です。
| 立場 | メリット |
|---|---|
| 買い手 | 売り手の資力に関わらず損害の補填を確保できるため、回収可能性が高まります。また、M&A後も良好な関係を維持したい売り手に対して、直接的な賠償請求を避けられるという利点もあります。 |
| 売り手 | 表明保証違反による偶発的な損害賠償リスクを限定できます。これにより、売却代金を早期に確定させ、株主への分配や再投資に充てることが可能になります(特にプライベート・エクイティ・ファンドにとって重要です)。 |
デューデリジェンスで特定されたリスクの大きさや性質を考慮し、売り手との交渉を通じて、R&Wの内容を精緻化し、必要に応じてW&I保険の活用を検討する進め方が求められます。
4.2 クロージングとPMIへの橋渡しに関する進め方デューデリジェンスの役割は、最終契約の締結を支援するだけではありません。取引を確実に完了させ、M&A後の統合プロセス(PMI)を成功に導くための重要なインプットを提供する役割も担っています。
4.2.1 クロージング前提条件(CPs)の充足確認クロージング前提条件(Conditions Precedent、以下「CPs」)とは、最終契約の締結日からクロージング日までの間に充足されるべき条件のことです。いずれかのCPが満たされない場合、買い手(または売り手)は取引を完了する義務を免除されます。
デューデリジェンスで発見された重要な課題への対応は、このCPsとして設定されることがよくあります。具体的な進め方としては、以下のような項目をCPsに盛り込み、充足状況を継続的にモニタリングします。
- 重要契約の同意取得:チェンジオブコントロール(COC)条項が含まれる重要な取引先やライセンサーから、株主変更に関する事前の同意を取得すること。
- 許認可の取得・維持:事業継続に不可欠な行政上の許認可を問題なく維持、または再取得すること。
- キーパーソンの同意:M&A後も事業に不可欠な役員や従業員(キーパーソン)が、継続して勤務することに同意する書面を提出すること。
- 法令違反の是正:デューデリジェンスで発見された重大な法令違反が、クロージングまでに是正されていること。
これらのCPsが着実に充足されるよう、売り手と密に連携しながら進捗を管理することが、M&Aを円滑に完了させるための鍵となります。
4.2.2 デューデリジェンス結果をインプットとしたPMI計画(100日プラン)の策定M&Aの成否は、クロージング後のPMIが計画通りに進むかどうかに大きく左右されます。そして、効果的なPMI計画は、デューデリジェンスで得られた情報に基づいて策定されます。特に、クロージング直後から実行する「100日プラン」の策定において、デューデリジェンスの結果は極めて重要なインプットとなります。
デューデリジェンスの各分野から得られる情報をPMI計画に落とし込む進め方の例を以下に示します。
| DD分野 | 発見事項の例 | PMI(100日プラン)への反映 |
|---|---|---|
| 財務DD | 月次決算の遅延、原価計算の精度が低い、内部統制に脆弱性がある。 | 経理部門の業務プロセス統合、会計システムの統一、決算早期化プロジェクトの立ち上げ、内部監査部門による業務監査の実施。 |
| 法務DD | 契約書の管理体制が属人的、コンプライアンス規程が未整備。 | 契約書管理システムの導入、法務部門によるコンプライアンス研修の実施、各種規程の見直しと整備。 |
| ビジネスDD | 特定のキーパーソンへの依存度が高い、両社の組織文化に大きな隔たりがある。 | キーパーソンのリテンションプラン(報酬、役職)の策定と実行、両社従業員による合同ワークショップの開催、経営陣からのビジョン共有メッセージの発信。 |
| 人事DD | 人事評価制度や報酬体系に大きな差異がある。 | 新人事制度の設計チームを発足、両社従業員への説明会の実施、報酬体系の統合ロードマップの策定。 |
このように、デューデリジェンスの段階からPMIチームと連携し、発見された課題を具体的なアクションプランにまで落とし込んでおくことが、M&Aによるシナジーを早期に実現し、価値を最大化するための最適な進め方と言えます。
【関連】デューデリジェンス失敗事例から学ぶ!M&Aで後悔しないための全知識5. まとめ
M&Aの成功は、デューデリジェンスの戦略的な進め方にかかっています。本記事で解説した通り、専門家チームの組成から分野別の詳細な調査、Q&Aプロセス、最終契約への反映、そしてPMI計画への橋渡しまで、各フェーズを体系的に進めることが不可欠です。
この一連のプロセスこそが、潜在的リスクを正確に洗い出し、企業価値を適切に評価し、最終的なM&Aの成功確率を最大化する最重要の理由です。


