デューデリジェンス重要ポイント7選:M&Aを成功させるための基礎知識
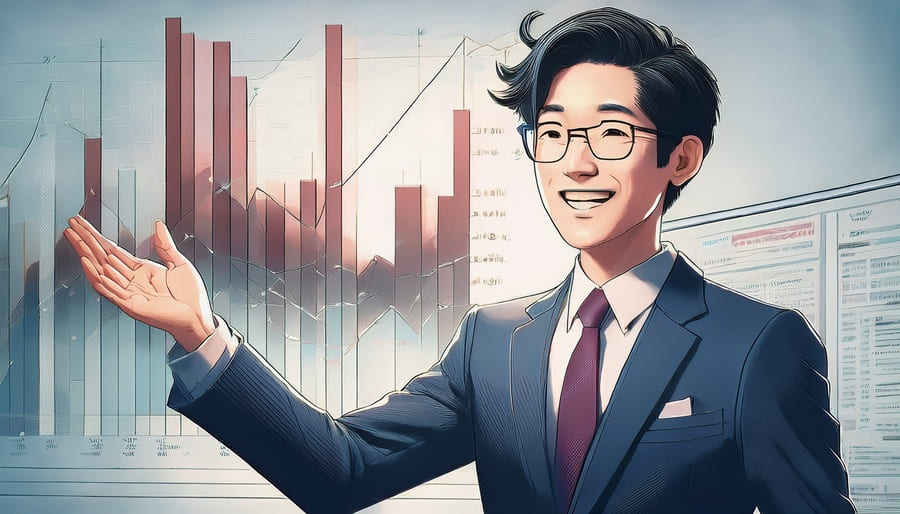
M&Aの成否を分けるデューデリジェンス。しかし、具体的に何を確認すれば良いか悩んでいませんか?本記事では、企業の価値を正しく評価し、簿外債務などの潜在的リスクを回避するための7つの重要ポイントを、財務・法務・事業の分野別に徹底解説します。
M&Aを成功させる鍵は、専門家任せにせず、経営者自身が調査の本質を理解し、主体的に関わることにあります。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&Aの成否を分けるデューデリジェンスの基本と、経営者が押さえるべき重要ポイント
M&A(企業の合併・買収)を成功に導くためには、デューデリジェンス(Due Diligence、以下DD)が極めて重要なプロセスとなります。
DDは、買収対象となる企業の価値やリスクを詳細に調査・分析する「買収監査」であり、このプロセスを省略したり、不十分なまま進めたりすると、予期せぬ簿外債務や訴訟リスクがM&A成立後に発覚し、事業計画が根底から覆される事態になりかねません。
本章では、M&Aの成否の鍵を握るDDの本質と全体像、そして経営者が押さえるべき基本的なポイントについて解説します。
DDは単なる「企業の粗探し」ではありません。M&Aという重要な経営判断を下すために、対象企業の実態を多角的に把握し、買収価格の妥当性や買収後のシナジー効果、潜在的なリスクを正確に見極めるための不可欠な手続きです。
経営者は専門家に任せきりにするのではなく、その本質とプロセスを正しく理解し、主体的に関与することが求められます。
M&AにおけるDDの主な目的は、以下の4つに集約されます。
- 企業価値評価(バリュエーション)の精査:交渉の初期段階で算出された企業価値が、対象企業の実態に基づいているかを検証します。DDの結果、収益性や資産状況に問題が見つかれば、買収価格の減額交渉に繋がります。
- 潜在的リスクの識別と分析:財務諸表に現れない簿外債務、偶発債務、訴訟、許認可の問題、労務トラブルなど、将来的に事業の障害となりうるリスクを洗い出し、その影響度を評価します。
- 最終契約書(DA)への反映:調査で判明したリスクを、価格調整条項や表明保証、補償条項といった形で最終契約書に盛り込み、買い手のリスクをヘッジします。
- M&A後の統合プロセス(PMI)に向けた情報収集:対象企業の組織文化、キーパーソン、業務プロセス、ITシステムなどを事前に把握することで、M&A成立後のスムーズな統合計画(PMI:Post Merger Integration)の策定に役立てます。
DDは一般的に以下のような流れで進められます。
| ステップ | 主な内容 | ポイント |
|---|---|---|
| 1. 専門家チームの組成とキックオフ | M&Aの目的や戦略に基づき、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家を選定し、調査方針やスケジュールを共有します。 | 自社のM&A戦略を深く理解し、業界知見が豊富な専門家を選ぶことが重要です。 |
| 2. 情報要求リスト(Request List)の提出 | 調査に必要な資料のリストを作成し、売り手側に提出します。近年はVDR(バーチャルデータルーム)上で資料が開示されるのが一般的です。 | 網羅的かつ具体的なリストを作成することで、効率的な情報収集が可能になります。 |
| 3. 資料分析とQ&A | 開示された資料を専門家が分析し、不明点や懸念事項について売り手側に質問します。Q&Aは複数回にわたって行われます。 | 回答内容を鵜呑みにせず、追加資料の要求や裏付け調査を徹底します。 |
| 4. マネジメント・インタビュー | 売り手企業の経営陣やキーパーソンに直接ヒアリングを行い、事業の強みや弱み、将来性、組織文化など、資料だけでは分からない定性的な情報を把握します。 | 対象企業のビジネスモデルや経営者のビジョンを深く理解する絶好の機会です。 |
| 5. 現地調査(サイトビジット) | 工場や店舗、本社などの事業拠点を訪問し、現場のオペレーションや従業員の状況、設備の老朽化などを直接確認します。 | 現場の雰囲気や従業員の士気など、数値化できない重要な情報を得ることができます。 |
| 6. 調査報告と最終交渉 | 各分野の専門家が調査結果を報告書にまとめ、発見されたリスクとその影響を買い手に報告します。この報告書を基に、買収価格や契約条件の最終交渉を行います。 | DDで発見されたリスクを交渉材料として活用し、自社に有利な条件を引き出します。 |
DDは、売り手企業の内部情報を詳細に調査するため、通常は初期交渉を経て「基本合意書(LOI: Letter of Intent)」または「覚書(MOU: Memorandum of Understanding)」を締結した後に本格的に開始されます。これは、売り手側が機密性の高い情報を開示するにあたり、買い手側の真剣な買収意欲を確認する必要があるためです。
LOIには、買収価格の目安やM&Aのスキームといった基本条件に加え、買い手にとって非常に重要な「独占交渉権」が定められるのが一般的です。独占交渉権とは、一定期間(通常1〜3ヶ月程度)、売り手が他の買収候補者と交渉することを禁じる権利です。
買い手はDDに多大なコストと時間を投下するため、この権利を確保することで、他社に横取りされるリスクを排除し、安心して調査に専念することができます。LOIの多くの条項に法的拘束力はありませんが、この独占交渉権と、知り得た情報の秘密を保持する「秘密保持義務」については、法的な拘束力を持たせるのが通例です。
DDは時間もコストもかかるため、あらゆる項目を無制限に調査することは現実的ではありません。M&Aを成功させるためには、その目的やディールサイズ(取引規模)に応じて、調査の深さと範囲、すなわち「スコープ」を適切に設定することが不可欠です。
1.2.1 M&Aの目的とディールサイズに応じた調査範囲(スコープ)の決定DDのスコープは、M&Aの目的によって重点を置くべき分野が異なります。例えば、新規事業への参入が目的ならば、対象企業の技術力や市場での競争優位性を評価する「事業DD」の重要度が高まります。
一方、同業他社を買収して規模の経済を追求するなら、収益性や資産内容を精査する「財務DD」や、人員整理の必要性などを探る「労務DD」が重要になります。
また、ディールサイズもスコープ設定に大きく影響します。数百万円規模の小規模な事業譲渡で、数千万円をかけてフルスコープのDDを実施するのは費用対効果に見合いません。このような場合は、財務と法務など、特にリスクが高いと考えられる分野に絞って調査を行うのが合理的です。
逆に、数百億円規模の大型案件や、法規制の異なる海外企業を買収するクロスボーダー案件では、環境、IT、知的財産、コンプライアンスなど、広範かつ詳細なDDが必要となります。
| M&Aの目的 | 特に重要となるDD分野 | 調査のポイント |
|---|---|---|
| 新規事業への参入 | 事業DD、IT・知財DD | ビジネスモデルの持続可能性、技術の陳腐化リスク、市場の成長性、特許の有効性などを重点的に評価する。 |
| 事業規模の拡大(同業買収) | 財務DD、労務DD | 正常収益力、コスト構造、重複する人員や拠点の整理、キーパーソンのリテンション(引き留め)などを精査する。 |
| 周辺事業の獲得 | 事業DD、法務DD | 既存事業とのシナジー効果(売上・コスト)、チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項による契約継続リスクなどを分析する。 |
| 事業承継 | 法務DD、税務DD、労務DD | オーナー経営に起因する潜在的な問題(親族との不明瞭な取引、コンプライアンス体制の不備など)を洗い出す。 |
適切なスコープを設定した上でDDを成功させるには、各分野の専門家との緊密な連携が欠かせません。財務・税務は公認会計士や税理士、法務は弁護士、事業はM&Aアドバイザーや経営コンサルタントといった専門家でチームを組成し、それぞれの知見を結集して多角的な調査を行います。
その際、調査の起点となるのが「情報要求リスト(Request List)」です。これは、売り手側に開示を求める資料を一覧にしたもので、その質がDDの成否を左右すると言っても過言ではありません。効果的なリストを作成するためのポイントは以下の通りです。
- リスク仮説に基づく作成:事前に検討したM&Aの目的や対象企業の事業内容から、「どのようなリスクが潜んでいるか」という仮説を立て、それを検証するために必要な資料は何かを逆算してリストを作成します。
- 網羅性と具体性:一般的なテンプレートを参考にしつつも、対象企業の業種や規模、ビジネスモデルの特性に合わせて項目をカスタマイズします。「契約書一式」のような曖昧な要求ではなく、「直近3年間に締結した売上上位10社との取引基本契約書」のように、具体的かつ明確に要求することが重要です。
- 優先順位付け:すべての情報を一度に要求すると売り手側の負担が大きくなり、対応が遅れる原因となります。M&Aの意思決定に不可欠な最重要資料から優先的に要求し、段階的に調査を進めるのが効率的です。
経営者は専門家チームと密にコミュニケーションを取り、これらのプロセスを主導することで、M&Aの成果を最大化するための質の高いデューデリジェンスを実現できるのです。
【関連】税務デューデリジェンスはなぜ外注すべき?M&Aにおける専門家活用のメリット2. 財務・税務デューデリジェンスにおけるM&Aの意思決定ポイント
M&Aのプロセスにおいて、財務・税務デューデリジェンスは、買収価格の妥当性を判断し、ディールの実行可否を決定するための根幹をなす調査です。
公認会計士や税理士といった専門家が中心となり、対象企業の財務諸表に現れない隠れたリスクを洗い出し、企業の真の価値を明らかにします。ここでは、M&Aの意思決定に直結する財務・税務デューデリジェンスの重要ポイントを解説します。
財務デューデリジェンスの最大の目的は、貸借対照表(B/S)や損益計算書(P/L)などの財務諸表の数字を精査し、対象企業の財政状態と収益性を正確に把握することです。
これにより、適切な買収価格(バリュエーション)の算定や、買収後の経営計画策定に不可欠な情報を得ることができます。
財務諸表上の数値は、必ずしも企業の真の価値を反映しているとは限りません。M&Aの意思決定のためには、「実態」ベースでの資産価値と「正常な」収益力を把握することが不可欠です。
実態純資産の把握:
貸借対照表上の純資産(簿価純資産)に対し、資産・負債を時価で再評価し、簿外の資産・負債を反映させることで「実態純資産」を算出します。これは企業の清算価値に近い概念であり、買収価格の下限を検討する上での重要な指標となります。
- 資産の時価評価:土地や有価証券など、含み損益を持つ資産を時価で評価し直します。
- 不良資産の除外:回収可能性の低い売掛金(滞留債権)や、陳腐化した棚卸資産(不良在庫)など、実質的な価値が乏しい資産を資産価値から控除します。
- 負債の再評価:退職給付引当金などが実態の債務額と乖離していないかなどを確認します。
正常収益力の分析:
損益計算書上の利益から、M&A後に変動する費用や一時的な損益(非経常損益)を除外し、対象企業が本来持つ「稼ぐ力」を測定します。この正常収益力は、将来の事業計画や企業価値評価の基礎となります。M&Aの実務では、正常収益力を示す指標としてEBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)が広く用いられます。
| 調整項目の種類 | 具体例 | 調整の理由 |
|---|---|---|
| 非経常的な損益 | 固定資産売却損益、災害損失、役員退職慰労金 | 一過性のものであり、将来の経常的な収益力を反映しないため。 |
| オーナー関連費用 | 過大な役員報酬、オーナー個人の生命保険料、私的な交際費 | M&A後は発生しない、あるいは適正水準に修正されるため。 |
| 会計方針の差異 | 減価償却方法の変更、引当金の計上基準の差異 | 買い手企業の会計方針と統一し、客観的な収益力を評価するため。 |
財務諸表に計上されていない債務は、買収後に想定外のキャッシュアウトを引き起こす重大なリスクです。また、事業運営に不可欠な運転資本の分析も、買収価格の最終決定や追加の運転資金需要を把握するために極めて重要です。
簿外債務・偶発債務の特定:
帳簿には現れない債務や、将来債務となる可能性のあるリスクを洗い出します。これらが発見された場合、買収価格の減額交渉や、売り手による表明保証の対象となります。
- 未払残業代:サービス残業が常態化している場合、過去に遡って多額の未払賃金支払義務が発生する可能性があります。
- 債務保証:対象企業が他社の借入等を保証している場合、その他社の経営破綻時に保証履行義務が発生します。
- 訴訟リスク:係争中の訴訟で敗訴した場合の損害賠償義務など。
- 環境債務:土壌汚染やアスベスト除去など、将来発生しうる対策費用。
運転資本(Working Capital)の評価:
運転資本は「売上債権+棚卸資産-仕入債務」で計算され、事業を円滑に回すために必要な資金を意味します。デューデリジェンスでは、過去の月次推移などから対象事業における「正常な」運転資本の水準を算定します。クロージング時点の運転資本がこの正常水準から乖離している場合、その差額を買収価格から調整(価格調整)する契約を締結するのが一般的です。また、売掛金の異常な増加や在庫の過大計上は粉飾決算の兆候である可能性もあり、慎重な調査が求められます。
税務デューデリジェンスは、過去の税務申告が適正に行われていたかを確認し、将来の追徴課税などの税務リスクを特定するプロセスです。同時に、M&Aのスキームを検討する上で、対象企業が持つ繰越欠損金などを活用し、税務メリットを最大化する方策を探る重要な役割も担います。
2.2.1 ポイント③:過去の税務申告の妥当性と潜在的な税務リスクの洗い出し過去の法人税、消費税、源泉所得税などの申告内容を詳細にレビューし、税務調査で指摘される可能性のある項目を洗い出します。税務リスクは、買収後に追徴課税や加算税として顕在化するため、事前にその影響額を定量的に把握しておく必要があります。
| 税目 | 主なチェック項目 | 潜在的リスク |
|---|---|---|
| 法人税 | 交際費と会議費の区分、役員賞与の損金性、減価償却資産の耐用年数、グループ会社間取引の価格設定(移転価格税制) | 過年度の申告誤りによる追徴課税、加算税、延滞税の発生。 |
| 消費税 | 課税売上と非課税売上の区分、仕入税額控除の適用要件、国外事業者との取引 | 申告漏れによる追徴課税、仕入税額控除の否認。 |
| 源泉所得税 | 役員や従業員への経済的利益の供与、業務委託契約の実態が雇用契約と判断されるリスク | 源泉徴収漏れによる不納付加算税、延滞税の発生。 |
特定された税務リスクは、その発生可能性と影響額を評価し、買収価格の交渉材料としたり、最終契約書における売り手の表明保証事項に含めたりといった対応を検討します。
2.2.2 ポイント④:繰越欠損金の引継ぎ可否と最適なM&Aスキームの検討税務デューデリジェンスは、リスクの洗い出しだけでなく、M&Aを有利に進めるためのタックスプランニングの側面も持ちます。
繰越欠損金の引継ぎ:
対象企業に税務上の繰越欠損金がある場合、買収後の利益と相殺することで法人税の負担を軽減できる「タックスシールド効果」が期待できます。
しかし、M&Aのスキームや特定の支配関係の変更があった場合など、税法上の規定により繰越欠損金の利用が制限されるケースがあります。デューデリジェンスでは、この引継ぎ・利用が可能かどうかを事前に検証し、期待できる税務メリットを正確に見積もります。
最適なM&Aスキームの検討:
M&Aには株式譲渡、事業譲渡、会社分割、合併など様々な手法(スキーム)があり、どのスキームを選択するかによって当事者の税負担は大きく異なります。
例えば、株式譲渡は手続きが簡便な一方、売り手株主の譲渡所得課税が中心となります。事業譲渡は、買い手にとっては必要な資産・事業のみを取得でき、簿外債務を引き継ぐリスクを遮断できるメリットがありますが、売り手企業に譲渡益に対する法人税が課され、不動産取得税や登録免許税などの流通税も発生します。
税務デューデリジェンスの結果を踏まえ、買い手と売り手双方の税務メリット・デメリットを総合的に勘案し、最も有利なスキームを選択することがM&A成功の鍵となります。
3. 法務・労務デューデリジェンスで見極めるべきM&Aのリスクと交渉ポイント
財務・税務デューデリジェンスが企業の「カネ」に関するリスクを評価するのに対し、法務・労務デューデリジェンスは、企業の事業活動を支える「ヒト・モノ・権利」に潜む法的リスクを網羅的に洗い出す重要なプロセスです。
M&A実行後に事業が継続できなくなったり、想定外の紛争や簿外債務が発覚したりする事態を防ぐため、弁護士や社会保険労務士といった専門家の協力を得て、慎重に進める必要があります。
ここでは、M&Aの成否に直結する法務・労務デューデリジェンスの核心的なチェックポイントを解説します。
3.1 法務デューデリジェンスの核心となる契約・許認可のチェックポイント法務デューデリジェンスの目的は、対象会社の法的側面を精査し、ディールストッパー(M&A取引を中止せざるを得ないほどの重大な問題)の有無を判断すること、そして発見されたリスクを買収価格や最終契約書の条件(表明保証など)に適切に反映させることです。調査範囲は、会社の基本定款から日々の取引契約、知的財産権、訴訟、コンプライアンス体制まで多岐にわたります。
3.1.1 ポイント⑤:チェンジ・オブ・コントロール(COC)条項と重要契約の継続性M&Aにおいて最も注意すべき法的リスクの一つが、「チェンジ・オブ・コントロール(Change of Control、以下COC)条項」です。これは、会社の支配権(株主)が変更された場合に、契約の相手方の事前承諾が必要になったり、契約が自動的に解除されたりする効力を持つ条項を指します。
もし、対象会社の事業の根幹をなす重要な取引先との契約や、不動産の賃貸借契約、金融機関との融資契約などにCOC条項が含まれていた場合、M&Aを実行した途端にその契約が失効し、事業継続が困難になるという致命的な事態に陥る可能性があります。
そのため、主要な契約書をすべて精査し、COC条項の有無とその内容を把握することが不可欠です。
| 契約の種類 | 具体的な契約例 | 確認すべきポイント |
|---|---|---|
| 取引基本契約 | 販売代理店契約、仕入基本契約、業務委託契約 | M&A後も主要な取引先との関係を維持できるか。 |
| ライセンス契約 | ソフトウェアライセンス契約、特許ライセンス契約 | 事業継続に必要なライセンスが失効しないか。 |
| 不動産賃貸借契約 | 本社オフィス、工場、店舗などの賃貸借契約 | 事業拠点を失うリスクはないか。 |
| 融資・リース契約 | 金融機関からの借入契約、設備リース契約 | 期限の利益を喪失し、一括返済を求められないか。 |
COC条項が発見された場合は、契約の相手方と事前に交渉し、M&A後も契約を継続するための同意を取り付ける必要があります。同意が得られない場合は、代替策の検討や、最悪の場合はM&A取引そのものを見直す判断も求められます。
3.1.2 知的財産権、訴訟リスク、事業に必要な許認可の有効性COC条項の確認と並行して、事業の価値や継続性を左右する法的要素を幅広く調査します。特に重要なのが、知的財産権、訴訟リスク、許認可の3点です。
- 知的財産権:対象会社の競争力の源泉である特許権、商標権、著作権などが、法的に有効かつ適切に保護されているかを確認します。権利の帰属(自社保有か、他社からのライセンスか)、有効期限、権利範囲を精査するとともに、第三者の知的財産権を侵害していないかという侵害リスクの有無も調査します。特にIT企業の場合、使用しているソフトウェアのライセンス違反が発覚すると、多額の損害賠償につながるケースがあるため注意が必要です。
- 訴訟リスク:現在係争中の訴訟はもちろん、将来的に訴訟へ発展する可能性のある潜在的な紛争(顧客からのクレーム、元従業員とのトラブル、行政からの指導など)を洗い出します。敗訴した場合の損害賠償額や、企業の評判を損なうレピュテーションリスクを評価し、買収価格に反映させる必要があります。
- 許認可の有効性:対象会社の事業運営に不可欠な許認可(例:建設業許可、古物商許可、人材派遣事業許可など)が、すべて適法に取得・維持されているかを確認します。許認可の種類によっては、M&Aによる株主変更に伴い、承継手続きや再取得が必要になる場合があります。手続きに時間を要することもあるため、M&Aのスケジュールに影響を与えないよう、早期の確認が重要です。
労務デューデリジェンスは、従業員という「ヒト」に関するリスクを特定し、M&A後の円滑な組織統合(PMI:Post Merger Integration)の土台を築くために行われます。特に、帳簿には現れない「簿外債務」の代表格である未払残業代などの労働債務の洗い出しと、事業価値を支えるキーパーソンの流出防止が最重要課題となります。
3.2.1 ポイント⑥:未払残業代などの潜在的労働債務とキーパーソンの特定労務リスクは、買収後に表面化し、多額の偶発債務や組織の混乱を招く可能性があります。特に以下の2点は重点的に調査する必要があります。
1. 潜在的労働債務の洗い出し
財務諸表には記載されないものの、法的には支払い義務を負う可能性のある債務を特定します。
| 調査項目 | 具体的な確認内容 | 潜在的リスク |
|---|---|---|
| 未払残業代 | タイムカード等の勤怠記録と給与台帳の突合、36協定の遵守状況、管理監督者の範囲の妥当性 | 過去2年分(法改正により将来は3年、5年へ)の未払賃金の遡及支払い義務(簿外債務) |
| 退職金・年金制度 | 退職金規程の内容、退職給付引当金の積立状況、確定給付企業年金等の制度設計 | 想定外の退職金支払いや年金制度の巨額な積立不足 |
| 労働紛争 | 過去及び現在の解雇、ハラスメント、労働災害等に関する紛争の有無 | 損害賠償請求や訴訟への発展、従業員の士気低下 |
| 社会保険・労働保険 | 加入義務者の加入状況、保険料の算定・納付の正確性 | 行政からの追徴金や延滞金の発生 |
これらの潜在的債務は、M&A後に労働基準監督署の調査や従業員からの訴えによって顕在化することが多く、買収価格の算定において正確に評価し、リスクとして織り込む必要があります。
2. キーパーソンの特定とリテンションプランの検討
M&Aの成功は、対象会社の事業価値を維持・向上させられるかにかかっています。その価値を支えているのが、特定の技術を持つエンジニア、重要な顧客との関係を築いている営業担当者、独自のノウハウを持つ役員などの「キーパーソン」です。
労務デューデリジェンスでは、誰がキーパーソンなのかを特定し、彼らがM&Aに対してどのような考えを持っているのか、処遇に不満はないかなどを把握します。
M&Aによる環境変化への不安からキーパーソンが離職してしまうと、期待したシナジー効果が得られないばかりか、事業価値そのものが大きく毀損する恐れがあります。そのため、必要に応じて役職の維持や報酬の見直し、ストックオプションの付与といったリテンション(引き留め)策を早期に検討・準備しておくことが、M&A成功の鍵となります。
【関連】デューデリジェンスの人事DD・労務DDは外注で効率化!外注する際のチェックリスト4. 事業・ITデューデリジェンスとPMIを見据えたM&A成功の最終ポイント
財務・税務・法務デューデリジェンスが、対象企業の「過去から現在」におけるリスクを精査する「守り」の調査であるとすれば、事業・ITデューデリジェンスはM&Aによって「未来」の価値をいかに創造するかを見極める「攻め」の調査と言えます。
M&Aの本来の目的である事業成長の実現と、統合後の円滑なオペレーション(PMI:Post Merger Integration)の成功は、このフェーズの調査の質に大きく左右されます。
事業デューデリジェンス(ビジネスデューデリジェンス)の最大の目的は、対象企業の事業価値を正確に評価し、買収によって期待されるシナジー効果が本当に実現可能か、その大きさはどの程度か、を具体的に明らかにすることです。ここでは、事業の将来性を見極め、M&Aの成果を最大化するための重要なポイントを解説します。
4.1.1 ポイント⑦:ビジネスモデルの強みと市場における競争優位性の評価対象企業がどのようにして利益を生み出しているのか、その「稼ぐ力」の源泉を深く理解することが不可欠です。表面的な財務数値だけでは見えない、事業の持続可能性や成長ポテンシャルを評価します。
具体的には、以下の視点で分析を進めます。
- ビジネスモデルの分析:誰に(顧客)、何を(価値)、どのように提供し(バリューチェーン)、どうやって収益を上げているのか(収益モデル)を解明します。特に、独自の技術、強力なブランド、安定した顧客基盤、模倣困難なサプライチェーンなど、収益の源泉となっている強みを特定します。
- 市場分析:対象企業が属する市場の規模、成長性、今後のトレンド、規制の動向などを評価します。成長市場にいるのか、成熟・衰退市場にいるのかによって、将来の収益予測は大きく変わります。
- 競争優位性の評価:競合他社と比較して、対象企業が持つ優位性は何かを客観的に分析します。価格競争力、品質、技術力、販売チャネル、顧客ロイヤルティなど、競争の源泉となっている要素(KBF:Key Buying Factor)を特定し、その持続可能性を評価します。SWOT分析などのフレームワークを用いて、内部環境(強み・弱み)と外部環境(機会・脅威)を整理することも有効です。
| 分類 | 分析項目 | 具体的な評価ポイントの例 |
|---|---|---|
| 強み (Strengths) | 内部環境(プラス要因) | 特許技術、高いブランド認知度、優秀な人材、強固な顧客基盤、効率的な生産体制 |
| 弱み (Weaknesses) | 内部環境(マイナス要因) | 特定の大口顧客への高い依存度、老朽化した設備、脆弱な財務体質、人材の流出リスク |
| 機会 (Opportunities) | 外部環境(プラス要因) | 市場の拡大、規制緩和、新たな技術の登場、競合の撤退、ライフスタイルの変化 |
| 脅威 (Threats) | 外部環境(マイナス要因) | 市場の縮小、規制強化、代替品の登場、新規参入による競争激化、原材料価格の高騰 |
M&Aの投資対効果を測る上で、シナジー効果を具体的に数値化することは極めて重要です。「シナジーが期待できる」という曖昧な期待だけでは、高値掴みにつながるリスクがあります。
シナジーは大きく「売上シナジー」と「コストシナジー」に分けられ、それぞれについて実現可能性と効果額を定量的に分析します。
売上シナジー:
両社の強みを組み合わせることで生まれる売上増加の効果です。一般的に実現の難易度は高いとされますが、M&Aの成功を大きく左右します。
- クロスセル/アップセル:買い手の顧客基盤に売り手の製品・サービスを、またはその逆を販売する。
- 販路拡大:互いの販売チャネルや営業網を相互活用し、新たな地域や顧客層へ展開する。
- ブランド力の向上:両社のブランドを組み合わせることで、市場での信頼性や認知度を高める。
コストシナジー:
事業の重複をなくし、効率化を進めることで生まれるコスト削減の効果です。売上シナジーに比べて実現可能性が高く、計画的に進めやすいとされています。
- 仕入れ・調達コストの削減:仕入れ量を増やすことによるバイイングパワーの向上。
- 製造・物流拠点の統廃合:重複する工場の閉鎖や物流網の最適化。
- 管理部門の効率化:経理、人事、総務などのバックオフィス機能の統合。
- 研究開発費の効率化:重複する研究開発テーマの集約。
これらのシナジー項目について、「いつまでに」「誰が」「何を」実行すれば、「いくら」の効果が見込めるのか、具体的なアクションプランとKPI(重要業績評価指標)に落とし込み、その実現可能性を厳しく評価することが求められます。
4.2 統合後(PMI)を見据えたITデューデリジェンスのポイント現代の企業経営においてITシステムは事業の根幹をなす神経網です。ITデューデリジェンスは、単に保有しているIT資産を評価するだけでなく、M&A後の事業統合(PMI)を円滑に進められるか、想定外の追加投資や事業継続リスクが潜んでいないかを見極めるために不可欠なプロセスです。
IT統合の失敗は、シナジー実現の遅延や、最悪の場合、事業停止に直結する重大なリスクとなります。
両社のITシステムをどのように統合していくかは、PMIにおける最重要課題の一つです。ITデューデリジェンスでは、現状のシステムを正確に把握し、統合にかかるコストや期間、難易度を事前に評価します。
評価すべき主要なポイントは以下の通りです。
| 評価項目 | 具体的なチェックポイント |
|---|---|
| 基幹システム(ERP) | SAP、Oracle、国産パッケージなど、利用しているERPの種類は何か。カスタマイズの度合いはどの程度か。 |
| インフラ環境 | オンプレミスかクラウド(AWS, Azureなど)か。サーバーやネットワーク機器の老朽化は進んでいないか。 |
| 技術的負債 | 独自開発されたレガシーシステムや、サポートが終了したOS・ミドルウェアは存在しないか。ドキュメントは整備されているか。 |
| IT人材・組織体制 | システムを運用・保守できる人材は社内にいるか。外部ベンダーへの依存度はどの程度か。 |
| 追加投資(CAPEX/OPEX) | システム統合に必要なハードウェア、ソフトウェアライセンス、開発委託費はいくらか。統合後の運用・保守費用はどの程度増減するか。 |
特に、長年改修を繰り返してきた独自開発のレガシーシステムは「技術的負債」となり、統合の大きな足かせとなる可能性があります。その存在を早期に特定し、刷新や改修にかかる費用(追加CAPEX)をM&Aの買収価格や事業計画に織り込むことが重要です。
4.2.2 情報セキュリティリスクとデータガバナンス体制の評価M&Aによって、これまで気づかなかった重大な情報セキュリティリスクを引き継いでしまう可能性があります。また、データの管理体制が不十分な場合、統合後のデータ活用が困難になるだけでなく、法令違反のリスクも生じます。
以下の点は、最低限確認すべき重要な項目です。
- セキュリティインシデント履歴:過去に情報漏洩やサイバー攻撃などの重大なインシデントが発生していないか。その際の対応は適切だったか。
- 脆弱性管理:サーバーやネットワーク機器、ソフトウェアの脆弱性診断を定期的に実施し、適切に対処しているか。
- データガバナンス:個人情報保護法やGDPR(EU一般データ保護規則)など、関連法規を遵守したデータ管理体制が構築されているか。顧客データや機密情報のアクセス管理は適切か。
- ソフトウェアライセンス:使用しているソフトウェアのライセンス契約は適切に管理されているか。ライセンス違反(不正コピー)の状態になっていないか。
これらの調査を通じて、買収後に発覚しうる潜在的なリスクを洗い出し、必要な対策費用を見積もるとともに、統合後のガバナンス体制をどのように構築していくべきかの計画を立てることが、M&Aを真の成功に導くための最後の鍵となります。
【関連】ITデューデリジェンスの外注でリスクを最小化!賢い依頼先の見つけ方5. まとめ
本記事では、M&Aを成功に導くデューデリジェンスの7つの重要ポイントを解説しました。財務・法務・税務から事業・ITに至るまで、多角的な調査は潜在リスクの特定だけでなく、企業価値やシナジー効果を正確に評価し、統合後(PMI)の成功を見据える上で不可欠です。
M&Aの目的を明確にし、公認会計士や弁護士など専門家と連携してこれらのポイントを網羅的に検証することが、ディール成功の鍵となります。


