ITデューデリジェンスの外注でリスクを最小化!賢い依頼先の見つけ方
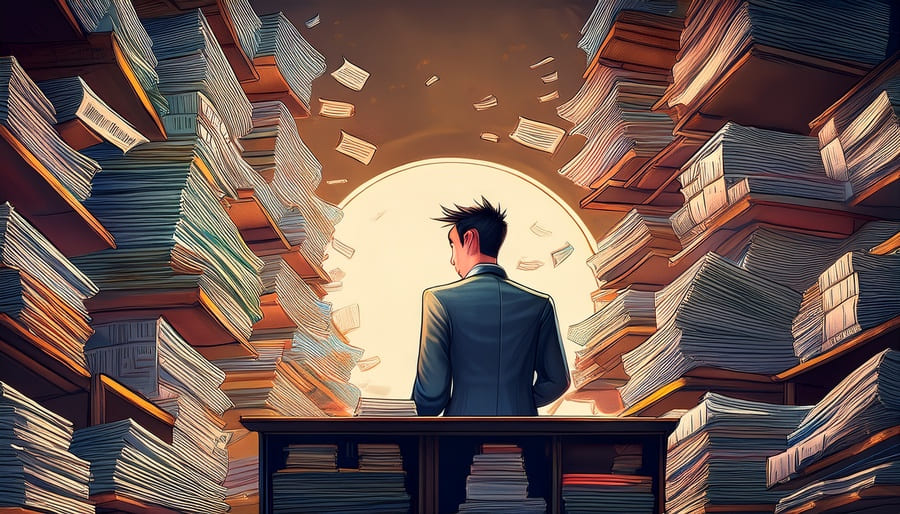
M&AにおけるITデューデリジェンスは、成功の鍵を握る重要なプロセスです。見過ごされがちなITリスクは、サイバーセキュリティ問題やレガシーシステムによる技術的負債として、M&A後の巨額な簿外債務やPMI(経営統合プロセス)の阻害要因となりかねません。
本記事では、ITデューデリジェンスを専門家へ外注することが、これらのリスクを最小化し、M&Aを加速させる上で不可欠であると結論付けます。外注の具体的なメリット、失敗しないための注意点、そして賢い依頼先の見つけ方まで、M&Aを成功に導く実践的な知見が得られます。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&A成功の鍵を握るITデューデリジェンス:なぜ専門家への外注が必須なのか
M&A(企業の合併・買収)は、企業の成長戦略において重要な手段ですが、成功の鍵を握るのは財務や法務といった側面だけではありません。近年、M&AにおけるITデューデリジェンスの重要性が飛躍的に高まっています。
買収対象企業のIT環境が抱える潜在的なリスクや技術的負債を見誤ると、M&A後のPMI(経営統合プロセス)が滞り、予期せぬコストや事業機会の損失を招く可能性があります。
特に「デューデリジェンス IT 外注」という選択は、M&Aを成功に導く上で不可欠な戦略となりつつあります。専門家による客観的かつ深い洞察は、自社だけでは見落としがちなITリスクを洗い出し、M&Aの意思決定をより確実なものにするからです。
本章では、M&AにおいてITデューデリジェンスの専門家への外注がなぜ必須なのか、その理由を詳しく解説します。
M&Aの交渉過程では、財務や法務といった目に見えるリスクに焦点が当たりがちです。しかし、企業の基盤を支えるITシステムや情報セキュリティ体制に潜むリスクは、見過ごされるとM&A後に巨額の損失や事業継続の危機を招く「簿外債務」となり得ます。ここでは、経営者が陥りがちなM&AのITリスクについて深掘りします。
1.1.1 サイバーセキュリティと個人情報保護:巨額の簿外債務となる可能性現代において、サイバーセキュリティは企業の存続を左右する最重要課題の一つです。買収対象企業のセキュリティ対策が不十分であったり、個人情報保護体制に脆弱性があったりする場合、M&A後に情報漏洩やサイバー攻撃といった重大なインシデントが発生するリスクを抱えることになります。
ひとたび情報漏洩が発生すれば、多額の損害賠償、ブランドイメージの失墜、顧客離れ、事業活動の停止など、計り知れない損害が発生します。これはM&A後に買い手企業が負うこととなる、まさに「巨額の簿外債務」です。個人情報保護法やGDPR(一般データ保護規則)といった法規制への対応状況も、厳しく評価されるべきポイントです。
ITデューデリジェンスの外注は、これらの潜在的なセキュリティリスクを専門家の目で洗い出し、M&Aの意思決定前にその影響度と対策コストを正確に把握するために不可欠です。
| リスク要素 | 潜在的な影響 | 主な評価項目 |
|---|---|---|
| サイバーセキュリティ対策の不備 | 情報漏洩、システム停止、業務妨害、風評被害、損害賠償 | セキュリティポリシー、インシデント対応体制、脆弱性診断結果、アクセス管理、従業員教育 |
| 個人情報保護体制の脆弱性 | 法規制違反(個人情報保護法、GDPRなど)、行政指導、訴訟、ブランド毀損 | 個人情報管理規程、同意取得状況、データ保管場所、委託先の管理、データ消去プロセス |
| 過去のインシデント隠蔽 | M&A後の発覚による信用失墜、追加コスト、法的責任 | 過去のインシデント記録、対応履歴、再発防止策 |
M&Aの目的の一つは、ITシステムの統合による業務効率化やシナジー効果の創出です。しかし、買収対象企業が長年使い続けてきた老朽化したシステム(レガシーシステム)や、場当たり的な改修によって複雑化したコード(技術的負債)を抱えている場合、これがPMIを著しく阻害する要因となります。
レガシーシステムは、現代のビジネス要件に対応できず、保守運用コストが高騰しがちです。また、新しいシステムとの連携が困難であるため、M&A後のシステム統合に多大な時間と費用を要し、計画されたシナジー効果が発揮されないばかりか、かえって業務効率を低下させることにもなりかねません。
技術的負債は、システムの安定性や拡張性を損ない、将来的な改修や機能追加の足かせとなります。
これらのITリスクを事前に把握せずM&Aを進めると、統合コストが当初の想定をはるかに超えたり、PMI期間が長期化したりする結果を招きます。ITデューデリジェンスの外注は、これらの技術的課題を早期に特定し、PMI計画に織り込むための重要なステップです。
| 課題要素 | PMIへの影響 | 主な評価項目 |
|---|---|---|
| レガシーシステム | 統合コスト増大、PMI期間長期化、業務非効率、システムダウンリスク | システム稼働年数、利用技術、ベンダーサポート状況、保守履歴、互換性 |
| 技術的負債 | システムの不安定化、改修困難、セキュリティ脆弱性、運用コスト増 | ソースコードの品質、ドキュメントの有無、開発体制、テストカバレッジ |
| IT人材の不足・流出 | システム維持困難、PMI推進力低下、ノウハウ喪失 | IT部門の組織体制、スキルセット、主要IT担当者の離職リスク |
M&AにおけるITデューデリジェンスの重要性は理解しつつも、「自社のIT部門で対応できるのではないか」と考える経営者もいるかもしれません。
しかし、現代の複雑なIT環境とM&A特有の状況を鑑みると、自社だけで網羅的かつ客観的な評価を行うことには限界があります。このセクションでは、なぜITデューデリジェンスの外注が不可欠なのか、その理由を深掘りします。
今日の企業IT環境は、オンプレミスの基幹システムからクラウドサービス(SaaS、PaaS、IaaS)、IoTデバイス、モバイルアプリ、RPA、AIなど、多岐にわたる技術要素で構成されています。
これらIT資産は、インフラ、アプリケーション、ネットワーク、データ、セキュリティ、ライセンスといった様々な側面から評価される必要があり、その複雑性は増す一方です。
一般的な企業のIT部門は、日々の運用保守や既存システムの改善が主な業務であり、M&Aという特殊な状況下で、買収対象企業の多岐にわたるIT資産を網羅的に、かつ専門的な知見をもって評価するための経験やリソースが不足しているケースがほとんどです。
特に、対象企業の業界特有のシステムや、特定の技術スタックに対する深い知見は、外部の専門家でなければ持ち得ないものです。ITデューデリジェンスの外注は、この専門性のギャップを埋めるための最も効果的な手段となります。
M&Aの交渉においては、売り手側は自社のIT資産やシステムに関する情報を、できるだけ有利に開示しようとする傾向があります。一方で、買い手側の自社IT部門も、買収後のシステム統合を前提とした期待や、既存の自社システムとの比較において、無意識のうちにバイアスがかかる可能性があります。
このような状況下で、ITデューデリジェンスを自社のみで行うと、潜在的なリスクや問題点を見落とすリスクが高まります。外部の専門家は、売り手・買い手双方の利害関係から独立した「中立的な第三者」として、客観的かつ厳正な評価を行うことができます。
彼らは過去の豊富な経験に基づき、企業が隠したがる情報や、自社では気づきにくいリスク要因を公平な視点で洗い出すことが可能です。
この客観的な評価は、M&Aの交渉において買い手企業が有利な条件を引き出すための根拠となったり、M&A後の予期せぬトラブルを未然に防いだりするために極めて重要です。専門家への「デューデリジェンス IT 外注」は、M&Aにおける情報非対称性を解消し、より健全でリスクの少ない意思決定を支援する上で不可欠なのです。
【関連】デューデリジェンスの費用相場はいくら?種類別料金とコストを抑える全知識2. M&Aを加速させるITデューデリジェンスの外注効果と注意点
M&Aのプロセスは、市場の変動や競合他社の動向により、迅速な意思決定が求められる時間との戦いです。ITデューデリジェンスを専門家に外注することで、短期間で質の高い調査報告書を得られ、経営層の意思決定を強力に支援します。
外注先の専門家は、買収対象企業のIT資産、システム構成、運用状況、セキュリティ対策、ITガバナンス体制などを客観的かつ網羅的に評価します。この調査報告書には、潜在的なITリスク(例:脆弱なサイバーセキュリティ対策、老朽化したレガシーシステム、過剰なソフトウェアライセンス費用、将来的な技術的負債)だけでなく、M&A後のIT統合で実現可能なシナジー効果や改善点も具体的に示されます。
これにより、経営層はIT面からのリスクと機会を正確に把握し、より迅速かつ的確なM&Aに関する最終的な意思決定を下すことが可能になります。特に、複雑化するIT環境においては、専門家の中立的な視点と深い知見が不可欠であり、M&Aの成否を左右する重要な要素となります。
2.1.2 IT統合コストの正確な把握とシナジー効果の最大化M&A後のPMI(経営統合プロセス)において、IT統合は最も大きなコスト要因の一つとなることが少なくありません。ITデューデリジェンスを外注することで、専門家が既存システムの評価を通じて、将来的なシステム移行、改修、新規導入にかかる具体的なコストを詳細に試算します。
これには、ハードウェア・ソフトウェアの購入費用、ライセンス費用、運用・保守費用、システム開発費用、そして人件費などが含まれます。
この正確なコスト予測は、M&Aの買収価格交渉における重要な根拠となるだけでなく、PMI計画における予算策定の精度を飛躍的に高めます。さらに、ITデューデリジェンスで特定されたIT資産の重複排除や標準化、クラウド移行によるコスト削減、業務プロセスの効率化といったシナジー効果の最大化に向けた具体的な戦略立案にも貢献します。
これにより、M&AのROI(投資対効果)を向上させ、長期的な企業価値向上に繋げることが可能となります。
ITデューデリジェンスの外注において、「丸投げ」は最も避けるべき行為です。依頼側がM&Aの目的やITデューデリジェンスで何を明らかにしたいのかを明確にせず、全てを外注先に任せてしまうと、期待外れの成果物や認識齟齬が生じるリスクが非常に高まります。
これを防ぐためには、RFI(情報提供依頼書)やRFP(提案依頼書)を適切に活用し、依頼する側の要件を具体的に提示することが不可欠です。RFIでは、自社の現状やM&Aの背景、外注先に求める大まかな役割などを説明し、外注候補企業から情報や知見を引き出します。
RFPでは、調査の目的、対象範囲(スコープ)、期待する成果物、納期、予算などを詳細に記述し、具体的な提案を求めます。これにより、外注候補企業はM&Aの意図を正確に理解し、最も適切な調査計画と見積もりを提示できるようになります。
| 項目 | RFI(情報提供依頼書) | RFP(提案依頼書) |
|---|---|---|
| 目的 | 外注候補企業の情報収集、市場動向の把握、自社の要件整理 | 具体的な課題解決に向けた提案、見積もりの取得 |
| 段階 | ベンダー選定の初期段階 | ベンダー選定の中・後期段階 |
| 内容 | 企業概要、実績、得意分野、技術力、料金体系の概要など | 調査目的、スコープ、期待成果物、納期、予算、評価基準など |
| 期待効果 | 幅広い選択肢の中から最適なパートナーを見つける準備 | 具体的な計画に基づいた、質の高い提案と最適なパートナーの選定 |
ITデューデリジェンスの外注契約を結ぶ際には、契約形態がその後のプロジェクト進行や責任範囲に大きな影響を与えるため、準委任契約と請負契約の違いを正確に理解しておくことが重要です。
準委任契約は、特定の業務の遂行を委任する契約であり、成果物の完成を保証するものではありません。外注先は善良な管理者の注意義務(善管注意義務)をもって業務を遂行し、その業務に要した工数や時間に対して報酬が支払われるのが一般的です。
ITデューデリジェンスのように、調査範囲が不確定な部分があったり、専門家の知見を借りて多角的に評価を進めたい場合に適しています。
一方、請負契約は、特定の成果物の完成を約束する契約です。外注先は契約で定められた成果物を完成させる義務を負い、その成果物の納品に対して報酬が支払われます。例えば、特定のシステムの脆弱性診断や、明確な仕様に基づいたシステム開発など、成果物の定義が明確な場合に用いられます。
ITデューデリジェンスでは、未知のリスクを探る性質上、調査範囲が柔軟に変動する可能性があるため、準委任契約が採用されるケースが多く見られます。
しかし、契約内容によっては成果物の定義を明確にすることで、請負契約に近い形で進めることも可能です。契約締結前に、どの契約形態がM&Aの目的と調査内容に最も合致するかを十分に検討し、責任範囲や報酬体系を明確にすることが不可欠です。
| 項目 | 準委任契約 | 請負契約 |
|---|---|---|
| 契約の目的 | 業務の遂行(労働力の提供、知見の活用) | 成果物の完成 |
| 報酬の対象 | 業務遂行に要した工数・時間 | 完成した成果物の納品 |
| 責任範囲 | 善管注意義務に基づいた業務遂行 | 成果物の完成義務、瑕疵担保責任 |
| 適したケース | 調査、コンサルティング、アドバイザリーなど、成果が不確定な業務 | システム開発、ウェブサイト制作など、成果物が明確な業務 |
3. 賢い依頼先の見つけ方:M&Aを成功に導くITデューデリジェンスの外注パートナー選定術
M&AにおけるITデューデリジェンス(ITDD)は、買収対象企業のIT資産や潜在的なリスクを正確に評価し、統合後の成否を左右する極めて重要なプロセスです。この複雑なITDDを外部の専門家に依頼する際、適切なパートナーを選定することは、M&Aの成功に直結します。
ここでは、信頼できる外注先を見極め、費用対効果の高いパートナーと契約するための具体的な選定術をご紹介します。
ITデューデリジェンスの質は、依頼するパートナーの専門性に大きく依存します。多岐にわたるIT領域を網羅し、かつ特定の業界知識を持つ専門家を選びましょう。
3.1.1 インフラ、アプリケーション、セキュリティ、ITガバナンスの網羅性買収対象企業のIT環境は、サーバーやネットワークといったITインフラから、業務を支えるアプリケーション、情報漏洩を防ぐセキュリティ対策、そしてそれらを統制するITガバナンスまで、多岐にわたります。
これらの要素全てを包括的に評価できる専門性が必要です。パートナーが提供するサービスが、以下の各領域において深い知見と実績を有しているかを確認しましょう。
| 評価領域 | 主なチェックポイント | 評価の重要性 |
|---|---|---|
| ITインフラ | サーバー、ネットワーク、データセンター、クラウド環境の現状と老朽化度、キャパシティ、運用体制、ベンダー構成 | 統合後の安定稼働、運用コスト増要因、移行リスク、技術的負債の特定 |
| アプリケーション | 基幹システム、業務アプリケーションの機能、カスタマイズ状況、ライセンス、保守体制、ベンダーロックインの有無、SaaS利用状況 | 業務継続性、統合後のシナジー効果、技術的負債、ライセンスコンプライアンスの評価 |
| セキュリティ | 情報セキュリティポリシー、アクセス管理、脆弱性診断、インシデント対応体制、個人情報保護法対応状況、サイバー攻撃対策 | サイバーリスク、情報漏洩リスク、法的・社会的責任、レピュテーションリスクの評価 |
| ITガバナンス | IT戦略、組織体制、IT予算管理、プロジェクト管理、IT資産管理の成熟度、コンプライアンス体制 | IT投資の適正性、PMI(経営統合プロセス)の円滑化、経営戦略との整合性、組織的リスクの特定 |
| データ管理 | データ構造、データ品質、データ移行の難易度、データプライバシー規制への対応状況 | データ統合の複雑性、ビジネスインテリジェンスへの影響、法的リスクの評価 |
これらの領域全てにおいて、深い知見と実績を持つパートナーを選ぶことが、網羅的かつ質の高いITデューデリジェンスを実現する鍵となります。特に、最新のクラウド技術やサイバーセキュリティ動向への理解は不可欠です。
3.1.2 対象企業の業種・業界特有システムへの知見特定の業種・業界には、そのビジネスモデルに特化したシステムや、厳格な規制が存在します。例えば、金融業界における基幹システムやレギュレーション対応システム、製造業における生産管理システム(ERPやMES)、医療業界における電子カルテシステムなど、業界固有の知識がなければ正確な評価は困難です。
依頼を検討するパートナーが、対象企業の属する業界でのITデューデリジェンス経験や、関連システムの知見を豊富に持っているかを確認しましょう。
過去のプロジェクト事例や、担当コンサルタントの経歴、保有資格(例:ITコーディネータ、情報処理安全確保支援士など)を詳細にヒアリングし、その専門性が本物であるかを見極めることが重要です。業界特有の慣習やリスクを理解しているかどうかが、デューデリジェンスの深度を大きく左右します。
ITデューデリジェンスの外注費用は決して安価ではありません。しかし、コストの安さだけで選ぶと重要なリスクを見落とす可能性があり、結果としてM&Aの失敗や追加コスト発生に繋がりかねません。品質とコストのバランスを見極め、費用対効果の高いパートナーを選びましょう。
3.2.1 料金体系の比較:固定報酬とタイムチャージITデューデリジェンスの料金体系は、主に固定報酬型とタイムチャージ型に大別されます。それぞれの特徴を理解し、プロジェクトの性質や予算に合わせて最適な形式を選択することが重要です。
| 料金体系 | 特徴 | メリット | デメリット | 適したケース |
|---|---|---|---|---|
| 固定報酬 | 事前に定められたスコープと成果物(報告書など)に対して、総額が固定される契約形態。 | 予算が明確で、追加費用のリスクが低い。費用計画が立てやすい。 | スコープ変更や想定外の事態への対応が難しい。調査が限定的になる可能性。 | 調査範囲が明確で、予測可能なプロジェクト。予算上限が厳格な場合。 |
| タイムチャージ | コンサルタントの稼働時間(人日単価)に応じて料金が発生する契約形態。 | スコープの柔軟な変更が可能。詳細な調査や深掘りが必要な場合に柔軟に対応できる。 | 総額が読みにくい。プロジェクトの進捗管理や稼働時間管理が重要になる。 | 調査範囲が不確定、深掘りが必要なプロジェクト。M&A交渉の状況に応じて柔軟に対応したい場合。 |
見積もり段階で、各料金体系のメリット・デメリットを十分に説明してもらい、自社のニーズに最も合致する形式を選びましょう。また、追加料金が発生する条件、成果物の定義、報告会の回数などについても明確に確認しておくことが不可欠です。透明性の高い料金提示を行うパートナーは信頼性が高いと言えます。
3.2.2 実績と評判:ケーススタディとリファレンスチェックの活用パートナー選定において、過去の実績と業界内での評判は非常に重要な判断材料となります。表面的な情報だけでなく、深く掘り下げて確認しましょう。
まず、パートナーが公開しているケーススタディや成功事例を詳しく確認します。特に、対象企業の業種や規模に近いM&A案件でのITデューデリジェンス経験があるか、どのような課題を特定し、どのような提言を行ったのかを具体的に把握することが重要です。具体的な企業名が公開されていなくとも、プロジェクトの概要や成果からその能力を推し量ることができます。
さらに、可能であればリファレンスチェックを依頼することも有効です。過去にそのパートナーを利用した企業から、実際のサービス品質、担当者の対応、報告書の質、プロジェクト管理能力、コミュニケーション能力などについて直接意見を聞くことで、より客観的な評価を得られます。
ただし、M&A関連のプロジェクトは秘密保持契約(NDA)が厳しいため、リファレンス提供が難しい場合もあります。その際は、NDAの範囲内で可能な情報提供を依頼し、誠実な対応を評価基準の一つとしましょう。
業界内の評判や口コミも参考にすべきですが、匿名情報や信憑性の低い情報には注意が必要です。信頼できる情報源からの評価を重視し、総合的に判断することが賢明です。また、パートナーが所属する業界団体や専門家コミュニティでの活動実績も、専門性の高さを示す指標となり得ます。
【関連】M&Aデューデリジェンスの流れをステップごとに完全理解4. M&A後のPMIを見据えたITデューデリジェンスの外注戦略
ITデューデリジェンス(ITDD)は、M&AにおけるITリスクの洗い出しに留まらず、その後の経営統合プロセス(PMI: Post Merger Integration)の成否を大きく左右します。
外注パートナーを選定する際には、単に現状分析能力だけでなく、PMIを見据えた視点を持っているかどうかが極めて重要になります。ここでは、ITDDの結果をいかにPMIへスムーズに連携させるか、そして契約締結前に最終確認すべきポイントについて解説します。
M&Aの成功は、デューデリジェンスで特定された課題をPMIでいかに解決し、シナジー効果を最大化できるかにかかっています。ITDDの結果がPMIのIT統合計画に直接反映されるような、シームレスな連携が求められます。
4.1.1 調査フェーズで特定した課題のPMI計画への反映ITデューデリジェンスの調査フェーズで特定されたIT関連の課題は、単なるリストアップで終わらせてはなりません。これらの課題は、M&A後のPMI計画に具体的に反映され、解決に向けたロードマップが描かれる必要があります。
例えば、サイバーセキュリティの脆弱性が発見された場合、PMI計画では統合後のセキュリティポリシーの統一、具体的な対策導入スケジュール、責任体制の明確化などが盛り込まれるべきです。
また、対象企業が抱えるレガシーシステムや技術的負債は、システム統合の障壁となり、将来的な運用コスト増大やビジネス展開の足かせとなる可能性があります。これらの課題に対しては、システムの刷新、段階的な移行計画、あるいはクラウド移行戦略など、具体的な解決策をPMIの初期段階から検討し、計画に落とし込むことが不可欠です。
外注パートナーが提供するITDD報告書が、単なるリスクの指摘に留まらず、それぞれの課題に対する推奨される解決策や、PMIにおける優先順位付けまで踏み込んでいるかを確認することが重要です。これにより、M&A後のIT統合プロジェクトを円滑に進めるための具体的な基盤が構築されます。
4.1.2 IT統合計画(Day1、Day100プラン)策定支援の有無M&A後のIT統合は、Day1(統合初日)から迅速かつ確実に進める必要があります。特に、業務継続性に関わる基幹システムの稼働、ネットワーク接続、メールシステムや共通アカウントの利用開始など、統合初日にクリアすべきIT要件は多岐にわたります。
さらに、Day100(統合後約3ヶ月)までには、主要なシステム統合やデータ移行、セキュリティ基盤の統一など、より広範なIT統合目標を達成するためのロードマップが求められます。
信頼できるITデューデリジェンスの外注パートナーは、調査結果に基づき、これらのDay1、Day100プラン策定を支援する能力を持っています。対象企業のIT環境を深く理解している専門家が、現実的かつ実現可能なIT統合計画の策定に参画することで、M&A後の混乱を最小限に抑え、スムーズな経営統合を支援します。
外注パートナーが、ITDD後のPMIフェーズにおける具体的な計画策定支援を提供できるか、その実績や体制を事前に確認することが賢明です。
M&Aを成功に導くITデューデリジェンスの外注パートナーを選定し、契約を締結する前には、最終的にいくつかの重要なポイントを確認しておく必要があります。これにより、期待通りの成果を得られ、M&A後のPMIも円滑に進めることができます。
4.2.1 報告書のクオリティと具体的な改善提案の有無ITデューデリジェンスの成果物である報告書は、M&Aの意思決定において極めて重要な情報源となります。単にIT資産のリストやリスクの羅列に終わるのではなく、そのクオリティと実用性が求められます。
具体的には、以下の点を確認することが重要です。
| 確認項目 | 詳細 |
|---|---|
| 網羅性と正確性 | 対象企業のITインフラ、アプリケーション、セキュリティ、ITガバナンスに関する情報が網羅的に、かつ正確に記述されているか。 |
| リスク評価の明確さ | 特定されたITリスクが、その深刻度、発生確率、ビジネスインパクトと共に明確に評価されているか。 |
| 具体的な改善提案 | 各リスクに対して、技術的側面だけでなく、経営的視点も踏まえた具体的な改善策や推奨されるアプローチが示されているか。 |
| PMIへの提言 | IT統合計画(Day1、Day100プラン)策定に向けた初期提言や、IT統合における優先順位付けに関するアドバイスが含まれているか。 |
| 分かりやすさ | 技術的な専門用語が多用されすぎず、経営層が意思決定に活用できるよう、簡潔かつ分かりやすくまとめられているか。 |
質の高い報告書は、M&A後のIT統合におけるロードマップ策定の強力な指針となり、不要なコストや時間を削減する上で不可欠です。契約前に報告書のサンプルを確認したり、報告会での説明体制について確認したりすることをお勧めします。
4.2.2 M&A後の継続的なITアドバイザリーサービスの提供可否ITデューデリジェンスはM&Aプロセスの初期段階ですが、その後のPMIフェーズにおいても、ITに関する専門的な知見や支援が継続的に必要となるケースが少なくありません。
デューデリジェンスを担当した外注パートナーが、M&A後のPMIフェーズにおいてITアドバイザリーや実行支援を提供できるかどうかは、長期的な視点でのパートナーシップを考える上で重要なポイントです。
継続的なアドバイザリーサービスには、IT統合計画の実行支援、システム移行プロジェクトの管理、セキュリティ強化策の導入支援、ITガバナンス体制の構築支援などが含まれます。
ITDDを通じて対象企業のIT環境を深く理解しているパートナーが、そのままPMIフェーズに移行して支援を提供することで、情報の引き継ぎロスがなく、一貫性のあるサポートが期待できます。
契約前に、M&A後の継続的な支援の範囲、提供体制、料金体系などについて具体的に確認し、必要に応じてそのオプションを契約に含めることを検討しましょう。これにより、M&A後のIT統合をより確実に、そして効率的に進めることが可能になります。
【関連】M&Aデューデリジェンス実践チェックリスト|買い手が見落とせない重要項目5. まとめ
M&AにおけるITデューデリジェンスは、見過ごされがちなITリスクを特定し、将来の統合コストやPMIの成否を左右する極めて重要なプロセスです。IT資産の複雑化と評価の専門性から、自社対応には限界があり、専門家への外注が不可欠です。
外注の際は、単なる「丸投げ」を避け、目的とスコープを明確にした上で、インフラ、アプリケーション、セキュリティ、ガバナンスを網羅し、M&A後のPMIまで見据えた専門性と実績を持つパートナーを選定することが肝要です。この賢い外注戦略こそが、M&Aを成功に導き、企業価値の最大化に繋がるでしょう。


