M&Aデューデリジェンスで失敗しないためのコンプライアンス調査全貌
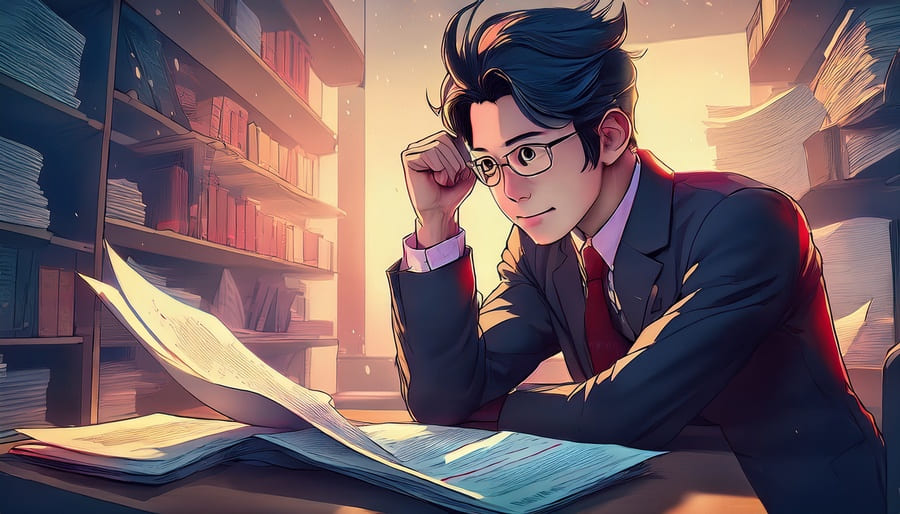
M&Aの成功は、買収対象企業の「隠れた爆弾」である偶発債務やレピュテーションリスクを事前に洗い出す、コンプライアンス・デューデリジェンスの精度で決まります。
本記事では、M&A実務担当者が押さえるべき調査の全体像から、贈収賄防止や個人情報保護、ESGといった最新領域まで網羅した調査項目、さらに調査結果をディール条件やPMIに活かす具体的な手法までを体系的に解説。M&Aを失敗させないための戦略的な進め方がわかります。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&A成功の礎となるデューデリジェンスとコンプライアンス調査の全体像
M&A(企業の合併・買収)は、事業成長を加速させるための強力な戦略的選択肢です。しかし、その成功は、買収対象企業のリスクをいかに正確に把握し、適切に管理できるかにかかっています。
そのための不可欠なプロセスが「デューデリジェンス(Due Diligence、DD)」であり、日本語では「買収監査」とも呼ばれます。デューデリジェンスは、財務、法務、ビジネス、人事など多岐にわたる領域を精査する活動ですが、その中でも特に企業の根幹を揺るがしかねないリスクを洗い出すのが「コンプライアンス・デューデリジェンス」です。
本章では、M&Aの成否を分けるコンプライアンス・デューデリジェンスの戦略的な重要性から、その調査範囲、そして他のデューデリジェンスとの連携に至るまで、M&A成功の礎となる全体像を詳細に解説します。
1.1 M&Aにおけるコンプライアンス・デューデリジェンスの戦略的重要性コンプライアンス・デューデリジェンスは、単に法令違反の有無を確認する形式的な手続きではありません。M&A取引の経済的条件や実行可否の判断、さらには買収後の統合プロセス(PMI)の成功までを見据えた、極めて戦略的な活動と位置づけられています。
その重要性は、主に「偶発債務とレピュテーションリスクの回避」と「PMIの円滑な推進」という2つの側面に集約されます。
M&Aの交渉段階で提示される企業価値(バリュエーション)は、財務諸表などの情報に基づいて算出されます。しかし、水面下で進行している法令違反や将来的に顕在化する可能性のあるコンプライアンス問題は、財務諸表には表れない「偶発債務」として、買収後に買い手企業に莫大な損失をもたらす時限爆弾となり得ます。
例えば、過去の贈収賄行為が発覚すれば巨額の課徴金が課される可能性があります。また、長年にわたるサービス残業代の未払いが発覚すれば、多額の未払賃金の支払義務が生じるかもしれません。これらの偶発債務は、M&Aの前提となっていた収益計画を根底から覆し、買収価格の妥当性を失わせるほどのインパクトを持ちます。
さらに深刻なのが「レピュテーションリスク」です。買収した子会社が反社会的勢力との関係や重大な品質不正を隠蔽していたことが発覚した場合、親会社である買い手企業のブランドイメージも著しく毀損されます。
結果として、顧客離れや取引停止、株価の下落を招き、企業価値を大きく損なうことになります。コンプライアンス・デューデリジェンスは、こうした致命的なリスクを事前に特定し、回避するための重要な防衛策なのです。
M&Aの真の成功は、契約締結(クロージング)後に始まるPMI(Post Merger Integration:経営統合プロセス)が円滑に進むかどうかにかかっています。コンプライアンス・デューデリジェンスは、このPMIを成功に導くための羅針盤としての役割も担います。
調査を通じて、対象企業のコンプライアンスに対する意識、社内規程の整備状況、内部統制システムの実効性といった「組織文化」や「ガバナンス体制」の実態を深く理解することができます。
これにより、買収後にどのような規程を導入する必要があるか、どのような従業員研修を実施すべきか、どの部署の内部管理体制を強化すべきかといった、具体的かつ実効性のある統合計画を早期に策定することが可能になります。
リスクの芽を事前に摘み取り、両社の企業文化の融合を円滑に進めることで、期待されるシナジー効果を最大化し、M&Aの成功確率を飛躍的に高めることができるのです。
コンプライアンス・デューデリジェンスは、他のデューデリジェンスと密接に連携しながら、効率的に進められます。ここでは、M&Aプロセスにおける位置づけと、具体的な調査の進め方について解説します。
1.2.1 法務・財務デューデリジェンスとの連携と役割分担デューデリジェンスは通常、法務、財務、ビジネス、人事、ITなど複数のチームが同時並行で進めます。コンプライアンス調査は主に法務デューデリジェンスの一部として、あるいは独立した専門チームによって実施されますが、各領域との連携が不可欠です。
それぞれの調査領域が有機的に連携することで、単独の調査では見抜けなかった複合的なリスクを発見できる可能性が高まります。
| デューデリジェンス領域 | 主な調査項目 | コンプライアンス調査との連携ポイント |
|---|---|---|
| コンプライアンスDD | 贈収賄、独占禁止法、個人情報保護、労働関連法規、各種業法などの遵守状況、反社会的勢力との関係、内部統制システムの有効性 | 各DDから得られた情報を集約し、コンプライアンス違反の兆候や潜在的リスクを総合的に評価するハブとしての役割を担う。 |
| 法務DD | 重要な契約内容、係争・訴訟案件、許認可の取得状況、知的財産権、登記・定款、議事録 | 契約書に不公正な条項がないか(下請法違反のリスク)、許認可の維持・更新に問題がないか(業法違反のリスク)などを連携して分析する。 |
| 財務DD | 財務諸表の正確性、収益性・財政状態の分析、簿外債務、税務リスク、キャッシュフロー | 使途不明金や不自然なコンサルティング費用が計上されていないかを確認し、贈収賄や粉飾決算の端緒としてコンプライアンスDDに情報提供する。 |
| 人事DD | 労働条件、人事制度、労務問題(未払残業代、ハラスメント等)、労働組合との関係 | 労働基準法などの労働関連法規の遵守状況を詳細に調査し、偶発債務(未払賃金)のリスクや労務トラブルの潜在的可能性を評価する。 |
このように、例えば財務DDで発見された不透明な支出が、コンプライアンスDDにおける贈収賄調査のきっかけとなったり、法務DDで確認された行政指導の履歴が、業法遵守体制の脆弱性を示す証拠となったりします。各専門家が緊密に情報交換を行うことが、調査の精度を高める上で極めて重要です。
1.2.2 VDR(ヴァーチャルデータルーム)を用いた効率的な資料請求現代のM&Aデューデリジェンスは、VDR(Virtual Data Room)と呼ばれるセキュアなオンラインプラットフォーム上で行われるのが一般的です。売り手企業は、買い手企業から要求された資料をVDRにアップロードし、買い手側の関係者(弁護士、公認会計士、コンサルタントなど)は、権限に応じてVDRにアクセスし、資料を閲覧・分析します。
このプロセスを円滑に進めるため、買い手側は事前に「DDリクエストリスト」と呼ばれる資料請求リストを作成し、売り手側に提示します。コンプライアンス調査に関するリクエストリストには、以下のような項目が含まれます。
- コンプライアンス関連規程(贈収賄防止規程、内部通報規程など)
- コンプライアンス委員会の議事録
- 役職員向けコンプライアンス研修の実施記録
- 内部監査・外部監査の報告書
- 過去の法令違反、行政指導、訴訟に関する記録
- 主要な取引先との契約書、反社会的勢力排除に関する覚書
- 許認可一覧および関連する申請・届出書類
VDRを活用することで、機密情報を安全に共有できるだけでなく、Q&A機能を通じて疑問点を効率的に解消し、調査の進捗を一元管理することが可能になります。これにより、限られた期間内で網羅的かつ深度のあるコンプライアンス・デューデリジェンスを実施することができるのです。
【関連】デューデリジェンスにおけるガバナンスチェックの全貌!M&Aの落とし穴回避術2. M&Aデューデリジェンスで網羅すべきコンプライアンス調査の主要領域
M&Aにおけるコンプライアンス・デューデリジェンスは、ターゲット企業が抱える潜在的リスクを洗い出すための極めて重要なプロセスです。その調査領域は、従来から指摘されてきた贈収賄や独占禁止法といった領域に加え、近年ではデータプライバシーやESGといった新たな領域へと拡大しています。
これらのリスクを見逃せば、M&A成立後に巨額の罰金や訴訟、深刻なレピュテーション毀損といった事態を招きかねません。ここでは、M&Aの成否を左右するコンプライアンス調査の主要領域を、「伝統的領域」と「新興領域」に分けて網羅的に解説します。
古くから企業の存続を揺るがすリスクとして認識され、M&Aデューデリジェンスにおいて必ず検証すべき伝統的なコンプライアンス領域です。これらの領域における違反は、当局からの課徴金や事業停止命令といった直接的かつ甚大な金銭的ダメージに繋がる可能性が高く、徹底した調査が求められます。
2.1.1 贈収賄防止(FCPA・英国贈収賄防止法)と反社会的勢力との関係企業の清廉性と社会からの信頼を根底から揺るがすのが、贈収賄や反社会的勢力との関係です。特にグローバルに事業展開する企業を買収する際は、海外の規制にも目を光らせる必要があります。
贈収賄防止に関しては、国内の刑法における贈収賄罪はもちろんのこと、海外の公務員に対する贈賄行為などを厳しく罰する米国の海外腐敗行為防止法(FCPA)や英国贈収賄防止法(UK Bribery Act)への準拠状況が重要な調査項目となります。
これらの法律は、日本企業であっても海外での活動内容によっては適用対象となる「域外適用」の性質を持つため、海外子会社や代理店の活動実態、接待交際費の規程と運用状況、内部監査の記録などを精査し、腐敗リスクを特定します。
また、反社会的勢力との関係遮断は、企業の社会的責任の根幹をなすものです。
デューデリジェンスでは、ターゲット企業が契約書に暴力団排除条項を適切に盛り込んでいるか、取引先の反社チェックを定期的かつ実効的な方法で行っているか、役職員が反社会的勢力と不適切な交友関係を持っていないかなどを、登記情報や過去の報道、専門機関のデータベースなどを活用して多角的に調査します。
公正な市場競争を阻害する行為は、企業の成長を妨げるだけでなく、巨額の課徴金や信頼失墜に繋がります。特に同業他社とのM&Aにおいては、企業結合後の市場シェアが独占禁止法上の問題とならないか、慎重な検討が不可欠です。
デューデリジェンスでは、過去に公正取引委員会から受けた排除措置命令や課徴金納付命令の有無を確認するとともに、価格カルテルや入札談合といった不当な取引制限に関与していないかを調査します。役職員の議事録やメール、同業他社との会合履歴などを分析し、違反の兆候がないかを探ります。
また、優越的地位の濫用にあたる行為も重要な調査対象です。特に、下請事業者との取引においては、下請代金支払遅延等防止法(下請法)の遵守状況を確認します。
発注書面の交付義務、支払期日の設定、不当な減額や返品の禁止といった規定が守られているか、社内規程や実際の取引記録を基に検証します。これらの違反は、当局からの勧告や指導に繋がり、企業イメージを大きく損なうリスクを内包しています。
| 調査領域 | 主な調査項目 | 潜在的リスク |
|---|---|---|
| 贈収賄防止 |
|
|
| 反社会的勢力との関係 |
|
|
| 独占禁止法・下請法 |
|
|
デジタルトランスフォーメーションの加速や、持続可能な社会への要請の高まりを受け、コンプライアンス調査の対象は新たな広がりを見せています。これらの領域は、違反した場合の制裁金だけでなく、企業価値やブランドイメージ、さらには事業継続性そのものに深刻な影響を与えるため、M&Aの意思決定においてその重要性は増すばかりです。
2.2.1 個人情報保護法・GDPR対応とサイバーセキュリティ体制データが「21世紀の石油」と称される現代において、個人情報の保護とサイバーセキュリティは事業の根幹を支える重要な経営課題です。M&Aによって大量の顧客データや機密情報を引き継ぐ場合、その管理体制に不備があれば、買収後に大規模な情報漏洩インシデントを引き起こす可能性があります。
デューデリジェンスでは、まず日本の改正個人情報保護法に準拠した体制が構築されているかを確認します。プライバシーポリシーの適切性、個人データの取得・利用・管理に関する社内規程、委託先の監督状況、そして漏洩発生時の報告体制などを精査します。
さらに、ターゲット企業がEU域内の個人データを取り扱っている場合は、GDPR(一般データ保護規則)への対応が不可欠です。違反した際の制裁金は極めて高額であり、そのリスク評価は必須となります。
同時に、技術的な側面からのサイバーセキュリティ体制の評価も欠かせません。情報セキュリティポリシーの整備状況、脆弱性診断の実施履歴、インシデント対応計画(CSIRTの有無など)、従業員へのセキュリティ教育の実態などを調査し、サイバー攻撃に対する防御力と回復力を評価します。
脆弱なシステムを抱えたままM&Aを進めると、統合後のシステム全体がリスクに晒されることになります。
投資家や消費者の企業を見る目は、もはや財務情報だけにとどまりません。環境(Environment)、社会(Social)、ガバナンス(Governance)への配慮、すなわちESGへの取り組みが企業価値を大きく左右する時代です。M&Aにおいても、ESG関連のリスクと機会を評価することは、長期的なリターンを確保する上で不可欠です。
デューデリジェンスでは、環境面では土壌汚染やアスベストといった過去の負の遺産の有無、環境関連法規制の遵守状況を調査します。社会面では、労働安全衛生管理体制、製品・サービスの安全性、そして近年特に注目される人権への配慮が調査対象となります。
特に、サプライチェーンにおける強制労働や児童労働といった人権侵害は、発覚すれば国際的な非難を浴び、不買運動などに発展する重大なリスクです。サプライヤーに対する人権デューデリジェンスの実施状況や、CSR調達方針の有無などを確認することが重要です。
これらの調査は、単なるリスクの洗い出しにとどまりません。ターゲット企業のESGへの先進的な取り組みは、M&A後の企業価値向上に繋がるポジティブな要素として評価することも可能です。コンプライアンス調査を通じて、負の側面と正の側面の両方からターゲット企業を評価する視点が求められます。
| 調査領域 | 主な調査項目 | 潜在的リスク |
|---|---|---|
| データ保護・サイバーセキュリティ |
|
|
| ESG・人権 |
|
|
3. M&Aの成否を分けるデューデリジェンスにおけるコンプライアンス調査の深掘り
M&Aのデューデリジェンスにおいて、表面的な資料の確認だけでは見抜けない「隠れたコンプライアンスリスク」が存在します。
これらは買収後に偶発債務として顕在化し、事業計画を根底から覆しかねない「隠れた爆弾」となり得ます。ここでは、ディールの成否を分ける、より一歩踏み込んだコンプライアンス調査の領域と手法について具体的に解説します。
コンプライアンスリスクは、全ての企業に共通する項目だけでなく、ターゲット企業が属する業界特有の規制や慣行に根差したものが数多く存在します。一般的な調査項目に加えて、事業の根幹をなす業界特有の法令遵守状況を精査することが、M&A成功の鍵を握ります。
3.1.1 許認可事業における業法遵守と行政指導履歴の分析建設業、医薬品製造・販売業、金融業、人材派遣業、廃棄物処理業など、事業運営に許認可が必要なビジネスモデルでは、その許認可の維持が事業継続の生命線です。
デューデリジェンスでは、許認可が有効に維持されているかはもちろん、その前提となる業法上の要件を充足し続けているかを徹底的に検証する必要があります。過去の行政指導や業務改善命令の履歴は、コンプライアンス体制の脆弱性を示す重要なシグナルであり、将来的な許認可取消リスクを評価する上で不可欠な情報源となります。
| 調査項目 | 具体的な確認内容 | 潜在的なリスク |
|---|---|---|
| 許認可の有効性と範囲 | 許認可証の原本確認、有効期限、更新状況、事業範囲との整合性 | 無許可営業、許認可失効による事業停止、PMI後の事業計画の破綻 |
| 業法上の要件遵守 | 人員配置(例:必置資格者)、設備基準、資産要件、業務プロセスの遵守状況 | 法令違反による罰則、是正措置に伴う追加コスト、許認可取消 |
| 行政処分・指導履歴 | 監督官庁からの業務改善命令、業務停止命令、課徴金納付命令、指導文書等の履歴 | 常習的な法令違反体質、レピュテーションの毀損、監督強化による事業運営の制約 |
| 変更届出の適時性 | 役員、所在地、株主構成など、届出義務のある事項に関する届出の履践状況 | 届出懈怠による過料、許認可更新時の障害、コンプライアンス意識の欠如 |
国境を越えて製品や技術を提供するグローバル企業にとって、輸出管理は極めて重要なコンプライアンス領域です。日本の「外国為替及び外国貿易法(外為法)」に基づくリスト規制やキャッチオール規制はもちろん、米国の輸出管理規則(EAR)に代表されるように、他国の法律が域外適用されるケースも少なくありません。
これらの規制に違反した場合、巨額の罰金や輸出禁止措置といった厳しい制裁が科され、企業の存続自体を脅かす事態に発展する可能性があります。そのため、ターゲット企業の輸出管理体制が実効性をもって機能しているかを厳しく評価する必要があります。
| 主要な規制 | 具体的な確認内容 | 違反した場合のリスク |
|---|---|---|
| 日本の外為法 | 貨物・技術の該非判定プロセスの妥当性、取引審査の記録、輸出許可の取得状況、社内規程・教育体制の整備状況 | 刑事罰(懲役・罰金)、行政制裁(輸出禁止命令)、社会的信用の失墜 |
| 米国再輸出規制(EAR) | 米国原産の製品・技術・ソフトウェアの含有率計算、取引先がエンティティ・リスト等の規制対象リストに含まれていないかのスクリーニング体制 | 巨額の民事・刑事罰、デニアル・オーダー(米国製品の輸出入権剥奪)、サプライチェーンの寸断 |
| 経済制裁関連法規 | 特定国・地域(例:ロシア、北朝鮮、イラン等)やテロリスト等の特定団体・個人との取引を排除するスクリーニング体制の実効性 | 資産凍結、取引禁止、金融機関からの取引停止、国際的なレピュテーションの毀損 |
VDR(ヴァーチャルデータルーム)で開示される整然とした資料だけでは、企業のコンプライアンスに関する実態を完全には把握できません。意図的に隠された不正や、組織に根付いてしまった不適切な慣行といった「隠れた爆弾」を発見するためには、より能動的で深掘りした調査手法が求められます。
3.2.1 フォレンジック調査とキーパーソンへのインタビュー不正会計、贈収賄、カルテルなどの疑いが少しでも持たれる場合には、デジタル・フォレンジック調査が極めて有効な手段となります。専門家がサーバーやPC内の電子メール、会計データ、チャット履歴などを保全・解析することで、削除されたデータからでも不正の証拠や痕跡を発見できる可能性があります。
全データを対象とすると膨大なコストと時間がかかるため、特定の部署や期間、キーワードに絞って調査を実施するのが一般的です。一方で、キーパーソンへのインタビューは、文書化されていない「生の情報」を引き出すために不可欠です。
法務・コンプライアンス担当者、内部監査責任者、現場の営業部長など、異なる立場の人々から話を聞くことで、社内規程と実態の乖離、過去に「もみ消された」インシデント、経営陣のコンプライアンス意識などを多角的に把握することができます。
内部通報制度は、自浄作用のバロメーターです。制度の有無を確認するだけでなく、その「実効性」を評価することが重要になります。通報窓口の独立性や秘匿性、通報後の調査プロセスの適切性、通報者が不利益な扱いを受けないための保護措置が機能しているかを確認します。
年間の通報件数やその内容、対応結果に関する記録を分析することで、組織が抱える潜在的な問題領域を特定できます。特に、通報件数が極端に少ない場合は、制度が形骸化しているか、報復を恐れて声を上げられない「モノ言えぬ文化」が醸成されている危険な兆候と捉えるべきです。
また、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントといった問題は、従業員の離職、生産性の低下、損害賠償請求訴訟、そしてSNS等によるレピュテーション毀損など、深刻な経営リスクに直結します。内部通報の内容や過去の労働審判、訴訟の有無、防止研修の実施状況などを調査し、特に経営層が関与する事案がないかを慎重に見極める必要があります。
4. M&Aデューデリジェンス後のコンプライアンス調査結果の活用とPMIへの展開
M&Aにおけるコンプライアンス・デューデリジェンスは、対象企業に潜むリスクを発見するだけで終わりではありません。むしろ、調査で得られた結果をM&Aの最終契約や買収価格に反映させ、さらに買収後の統合プロセス(PMI:Post Merger Integration)に活かしてこそ、その真価が発揮されます。
このフェーズでの対応を誤ると、デューデリジェンスで特定したリスクがそのまま買い手企業の負担となり、M&Aのシナジー効果を大きく損なうことになりかねません。ここでは、コンプライアンス調査の結果を最大限に活用し、M&Aを成功に導くための具体的な手法を解説します。
コンプライアンス・デューデリジェンスで発見されたリスクは、その深刻度や影響に応じて、M&Aの取引条件に具体的に落とし込む必要があります。
これにより、買い手は予期せぬ損失から自社を守り、より安全なディールを実現することが可能となります。主な反映方法には、「表明保証と補償条項によるリスクヘッジ」と「価格調整やクロージング前提条件の設定」があります。
株式譲渡契約書(SPA)などの最終契約書に適切な条項を盛り込むことは、コンプライアンスリスクに対する最も基本的な防御策です。特に重要なのが「表明保証」と「補償」の二つの条項です。
表明保証(Representations and Warranties)とは、売り手が対象会社の財務状況や法務、コンプライアンス遵守状況などについて、特定の事実が真実かつ正確であることを表明し、保証するものです。デューデリジェンスで特に懸念された事項については、一般的な表明保証に加えて、より具体的かつ詳細な「特別表明保証」を要求することが有効です。
一方、補償条項(Indemnification)は、表明保証違反が発覚した場合や、デューデリジェンスで特定された潜在リスク(特定補償事項)が顕在化し、買い手に損害が生じた場合に、売り手がその損害を金銭的に補填することを約束する条項です。これにより、万が一問題が発生した際のリスクを売り手に移転させることができます。
| 条項 | 役割 | コンプライアンス調査結果の反映例 |
|---|---|---|
| 表明保証(R&W) | 売り手に対象会社のコンプライアンス遵守状況を保証させることで、情報の非対称性を解消し、リスクの所在を明確にする。 | 過去の海外拠点での贈収賄リスクが懸念される場合、「過去5年間にわたり、FCPA(海外腐敗行為防止法)や英国贈収賄防止法を含む一切の贈収賄関連法令に違反した事実はない」という特別表明保証を要求する。 |
| 補償条項(Indemnification) | 表明保証違反や特定のリスクが顕在化した際の金銭的損害を売り手に負担させることで、買い手のリスクをヘッジする。 | 個人情報漏洩のインシデント履歴が確認された場合、将来、当該インシデントに起因する損害賠償請求や行政からの課徴金が発生した際には、売り手がその全額を補償する旨を定める。 |
デューデリジェンスの結果、発見されたコンプライアンス違反の是正に多額の費用が見込まれる場合や、リスクが極めて重大である場合には、より直接的な方法でディールに反映させる必要があります。
一つは、プライスチップ(Price Chip)と呼ばれる買収価格の減額交渉です。例えば、大規模なカルテルへの関与が発覚し、将来的に巨額の課徴金納付命令が下される可能性が高い場合、その予想される金額や弁護士費用などを合理的に算出し、買収価格から差し引くことを交渉します。
これは、リスクを価格に織り込むことで、買い手の負担を事前に軽減するアプローチです。
もう一つは、クロージング前提条件(Conditions Precedent)の設定です。これは、M&A取引を完了させる(クロージングする)ための前提として、売り手側が特定のコンプライアンス問題を解決することを義務付けるものです。
例えば、事業に必要な許認可の不備が発見された場合に、クロージング日までに正規の許認可を再取得することや、監督官庁からの行政指導に対する是正措置を完了させることなどを条件として設定します。この条件が満たされない限り、買い手は取引を完了する義務を負いません。
M&Aが無事にクロージングを迎えた後、最も重要なフェーズがPMI(ポスト・マージャー・インテグレーション)です。特にコンプライアンスに関しては、異なる企業文化やルールを持つ組織を円滑に統合し、グループ全体として実効性のあるガバナンス体制を早期に構築することが不可欠です。
デューデリジェンスで得られた情報は、このPMI計画を策定するための貴重なインプットとなります。
PMIはクロージング初日である「Day1」から始まります。Day1には、新体制におけるコンプライアンスの基本方針を役職員に明確に伝え、混乱を防ぐことが重要です。そのためには、クロージング前からデューデリジェンスの結果に基づいた詳細なコンプライアンス統合計画を準備しておく必要があります。
統合計画には、以下の要素を盛り込むことが求められます。
| 統合計画の項目 | 具体的なアクションプラン | デューデリジェンス結果の活用 |
|---|---|---|
| ガバナンス体制の構築 | ・新会社のCCO(チーフ・コンプライアンス・オフィサー)の任命 ・コンプライアンス委員会の設置・再編 ・買い手企業へのレポーティングラインの確立 |
対象会社のコンプライアンス担当部署の機能が不十分であった場合、買い手企業からの人材派遣や権限の明確化を計画に盛り込む。 |
| 規程・ルールの統合 | ・買い手企業の行動規範やコンプライアンス・ポリシーの展開 ・贈収賄防止、利益相反、内部通報などの主要規程の統合・改訂 ・各種申請・承認プロセスの統一 |
対象会社の規程に不備(例:贈答・接待に関する基準が曖昧)が発見された場合、優先的に買い手の基準に合わせた規程改訂を行う。 |
| リスクのモニタリング | ・内部通報制度(ヘルプライン)の統合と周知 ・コンプライアンスに関するリスク評価プロセスの導入 ・内部監査部門による定期的な監査計画の策定 |
デューデリジェンスで特定された高リスク領域(例:特定の海外子会社、特定の取引先との関係)を重点的なモニタリング対象として設定する。 |
この計画を成功させる鍵は、デューデリジェンスで明らかになった対象会社のコンプライアンス上の「弱点」を正確に把握し、それに対する具体的な処方箋をあらかじめ用意しておくことです。
4.2.2 新体制における役職員へのコンプライアンストレーニング新しいコンプライアンス体制を構築しても、それが現場の役職員に浸透しなければ意味がありません。M&A後は、速やかに新体制の方針に基づいたコンプライアンストレーニングを実施することが不可欠です。
これは、ルールを周知するだけでなく、買収された側の従業員の不安を払拭し、グループとしての一体感を醸成する上でも極めて重要なプロセスです。
トレーニングは、対象者の階層や職務に応じて内容を最適化する必要があります。
- 経営層向け:新体制におけるコンプライアンス経営の重要性、取締役としての善管注意義務、グループ全体のガバナンス体制について理解を深めるセッションを実施します。
- 管理職向け:部下の労務管理、ハラスメント防止、現場で発生しうるコンプライアンス問題への初期対応など、マネジメント層に求められる具体的な役割と責任についてトレーニングを行います。
- 一般社員向け:全社員が遵守すべき行動規範、新しい内部通報制度の利用方法、個人情報保護や情報セキュリティに関する基本ルールなど、実務に即した内容をeラーニングや集合研修で提供します。
- 高リスク部門向け:デューデリジェンスの結果、特にリスクが高いと判断された部門(例:海外営業部門、購買部門)に対しては、贈収賄防止や独占禁止法など、関連する法令に特化したより専門的な研修を追加で実施します。
M&A後のコンプライアンス体制の統合は、一朝一夕には実現しません。Day1から始まる計画的な取り組みと、役職員一人ひとりへの粘り強いコミュニケーションを通じて、初めて強固なコンプライアンス文化を醸成することができるのです。
【関連】初めてのM&Aデューデリジェンス|中小企業が最低限押さえるべき項目とは5. まとめ
M&Aの成功は、徹底したコンプライアンス・デューデリジェンスに懸かっています。本調査は、贈収賄や独占禁止法といった伝統的リスクに加え、個人情報保護やESGなど新たな領域に潜む偶発債務やレピュテーションリスクを事前に特定するために不可欠です。
調査結果を表明保証や価格交渉に的確に反映させ、買収後のPMIで円滑な体制統合を実現すること。これら一連のプロセスを緻密に行うことこそが、M&Aの価値を最大化し、失敗を回避する唯一の道筋と言えるでしょう。


