デューデリジェンスで企業価値評価を正確に見抜く重要ポイントと手法
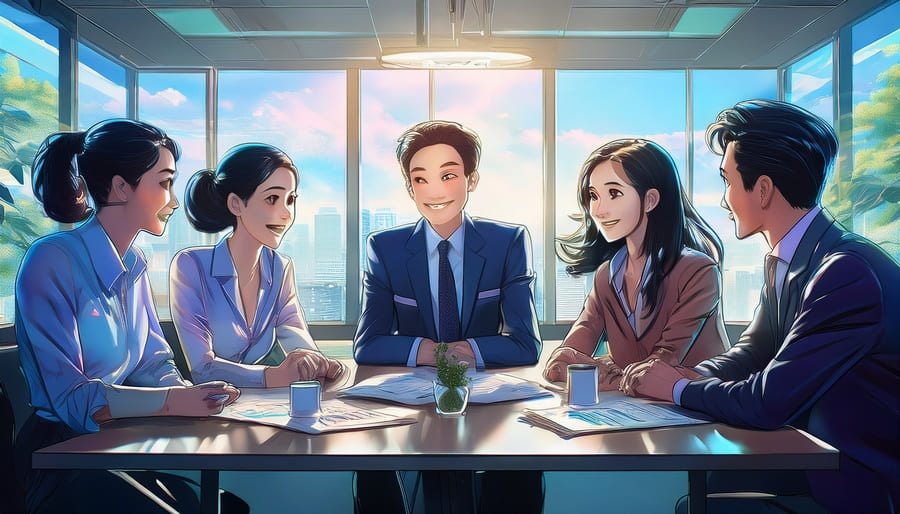
M&Aの成否は、デューデリジェンスで企業の実態を正確に把握し、企業価値評価に反映できるかで決まります。本記事では、財務諸表に表れない簿外債務や事業リスクを特定し、DCF法やEBITDAマルチプル法といった評価額へ具体的に落とし込む手法を解説。
初期評価額の罠を避け、スタンドアローン・バリューを適正に修正し、M&A交渉を有利に進めるための実践的ノウハウがわかります。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&A成功の土台:デューデリジェンスと企業価値評価の密接な関係
M&A(企業の合併・買収)のプロセスにおいて、「デューデリジェンス(Due Diligence)」と「企業価値評価(Valuation)」は、成功を左右する車の両輪です。これらは独立した手続きではなく、相互に深く関連し、影響を与え合う関係にあります。
初期段階で算定された企業価値はあくまで仮説に過ぎず、デューデリジェンスという精密検査を通じてその仮説を検証し、より現実に即した評価額へと精緻化していくプロセスこそが、M&Aの成否を分けるのです。
本章では、なぜデューデリジェンスが企業価値評価に不可欠なのか、その密接な関係性と、M&Aの意思決定に与える本質的な役割について掘り下げて解説します。
1.1 スタンドアローン・バリューの罠とデューデリジェンスの役割M&A交渉の初期段階で提示される企業価値は、多くの場合「スタンドアローン・バリュー」を基礎としています。これは、買収対象企業が他社からの支援やシナジー効果なしに、単独で事業を継続した場合に創出されると予測される価値を指します。
しかし、この初期評価額には、買い手が見落としてはならない「罠」が潜んでいる可能性があります。デューデリジェンスは、その罠の正体を暴き、評価の前提を根本から見直すための重要な役割を担います。
売り手から提示される情報や公開情報だけでは把握できない「未認識リスク」は、M&Aにおける最大の脅威の一つです。これらのリスクは、スタンドアローン・バリューの算定根拠となる将来のキャッシュフローや純資産を大きく毀損させる可能性があります。
例えば、以下のようなリスクがデューデリジェンスによって発見されることがあります。
- 簿外債務・偶発債務:決算書に記載されていない債務保証、訴訟による損害賠償リスク、未払いの残業代など。
- 資産の過大評価:回収不能な売掛金(不良債権)、販売見込みのない滞留在庫、実態価値の低い不動産など。
- 法務・コンプライアンス違反:許認可の不備、重要な契約における違反、知的財産権の侵害リスクなど。
- 人事労務問題:キーパーソンの退職意向、潜在的な労働紛争のリスクなど。
デューデリジェンスは、こうした財務諸表の数字の裏に隠されたリスクを体系的に洗い出し、企業価値評価から控除すべき項目を特定するための不可欠なプロセスです。
1.1.2 デューデリジェンスによる事業計画の蓋然性検証企業価値評価、特にDCF法(ディスカウンテッド・キャッシュフロー法)を用いる場合、その計算の基礎となるのは対象企業が策定した「事業計画」です。しかし、売り手側が提示する事業計画は、M&Aを有利に進めるために楽観的な売上成長や希望的観測に基づいた利益率が設定されているケースが少なくありません。
ビジネスデューデリジェンスは、この事業計画が絵に描いた餅ではないか、その実現可能性(蓋然性)を客観的な視点から徹底的に検証します。
- 市場環境の分析:市場の成長性、競争環境、規制の変更などが事業計画に正しく反映されているか。
- 競争優位性の評価:対象企業の製品・サービスの強みや弱み、競合他社との差別化要因は持続可能か。
- 顧客・サプライヤー分析:特定顧客への依存度、主要サプライヤーとの関係安定性などを評価し、売上やコストの変動リスクを洗い出す。
これらの検証を通じて、楽観的すぎる売上予測を下方修正したり、想定されていなかったコスト増を織り込んだりすることで、より現実的な将来キャッシュフロー予測を作成し、企業価値評価の精度を飛躍的に高めることができます。
1.2 企業価値評価を深化させる多角的デューデリジェンスの必要性企業価値を正確に把握するためには、財務情報だけでなく、事業、法務、人事、ITといった多角的な視点からのデューデリジェンスが不可欠です。それぞれの分野における調査結果が、財務的な企業価値評価に直接的・間接的に影響を与え、評価額を大きく変動させる要因となり得ます。
1.2.1 財務諸表だけでは見えない無形資産(のれん)の毀損リスクM&Aの買収価格が対象企業の純資産を上回る場合、その差額は「のれん(営業権)」として買い手の資産に計上されます。この「のれん」の源泉は、ブランド価値、顧客基盤、優れた技術力、優秀な人材といった、財務諸表には直接現れない無形資産です。
しかし、これらの無形資産の価値は非常に脆弱な場合があります。例えば、
- 法務デューデリジェンスで、事業の根幹をなす特許の有効性に疑義が発見される。
- 人事デューデリジェンスで、技術開発の中核を担うエンジニアチームに集団退職のリスクが判明する。
- ビジネスデューデリジェンスで、主要顧客との契約にチェンジオブコントロール(COC)条項があり、買収によって契約が解除される可能性が発覚する。
これらの事象は、買い手が期待していた「のれん」の価値、すなわち超過収益力を根本から覆し、将来的な減損損失につながる重大なリスクとなります。多角的なデューデリジェンスは、こうした無形資産の毀損リスクを事前に特定し、企業価値評価に織り込むために極めて重要です。
1.2.2 シナジー効果の実現可能性と定量的な企業価値評価への反映買い手がスタンドアローン・バリューを上回る買収価格(プレミアム)を支払う最大の理由は、M&Aによって生まれる「シナジー効果」への期待です。しかし、期待されたシナジーが実現しないケースは後を絶ちません。
デューデリジェンスは、買い手が描くシナジーの実現可能性を冷静に評価し、その価値を定量的に企業価値評価へ反映させるための根拠を提供します。シナジーは大きく分けて「売上シナジー」と「コストシナジー」に分類され、それぞれ異なる視点での検証が必要です。
| シナジーの種類 | 具体例 | デューデリジェンスにおける主な検証ポイント |
|---|---|---|
| 売上シナジー | クロスセル・アップセル、販売チャネルの相互活用、新規市場への進出 | 両社の顧客層の重複度、ブランドイメージの整合性、販売体制の統合可能性、市場でのカニバリゼーション(共食い)リスクの分析 |
| コストシナジー | 仕入れ・購買の共通化、管理部門の統合、製造・物流拠点の統廃合 | システム統合の難易度と追加投資コスト、拠点統廃合に伴う従業員の整理費用や移転費用、取引先との契約条件の再交渉可能性 |
デューデリジェンスを通じて、期待されるシナジーの規模、発生時期、実現までのコストや障壁を具体的に明らかにします。この結果に基づき、「期待値」ではなく「実現可能性の高いシナジー価値」のみを企業価値評価に加算することで、過大なプレミアムを支払うリスクを回避することができるのです。
【関連】デューデリジェンスの外部委託でリスクを回避しM&Aを成功させる方法2. 財務デューデリジェンスがM&Aの企業価値評価をどう変えるか
M&Aにおける企業価値評価は、対象企業から提示された財務諸表を基に初期的な算定(スタンドアローン・バリュー)が行われます。しかし、その数値はあくまで会計基準に則った過去の実績であり、M&A後の将来の価値を保証するものではありません。
財務デューデリジェンス(財務DD)は、この初期評価額の妥当性を検証し、財務諸表の裏側に隠されたリスクや実態を明らかにすることで、企業価値評価をより現実に即したものへと修正・深化させる極めて重要なプロセスです。
財務DDの目的は、単なる粉飾決算の発見に留まりません。対象企業の「正常な収益力」と「実質的な純資産」を正確に把握し、M&Aの価格交渉や最終契約の土台となる客観的な根拠を提供することにあります。
具体的には、損益計算書(P/L)と貸借対照表(B/S)を精査し、将来のキャッシュフロー予測の精度を高め、潜在的な財務リスクを洗い出していきます。
企業価値評価手法の中でも特にDCF法やEBITDAマルチプル法では、将来にわたって継続的に生み出されると期待される収益力、すなわち「正常収益力」が評価の起点となります。
財務DDでは、過去の損益計算書から一時的な要因や非継続的な取引を排除し、この正常収益力を精密に分析します。また、事業活動に不可欠な運転資本の実態を把握することは、将来のキャッシュフロー予測の正確性を左右する重要な要素です。
正常収益力とは、対象企業が本来持つ事業から、将来にわたって安定的に創出できると見込まれる利益水準を指します。
財務DDでは、過去数期分の損益計算書を分析し、以下のような非経常的・一時的な損益項目を特定し、これらを排除する「正常化分析」を行います。このプロセスを経て算出される「正常EBITDA」は、企業価値評価の基礎となる極めて重要な指標です。
| 調整項目の種類 | 具体例 | 企業価値評価への影響 |
|---|---|---|
| 非経常的な費用(加算調整) | 役員退職慰労金、構造改革費用、訴訟関連費用、災害損失、過年度の修正損 | これらの費用を利益に加算することで、過小評価されていた収益力が正常化され、企業価値評価額が上昇する可能性があります。 |
| 非経常的な収益(減算調整) | 固定資産売却益、補助金収入、保険金収入、受贈益 | これらの収益は将来の継続性がないため利益から減算します。調整を怠ると、収益力を過大評価し、高値掴みのリスクを負うことになります。 |
| 会計方針の変更・裁量的な費用 | 減価償却方法の変更、過剰または過少な引当金、オーナー経営者への過大な役員報酬や関連会社との非合理的な取引 | M&A後に適用される会計方針や合理的な費用水準に修正します。特にオーナー関連の費用は、実質的な利益水準を把握するために重要な調整項目です。 |
これらの正常化調整を行うことで、対象企業の真の実力を見極め、より精度の高い事業計画の策定と企業価値評価を実現することが可能になります。
2.1.2 過少・過大運転資本がキャッシュフローに与える影響分析運転資本(売上債権+棚卸資産-仕入債務)は、事業の成長に伴い増加し、キャッシュフローを圧迫する要因となります。財務DDでは、過去の運転資本の推移を分析し、事業規模に見合った「正常運転資本」の水準を算定します。
M&Aの取引実行日(クロージング日)における実際の運転資本がこの正常水準から乖離している場合、その差額は株式譲渡価格の調整項目(価格調整)となるのが一般的です。
- 過少運転資本:クロージング日に運転資本が正常水準より少ない状態です。例えば、意図的に仕入を抑制したり、支払を早めたりすることで発生します。
この場合、買収後に買い手は不足分の運転資金を追加で投下する必要があるため、実質的な買収価格の上昇を意味します。そのため、不足額は譲渡価格から減額されることになります。 - 過大運転資本:クロージング日に運転資本が正常水準より多い状態です。これは売上債権の回収遅延や過剰在庫などが原因で発生します。この超過分は本来売り手が回収すべきキャッシュが事業内に滞留している状態と見なされ、譲渡価格に加算されることがあります。
運転資本の実態を正確に把握することは、買収後の追加資金需要を予測し、予期せぬ資金繰りの悪化を防ぐ上で不可欠です。また、将来の運転資本の増減はフリーキャッシュフローの予測に直接影響するため、DCF法による企業価値評価の精度を大きく左右します。
2.2 貸借対照表に潜むリスクと企業価値評価へのインパクト貸借対照表(B/S)は企業の財政状態を示す重要な財務諸表ですが、その計上額が必ずしも実態価値を反映しているとは限りません。
特に、会計帳簿には現れない「簿外債務」や、資産価値が著しく低下している「不良資産」の存在は、企業価値を大きく毀損させるリスク要因です。財務DDでは、これらの隠れたリスクを洗い出し、「実質純資産」を算定します。
企業価値評価において、事業価値から株式価値を算出する際には、有利子負債等を控除します。このとき、B/Sに計上されている借入金だけでなく、実質的に負債と同等の性質を持つ簿外債務や、将来負債化する可能性のある偶発債務も「純有利子負債」に含めて計算する必要があります。
財務DDで発見される主な簿外・偶発債務は以下の通りです。
| 債務の種類 | 具体例 | 株式価値への直接的な影響 |
|---|---|---|
| 簿外債務 | 未払残業代、退職給付引当金の不足額、リース債務(特にオフバランス取引)、デリバティブ取引の含み損 | 発見された債務は純有利子負債に加算され、その分だけ株式価値が直接的に減少します。 |
| 偶発債務 | 係争中の訴訟における潜在的な損害賠償義務、第三者への債務保証、製品保証引当金の不足、土壌汚染などの環境修復義務 | 発生可能性と影響額を合理的に見積もり、リスクの度合いに応じて企業価値評価の価格調整項目や割引率への反映を検討します。 |
これらの債務を見過ごした場合、M&A後に予期せぬ債務負担が発生し、投資リターンが大幅に悪化する可能性があります。純有利子負債を実態に即して再計算することは、適正な株式価値を算定するための必須の作業です。
2.2.2 不良債権・滞留在庫の実態評価と実質純資産の修正B/Sの資産サイドにも、企業価値を毀損させるリスクは潜んでいます。財務DDでは、資産が簿価通りの価値を有しているかを個別に検証し、実態価値(時価)に基づいた実質純資産を算定します。
- 売上債権の評価:得意先ごとの残高と滞留状況を分析する年齢調べ(エイジングリスト)を実施し、回収可能性の低い不良債権を特定します。貸倒引当金が実態に比べて不足している場合は、追加の引当金を計上し、その分だけ純資産を減額修正します。
- 棚卸資産の評価:長期間販売されていない滞留在庫や、陳腐化・品質劣化した不良在庫の実態を把握します。実地棚卸への立ち会いや、在庫の回転期間分析を通じて、簿価と時価の乖離を評価します。評価損の計上が必要と判断されれば、これも純資産の減少要因となります。
- 固定資産の評価:遊休資産や、事業に使用されていない非事業用資産、減損処理が必要な資産がないかを確認します。これらの資産は、事業価値の評価からは除外し、別途時価で評価して加算(または処分費用を減算)するなどの調整を行います。
これらの資産評価を通じてB/Sを時価に洗い替えることで、実質的な純資産額が明らかになります。この結果は、コストアプローチ(純資産法)による企業価値評価の基礎となるだけでなく、将来の損失発生リスクを織り込むことで、収益性アプローチ(DCF法など)における評価の信頼性も高めることにつながります。
【関連】M&A デューデリジェンスの最適な相談先と選び方3. M&Aの成否を分ける:非財務デューデリジェンスによる企業価値評価の深化
M&Aにおける企業価値評価は、財務諸表の数字を分析する財務デューデリジェンスだけでは完結しません。むしろ、その数字の裏付けとなる事業の持続可能性や、潜在的なリスクを洗い出す「非財務デューデリジェンス」こそが、評価の精度を決定づけ、M&Aの最終的な成否を分ける鍵となります。
事業の実態、法務・人事面に潜むリスクを深く掘り下げることで、将来キャッシュフロー予測の確からしさを検証し、より現実に即した企業価値を導き出すことが可能になるのです。
ビジネスデューデリジェンス(事業デューデリジェンス)は、対象会社の事業モデル、市場における競争優位性、顧客基盤、サプライチェーン、技術力といった事業そのものの実態を多角的に分析・評価するプロセスです。
対象会社が提示する事業計画が、希望的観測ではなく、客観的な事実と合理的な根拠に基づいているかを徹底的に検証します。この検証結果は、DCF法などで用いる将来キャッシュフロー予測の数値を直接的に修正する根拠となり、企業価値評価の根幹を支えます。
事業の安定性を評価する上で、取引先との関係性は極めて重要な調査項目です。特に、売上や仕入が特定の企業に集中している場合、その依存関係は大きな経営リスクとなり得ます。例えば、売上上位3社で全体の70%を占めるような事業構造では、そのうち1社との取引が停止するだけで、事業計画は根本から崩壊しかねません。
ビジネスデューデリジェンスでは、取引先ごとの売上構成比や契約内容、関係性の安定性を調査し、依存リスクが顕在化した場合の財務インパクトをシミュレーションします。この結果、将来売上の減少リスクとしてキャッシュフロー予測に織り込む、あるいは割引率にリスクプレミアムを上乗せするといった形で企業価値評価に反映させます。
同様に、サプライチェーンの脆弱性も評価に大きな影響を与えます。特定の供給元への依存、地政学リスクによる調達難、原材料価格の急激な変動可能性などを評価し、生産停止やコスト増が収益性に与える影響を分析します。
これらのリスクは、将来の原価率の上昇として事業計画を修正したり、偶発的な損失として評価額から控除したりする必要があるでしょう。
対象会社の収益力の源泉となっているKSF(Key Success Factor:重要成功要因)を特定し、その持続可能性を評価することは、ビジネスデューデリジェンスの中核をなします。KSFは、独自の技術力、強力なブランド、模倣困難なビジネスモデル、特定の販売チャネルなど、企業によって様々です。
重要なのは、そのKSFがM&A後も維持できるか、陳腐化するリスクはないかを冷静に見極めることです。
例えば、事業計画が「独自のAI技術による市場シェア拡大」を前提としている場合、その技術の特許ポートフォリオ、競合他社の開発状況、代替技術の登場可能性などを精査します。
もしKSFの競争優位性が脆弱であると判断されれば、事業計画に描かれた楽観的な成長率は下方修正されるべきです。このように、KSFの客観的な分析を通じて将来キャッシュフロー予測の蓋然性を検証し、企業価値評価の精度を飛躍的に高めることができます。
法務・人事デューデリジェンスは、コンプライアンス違反、訴訟リスク、重要な契約に潜む問題点、人事労務関連の簿外債務など、法的な観点や組織・人材の観点からリスクを洗い出すプロセスです。
これらの領域で発見される問題は、時にM&A取引そのものを頓挫させる「ディールブレーカー」となる可能性を秘めており、企業価値を直接的に毀損する簿外債務として認識されるケースも少なくありません。
法務デューデリジェンスにおいて特に注意すべきなのが、チェンジオブコントロール(Change of Control:COC)条項です。これは、M&Aによって会社の支配権(株主)が変更された場合に、契約相手方が事前の通知や承諾なく契約を解除できる権利を定めた条項です。
事業継続に不可欠な契約にCOC条項が含まれていると、M&Aの実行と同時にその契約が失効し、事業の前提が覆るという深刻な事態を招きかねません。
例えば、主力製品の製造に不可欠な技術ライセンス契約や、主要な販売チャネルである代理店契約が失効すれば、企業価値は著しく毀損します。COC条項のリスクを洗い出し、契約相手方から事前に承諾を取り付ける(コンセントの取得)必要性や、最悪の場合の代替策を検討することが不可欠です。
このリスクは、該当契約からの将来キャッシュフローをゼロとして再計算したり、契約の再交渉にかかるコストを評価額から控除したりする形で企業価値評価に反映されます。
| 契約の種類 | 潜在的リスク | 企業価値評価への反映方法 |
|---|---|---|
| 技術ライセンス契約 | 主力製品の製造・販売が不可能になる | 将来キャッシュフローの大幅な減少、または事業価値の消滅 |
| 販売代理店契約 | 主要な販売チャネルを失い、売上が激減する | 将来売上の下方修正、代替チャネル構築コストの控除 |
| 不動産賃貸借契約 | 本社や工場の移転を余儀なくされ、事業が中断する | 移転コストや事業中断による逸失利益を評価額から控除 |
| 金融機関との借入契約 | 期限の利益を喪失し、一括返済を求められる | 資金繰りの悪化、再ファイナンスコストの発生 |
人事デューデリジェンスでは、「ヒト」に関するリスクを評価します。特に重要なのが、企業の価値創造の中核を担うキーパーソン(経営幹部、トップエンジニア、エース営業担当者など)の流出リスクです。M&Aによる環境変化を嫌気してキーパーソンが退職してしまえば、事業計画の達成は困難になります。
そのため、キーパーソンを特定し、彼らをM&A後も引き留めるためのリテンションプラン(役員報酬の見直し、インセンティブプランの導入など)の必要性と、それに伴う追加コストを算定し、企業価値評価に織り込む必要があります。
また、財務諸表に計上されている退職給付引当金が、実態を正確に反映しているかの検証も不可欠です。特に中小企業では、退職金規程が未整備であったり、過去の勤務期間に対する債務が適切に計算されていなかったりするケースが見受けられます。
人事デューデリジェンスを通じて従業員の年齢構成や勤続年数、退職金規程を精査し、本来計上すべき退職給付債務を再計算します。この結果、判明した未認識の債務は実質的な簿外債務として、企業価値の算定上、純有利子負債(ネットデット)に加算して評価額から控除することになります。
4. M&A交渉を有利に進めるデューデリジェンス結果を反映した最終企業価値評価
デューデリジェンスは、対象企業の潜在的リスクを洗い出すだけの調査ではありません。その調査結果を最終的な企業価値評価額、ひいては買収価格に適切に反映させ、M&A交渉を有利に進めるための強力な武器となります。
初期段階で提示される暫定的な企業価値(インディケーション・バリュー)は、あくまで限られた情報に基づく仮説に過ぎません。デューデリジェンスを通じて、その仮説の前提となった事業計画の妥当性を検証し、財務諸表には表れないリスクを定量化することで、客観的根拠に基づいた最終的な企業価値評価を導き出すことが可能になるのです。
デューデリジェンスでの発見事項は、具体的な企業価値評価(バリュエーション)の計算プロセスに落とし込む必要があります。ここでは、代表的な評価手法である「DCF法」と「EBITDAマルチプル法」において、どのようにリスクを反映させるかを解説します。
4.1.1 DCF法における割引率(WACC)へのリスクプレミアムの上乗せDCF(ディスカウンテッド・キャッシュフロー)法は、対象企業が将来生み出すフリーキャッシュフローを、事業のリスクを反映した割引率(WACC:加重平均資本コスト)で現在価値に割り引くことで企業価値を算出する手法です。デューデリジェンスで発見されたリスクは、将来のキャッシュフローの不確実性を高める要因となります。
この不確実性を評価額に反映させるため、算出されたWACCに「個別企業リスクプレミアム」を上乗せするアプローチが一般的です。例えば、以下のようなリスクが発見された場合、リスクプレミアムの上乗せが検討されます。
- 特定の大口取引先への過度な売上依存
- キーパーソン(創業者や特定の技術者など)の退職による事業継続リスク
- 解決の目処が立たない重要な訴訟の存在
- 業界の規制強化による将来的な収益圧迫の可能性
リスクプレミアムの具体的な数値(例:1%~5%など)は、客観的なデータのみで算出することは困難であり、専門家の知見や過去の類似案件を参考に、買い手側が合理的な根拠を持って設定し、交渉に臨むことになります。このプレミアムの上乗せは、割引率を高め、結果として企業価値評価額を引き下げる効果を持ちます。
4.1.2 EBITDAマルチプル法における価格調整項目としてのリスクの定量化EBITDAマルチプル法は、類似上場企業の株価や類似のM&A取引事例から、企業価値がEBITDA(利払前・税引前・減価償却前利益)の何倍で評価されているか(マルチプル)を算出し、対象企業のEBITDAに乗じることで企業価値を評価する手法です。
この手法では、デューデリジェンスで発見された金銭的な影響額を直接算定し、企業価値から控除する「価格調整」を行うのが一般的です。
具体的には、算出した企業価値(エンタープライズ・バリュー)から純有利子負債を差し引いて株式価値を計算する際に、発見されたリスク項目を純有利子負債と同様の「デット・ライク・アイテム(負債類似項目)」として加算します。これにより、最終的な株式価値が引き下げられます。
| 発見事項(リスク) | 内容と企業価値への影響 |
|---|---|
| 簿外債務・偶発債務 | 退職給付引当金の不足額、未払残業代、訴訟損失引当金など、貸借対照表に計上されていない将来のキャッシュアウト要因。算定された金額を価格から直接控除します。 |
| 滞留在庫・不良債権 | 評価額が過大に計上されている在庫や回収不能な売掛金。実態に合わせた評価減を行い、その減少額を純資産から控除する形で価値を調整します。 |
| 設備投資(CAPEX)の不足 | 事業計画達成に必要な設備投資が計画に盛り込まれていない、または過少に見積もられている場合、その不足額を将来のキャッシュアウトとして価値から控除します。 |
| 環境債務・修繕義務 | 工場の土壌汚染対策費用や、賃借物件の原状回復義務など、将来発生が見込まれる費用。見積額を負債として認識し、価値を減額します。 |
この方法は、DCF法におけるリスクプレミアムの上乗せに比べて、リスクの影響を金額で直接的に示すため、売り手との価格交渉において、より客観的で説得力のある根拠として提示しやすいというメリットがあります。
4.2 デューデリジェンスの発見事項を最終契約に盛り込む交渉術デューデリジェンスで発見されたリスクの中には、現時点での金銭的な影響額を正確に算定することが困難なものも存在します。
このような定量化しきれないリスクについては、最終契約書である株式譲渡契約書(SPA: Stock Purchase Agreement)の条項を工夫することで、買い手のリスクをヘッジすることが可能です。
表明保証条項とは、売り手が対象会社の財務、税務、法務、事業などに関する特定の事柄が、真実かつ正確であることを買い手に対して表明し、保証するものです。デューデリジェンスで懸念事項が発見された場合、その事項に関連する表明保証をSPAに具体的に盛り込むことで、リスクを売り手に負担させることができます。
例えば、「認識している範囲において、重要な訴訟は提起されていない」という一般的な表明保証に加えて、デューデリジェンスで特定された潜在的な訴訟リスクについて、「〇〇に関する紛争は存在せず、将来においても損害賠償請求が発生する可能性はない」といった、より個別具体的な表明保証を要求します。
万が一、契約後にこの表明保証に違反する事実が発覚した場合、買い手は売り手に対して補償条項(Indemnification)に基づき損害賠償を請求することができ、金銭的な損失をカバーすることが可能になります。
アーンアウト条項は、M&Aの対価の支払い方法に関する取り決めの一つです。クロージング時点では買収対価の一部のみを支払い、残りの対価は、M&A後の一定期間内に、対象会社が事前に合意した業績目標(例:売上高、EBITDAなど)を達成した場合に限り、追加で支払うという仕組みです。
この条項は、デューデリジェンスの結果、売り手が提示する事業計画の実現可能性に疑問符がつく場合や、将来の業績の不確実性が高いと判断された場合に特に有効です。買い手にとっては、実際に業績が伴わなければ追加の支払いをせずに済むため、高値掴みのリスクを大幅に低減できます。
一方で、売り手にとっても、自社の将来性に対する自信を価格に反映させる機会となり、双方にとって合理的な着地点を見出すための有効な交渉ツールとなり得ます。アーンアウトを設計する際は、達成目標とする財務指標、測定期間、算定方法などを明確に定義し、将来の紛争を避けるための詳細な規定を契約書に盛り込むことが極めて重要です。
5. まとめ
M&A成功の鍵は、デューデリジェンスによる企業価値評価の深化にあります。財務諸表だけでは見えない正常収益力や簿外債務、事業の将来リスクを多角的に検証することで、当初の評価額の妥当性が明らかになります。
この詳細な分析結果は、DCF法における割引率の調整や最終契約の表明保証条項に反映され、リスクを織り込んだ適正な企業価値での買収と、M&A後の成功確度を高めるために不可欠です。


