事業再生計画書の作り方|金融機関説得のためのポイントと事例解説
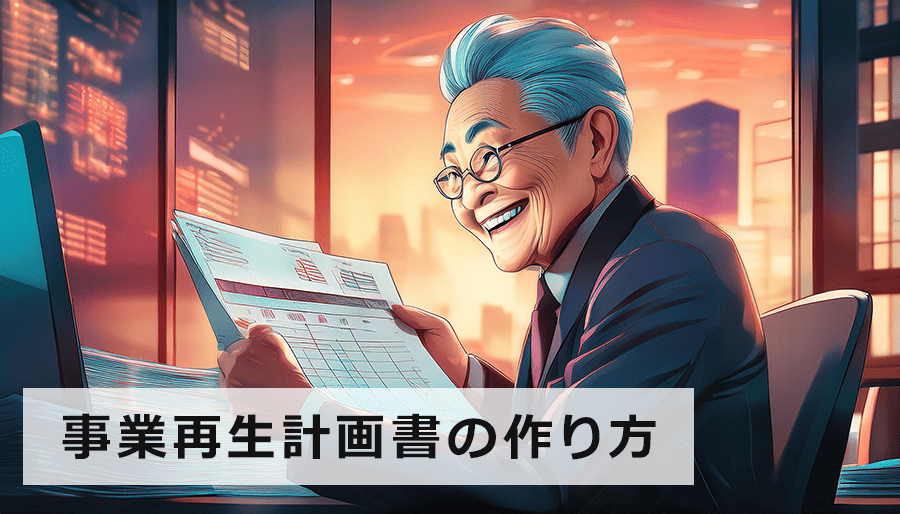
資金繰りが悪化し、事業の継続が困難になった時、事業再生計画書はあなたの会社を救う強力なツールとなります。しかし、ただ作成すれば良いというものではありません。金融機関を説得し、支援を取り付けるための戦略的な計画書でなければ意味がないのです。
この記事では、事業再生計画書の作り方を、金融機関の視点も踏まえながら具体的に解説します。財務状況の分析や事業上の課題の明確化といった現状分析から、具体的な再生計画の策定、そして金融機関を説得するためのポイントまで、実例を交えながら分かりやすく説明します。
この記事を読むことで、金融機関が納得する事業再生計画書の書き方が理解でき、融資獲得の可能性を高めることができます。事業再生の成功に向けて、ぜひ本記事を参考にしてください。再生計画の実例として、製造業、飲食業、小売業の事例も紹介しているので、業種に合わせた計画策定のヒントを得られます。
「赤字解消(経営再建)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・事業再生などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 事業再生計画書とは何か?
事業再生計画書とは、経営難に陥った企業が、その事業を再生させるために作成する計画書です。金融機関からの融資継続や新規融資を受ける際に必要となるだけでなく、取引先や従業員、株主など、あらゆるステークホルダーに対して、企業の再建への道筋を示す重要な役割を担います。いわば、企業の「未来予想図」であり、再生への強い意志を示すものです。
【関連】事業再生とは?基本戦略と成功へのステップ1.1 事業再生計画書の目的
事業再生計画書の主な目的は、以下の3点に集約されます。
| 金融機関からの資金調達 | 金融機関は、融資の可否を判断する上で、事業再生計画書の提出を求めます。計画の具体性、実現可能性、そして返済能力などを評価し、融資実行の判断材料とします。そのため、金融機関を説得できるだけの説得力のある計画書を作成することが重要です。 |
|---|---|
| ステークホルダーの理解と協力の獲得 | 事業再生には、金融機関だけでなく、取引先、従業員、株主など、様々なステークホルダーの理解と協力が不可欠です。事業再生計画書は、これらのステークホルダーに対して、現状の課題と今後の展望を明確に示し、協力を得るためのツールとなります。 |
| 社内における意識改革 | 事業再生計画書の作成を通じて、社内の現状認識を共有し、再生に向けた共通の目標を設定することができます。これにより、従業員のモチベーション向上や意識改革を促し、再生への取り組みを一体的に進めることができます。 |
1.2 事業再生計画書の必要性
事業再生計画書は、単なる資料作成ではなく、企業再生のプロセスそのものと言えるでしょう。計画書を作成する過程で、経営陣は自社の現状を客観的に分析し、将来のビジョンを明確にすることができます。また、金融機関との交渉やステークホルダーとのコミュニケーションを通じて、様々なフィードバックを得ることで、計画の精度を高めることができます。
特に、金融機関との関係においては、事業再生計画書の有無が、融資の可否を大きく左右します。計画性のないまま資金援助を求めても、金融機関は応じてくれないでしょう。事業再生計画書は、金融機関に対して、企業の再生への真剣な取り組み姿勢を示す証拠となるのです。また、計画書に基づいた経営を行うことで、金融機関からの信頼獲得にも繋がります。
| 事業再生計画書の必要性 | 詳細 |
|---|---|
| 金融機関からの融資獲得 | 金融機関は、融資判断の重要な材料として事業再生計画書を重視します。 |
| ステークホルダーの理解と協力 | 取引先、従業員、株主など、様々なステークホルダーに現状と展望を共有し、協力を得るために必要です。 |
| 社内意識の改革 | 計画作成を通じて現状認識を共有し、再生への意識統一を図ることができます。 |
| 経営のPDCAサイクル確立 | 計画、実行、評価、改善のサイクルを確立し、継続的な改善を促します。 |
| 企業価値の向上 | 再生計画の実行を通じて、中長期的な企業価値の向上を目指します。 |
上記のように、事業再生計画書は、企業再生において必要不可欠な存在です。単なる形式的な書類ではなく、企業の未来を左右する重要なツールと言えるでしょう。作成には専門的な知識が必要となる場合もあるため、必要に応じて専門家の支援を受けることも検討しましょう。
2. 事業再生計画書の作り方
事業再生計画書は、企業が経営危機に陥った際に、その再建を図るための具体的な計画をまとめた文書です。金融機関からの融資継続や新規融資を受けるため、あるいは取引先や従業員の理解と協力を得るために不可欠なものです。この章では、事業再生計画書の具体的な作成手順を解説します。
2.1 現状分析
再生計画を策定する前に、まず現状を客観的に分析することが重要です。財務状況と事業上の課題を明確に把握することで、効果的な再生計画を立案できます。
2.1.1 財務状況の分析財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)を分析し、経営悪化の原因を特定します。売上高の推移、収益性、債務状況、資金繰りなどを詳細に分析し、問題点を明確にしましょう。以下の項目に着目すると良いでしょう。
| 売上高の推移と減少原因 | |
| 粗利益率、営業利益率の推移と低下の原因 | |
| 固定費、変動費の比率と増加要因 | |
| 流動比率、自己資本比率などの安全性指標の推移 | |
| 債務の構成と返済能力 | |
| キャッシュフローの現状と問題点 |
これらの分析を通して、財務状況の悪化要因を特定し、再生計画に反映させるべき重要なポイントを抽出します。
2.1.2 事業上の課題の分析財務分析に加えて、事業上の課題も分析する必要があります。市場環境の変化、競合他社の動向、自社の強みと弱み、経営体制の問題点など、多角的な視点から分析を行いましょう。例えば、SWOT分析を用いることで、自社の現状を客観的に把握することができます。
| 強み(Strengths) | 弱み(Weaknesses) |
|---|---|
|
|
| 機会(Opportunities) | 脅威(Threats) |
|
|
これらの分析結果を基に、事業上の課題を明確化し、具体的な対策を検討します。
2.2 再生計画の策定
現状分析を踏まえ、具体的な再生計画を策定します。計画は実現可能な範囲で、かつ金融機関を説得できる内容でなければなりません。
2.2.1 具体的な施策とスケジュール現状分析で明らかになった問題点に対する具体的な施策を立案し、実行スケジュールを策定します。不採算事業の撤退、コスト削減、新規事業の立ち上げ、営業戦略の見直しなど、具体的な施策を明確に示すことが重要です。それぞれの施策について、誰が、いつまでに、何を行うのかを具体的に記載することで、計画の実行可能性を高めます。
例えば、コスト削減策としては、以下のような項目が考えられます。
| 人件費削減 | 早期退職優遇制度の導入、残業時間の削減 |
|---|---|
| 広告宣伝費削減 | 効果の低い広告媒体の見直し |
| 外注費削減 | 内製化の推進、取引先の選定見直し |
| 賃料削減 | 事務所移転の検討 |
再生計画の成果を測るための数値目標を設定します。売上高、利益率、債務償還率など、具体的な数値目標を設定し、計画の進捗状況を管理します。目標値は、現状分析の結果を踏まえ、現実的で達成可能な範囲で設定する必要があります。また、金融機関が納得できる根拠を示すことが重要です。例えば、売上高の目標値を設定する場合、市場規模や競合他社の動向、自社の営業力などを考慮し、実現可能な数値を設定する必要があります。
3年後までの売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の目標値を提示し、その根拠を明確に説明することで、金融機関の理解と協力を得やすくなります。
2.3 金融機関への説明資料の作成
作成した事業再生計画書は、金融機関への説明資料として使用されます。金融機関は、提出された事業再生計画書に基づいて、融資の可否を判断します。そのため、計画の内容を分かりやすく説明し、金融機関の理解と協力を得ることが重要です。事業再生計画書には、以下の内容を記載する必要があります。
| 会社の概要 | |
| 現状分析 | |
| 再生計画の概要 | |
| 具体的な施策とスケジュール | |
| 数値目標 | |
| 財務諸表 |
これらの情報を整理し、図表やグラフなどを用いて視覚的に分かりやすく説明することで、金融機関の理解を深めることができます。また、金融機関からの質問に的確に回答できるように、事前に想定される質問と回答を用意しておくことも重要です。
【関連】事業再生のための資金調達【成功事例から学ぶ実践ガイド】3. 金融機関を説得するためのポイント
事業再生計画書は、金融機関の理解と協力を得るための重要なツールです。計画の良し悪しだけでなく、金融機関への説明方法も再生の成否を大きく左右します。ここでは、金融機関を説得するためのポイントを解説します。
3.1 説得力のある資料作成
金融機関は、数多くの事業再生計画書を目にしています。そのため、分かりやすく説得力のある資料を作成することが重要です。具体的には、以下の点に注意しましょう。
3.1.1 図表やグラフの活用現状分析や将来予測などの数値データは、図表やグラフを用いて視覚的に分かりやすく提示することで、金融機関の理解を促進します。複雑な財務状況や事業の課題も、視覚化することで直感的に把握しやすくなります。例えば、売上高や利益の推移、債務の状況などをグラフで示すことで、現状の問題点や再生計画の効果を明確に伝えることができます。また、キャッシュフロー予測をグラフ化することで、返済能力を具体的に示すことが可能です。
3.1.2 ストーリー性のある構成事業再生計画書は、単なる数値の羅列ではなく、企業の再生ストーリーを伝えるものであるべきです。現状分析で課題を明確にし、再生計画で具体的な解決策を示し、将来の展望を描くことで、金融機関に共感と納得感を与え、支援への意欲を高めることができます。
例えば、過去の成功体験や経営理念、従業員の想いを織り交ぜることで、企業の再生への強い意志を伝えることができます。また、地域社会への貢献や雇用の維持といった視点も盛り込むことで、金融機関の理解を深めることができます。
3.2 金融機関とのコミュニケーション
事業再生計画書の作成だけでなく、金融機関との積極的なコミュニケーションも重要です。信頼関係を構築することで、円滑な交渉を進めることができます。
3.2.1 誠実な対応金融機関との交渉においては、誠実な対応が不可欠です。現状を隠さず、課題を率直に伝え、真摯な姿勢で対応することで、金融機関の信頼を得ることができます。不明点や疑問点には、迅速かつ正確に回答するよう心がけましょう。また、定期的に状況を報告し、進捗状況を共有することも重要です。金融機関との良好な関係を築くことで、再生への支援を得やすくなります。
3.2.2 質問への的確な回答金融機関は、事業再生計画の内容について様々な質問をしてきます。質問の意図を正確に理解し、的確に回答することで、金融機関の不安を解消し、信頼感を高めることができます。想定される質問への回答を事前に準備しておくことで、スムーズな説明が可能になります。例えば、財務状況の悪化要因、再生計画の具体性、リスク対策などについて、具体的な根拠に基づいた説明を準備しておきましょう。
| ポイント | 詳細 |
|---|---|
| 資料作成 | 図表やグラフを活用し、視覚的に分かりやすく説明する。ストーリー性のある構成で、金融機関の共感を得る。 |
| コミュニケーション | 誠実な対応で信頼関係を構築する。質問には的確に回答し、金融機関の不安を解消する。 |
| その他 | 金融機関の担当者との良好な人間関係を築く。金融機関の視点に立ち、彼らのニーズを理解する。金融支援以外の選択肢も検討する。 |
これらのポイントを踏まえ、金融機関を説得するための効果的な事業再生計画書を作成し、再生への道を切り開きましょう。
4. 事業再生計画書の実例解説
事業再生計画書は、業種や企業規模、直面する課題によってその内容は大きく異なります。ここでは、異なる業種の事例を通して、具体的な事業再生計画書の内容を解説します。それぞれ「現状分析」「再生計画の策定」「金融機関への説明資料の作成」といった構成で説明し、ポイントを解説します。
4.1 製造業の事例 4.1.1 中小企業A社(金属加工業)の例
現状分析
主要取引先の倒産により売上が急減、資金繰りが悪化。過剰設備投資による借入金の負担も重荷となっている。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務状況 | 売上高前年比50%減、債務超過 |
| 事業上の課題 | 取引先の偏り、過剰設備、低い生産効率 |
再生計画の策定
新規取引先の開拓(営業強化、展示会出展)、設備売却による債務圧縮、生産工程の見直しによる効率化を図る。
| 施策 | スケジュール | 数値目標 |
|---|---|---|
| 新規取引先開拓 | 3ヶ月以内に5社、1年以内に20社 | 売上高前年比20%増 |
| 設備売却 | 6ヶ月以内 | 借入金30%削減 |
| 生産工程見直し | 1年以内 | 生産性20%向上 |
金融機関への説明資料の作成
新規取引先の開拓状況、設備売却の進捗、生産性向上によるコスト削減効果を数値で示し、返済能力の回復を強調する。中小企業再生支援協議会による支援も明記することで、金融機関の理解と協力を得やすくする。
4.2 飲食業の事例 4.2.1 飲食店B店(居酒屋)の例
現状分析
新型コロナウイルスの影響による客足減少、売上減少。固定費負担が重く、資金繰りが逼迫している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務状況 | 売上高前年比70%減、営業損失計上 |
| 事業上の課題 | 集客力低下、高い固定費、テイクアウト・デリバリー対応の遅れ |
再生計画の策定
テイクアウト・デリバリーの強化、オンライン販促による集客、コスト削減(家賃交渉、人員配置の見直し)を実施。
| 施策 | スケジュール | 数値目標 |
|---|---|---|
| テイクアウト・デリバリー強化 | 1ヶ月以内 | 売上高10%増 |
| オンライン販促 | 継続実施 | 新規顧客獲得数月50人 |
| コスト削減 | 3ヶ月以内 | 固定費15%削減 |
金融機関への説明資料の作成
テイクアウト・デリバリーの売上増加、オンライン販促による集客効果、コスト削減による収益改善を数値で示し、事業の継続可能性をアピールする。政府系金融機関の融資制度の活用も明記し、返済計画の具体性も示す。
4.3 小売業の事例 4.3.1 小売店C店(アパレル)の例
現状分析
消費低迷、競合激化により売上減少。過剰在庫を抱え、資金繰りが悪化している。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 財務状況 | 売上高前年比30%減、在庫増加 |
| 事業上の課題 | 販売力不足、ECサイト未整備、過剰在庫 |
再生計画の策定
ECサイト構築による販路拡大、在庫処分セールの実施、販売促進策の実施(ポイントカード導入、SNS活用)、仕入れの見直しによる在庫管理の最適化。
| 施策 | スケジュール | 数値目標 |
|---|---|---|
| ECサイト構築 | 3ヶ月以内 | 売上高15%増 |
| 在庫処分 | 2ヶ月以内 | 在庫20%削減 |
| 販売促進策 | 継続実施 | 新規顧客獲得数月30人 |
金融機関への説明資料の作成
ECサイトによる売上拡大、在庫削減によるキャッシュフロー改善、販売促進策による集客効果を数値で示し、将来的な収益性向上を強調する。商工会議所などによる経営相談の活用も明記し、経営改善への取り組み姿勢を示す。
【関連】事業再生コンサル費用はいくら?料金相場と賢い選び方を徹底解説5. まとめ
事業再生計画書は、経営危機に陥った企業が再建を図るための重要なツールです。金融機関からの融資継続や新規融資を受けるためには、説得力のある事業再生計画書を作成し、金融機関の理解と協力を得ることが不可欠です。本記事では、事業再生計画書の作り方を、現状分析、再生計画の策定、金融機関への説明資料の作成という流れに沿って解説しました。
財務状況や事業上の課題を分析し、具体的な再生計画を策定することで、企業の再建への道筋を示すことができます。図表やグラフを活用し、ストーリー性のある構成にすることで、金融機関にとって理解しやすい資料を作成することが重要です。また、金融機関との良好なコミュニケーションも重要です。
誠実な対応と的確な質問への回答は、金融機関の信頼獲得に繋がります。製造業、飲食業、小売業の実例を参考に、自社の状況に合わせた事業再生計画書を作成しましょう。本記事が、事業再生に取り組む企業の皆様の一助となれば幸いです。


