事業承継前に赤字解消!事業再生で黒字化させる3つのステップ
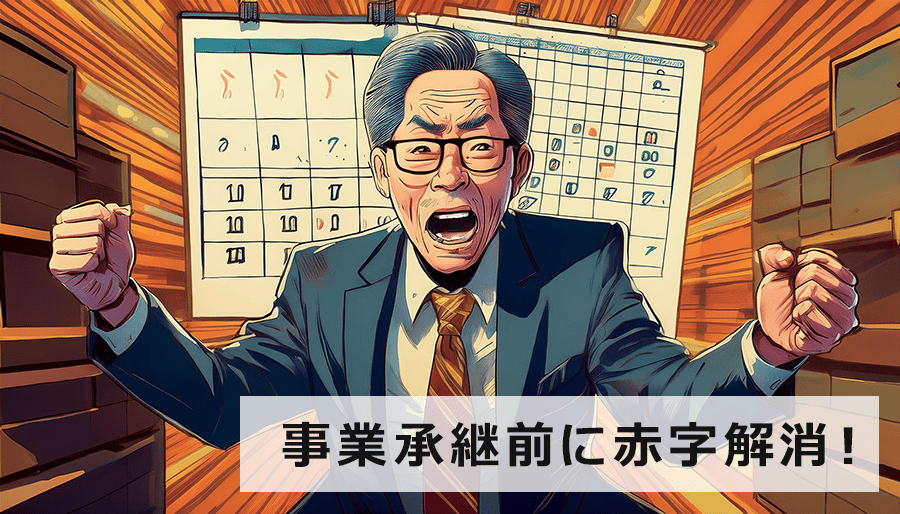
事業承継を控えているが、会社の業績が赤字で悩んでいませんか?赤字経営のままでは、事業をスムーズに引き継ぐことは困難です。本記事では、事業承継前に赤字を解消し、事業再生によって黒字化を実現するための3つのステップを解説します。事業承継を成功させるためには、事前に会社を健全な状態にすることが不可欠です。
この記事を読むことで、財務諸表の分析、収益構造の見直し、市場環境の把握といった現状分析の方法を理解し、赤字の根本原因を特定できるようになります。さらに、売上向上策、コスト削減策、事業再生計画書作成のポイントなどを学び、具体的な赤字解消策を立案できるようになります。
そして、PDCAサイクルを活用した計画の実行とモニタリング、軌道修正の方法を理解することで、事業承継前に黒字化を達成するための具体的な方法を習得できます。事業承継を成功させ、次世代へ会社を繋ぐために、ぜひこの記事を参考にしてください。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. 事業承継を成功させるために、なぜ事業再生が必要なのか?
事業承継は、会社の将来を左右する重要なイベントです。しかし、赤字経営の状態では、事業承継をスムーズに進めることは非常に困難です。後継者にとって、負債を抱えた会社を引き継ぐことは大きなリスクとなるからです。
また、金融機関からの融資も受けにくくなり、事業展開の足かせとなる可能性があります。事業再生によって会社を健全な状態に戻すことは、事業承継を成功させるための重要なステップと言えるでしょう。
1.1 赤字経営のままでは事業承継が困難な理由
赤字経営の状態では、後継者は以下の様な困難に直面する可能性があります。
| ● | ● |
|---|---|
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| ● | ● |
| 経営の不安定さ | 赤字経営は会社の存続自体を危うくする可能性があり、後継者は大きな不安を抱えることになります。 |
|---|---|
| 資金調達の困難さ | 金融機関は赤字企業への融資に慎重になるため、事業に必要な資金を調達することが難しくなります。設備投資や事業拡大の機会を失う可能性も高まります。 |
| 従業員のモチベーション低下 | 会社の業績が悪化すると、従業員のモチベーションが低下し、優秀な人材の流出につながる可能性があります。後継者は、士気の低い組織を立て直すという大きな課題を背負うことになります。 |
| 取引先の信用不安 | 赤字経営は取引先に不安感を与え、取引停止や契約解除のリスクを高めます。安定した事業運営が難しくなる可能性があります。 |
| 後継者自身の負担 | 赤字経営の会社を再建するには、多大な時間と労力が必要です。後継者自身の生活やキャリアにも影響を与える可能性があります。 |
1.2 事業再生で会社を健全化させるメリット
事業再生によって会社を健全化させることで、以下のようなメリットが得られます。
| メリット | 詳細 |
|---|---|
| 後継者への負担軽減 | 健全な財務状況の会社を引き継ぐことで、後継者の経営負担を軽減できます。 |
| 資金調達の円滑化 | 金融機関からの信頼性が高まり、資金調達が容易になります。 |
| 従業員のモチベーション向上 | 会社の業績改善は従業員のモチベーション向上に繋がり、優秀な人材の確保・定着に繋がります。 |
| 取引先からの信頼向上 | 健全な経営状態は取引先からの信頼向上に繋がり、安定した取引関係を築くことができます。 |
| 企業価値の向上 | 事業の収益性向上は、企業価値の向上に繋がります。 |
| 事業承継の円滑化 | 健全な会社を引き継ぐことで、後継者も安心して事業を承継できます。また、第三者への売却も容易になります。 |
1.3 黒字化がスムーズな事業承継の鍵となる
事業承継をスムーズに進めるためには、後継者が安心して経営を引き継げる環境を整えることが重要です。黒字化は、そのための重要な指標となります。黒字化を達成することで、後継者は事業の成長に集中できるようになり、持続可能な経営基盤を築くことができます。
また、黒字化は企業価値の向上にも繋がり、M&Aなど将来の選択肢を広げることにも繋がります。事業承継前に事業再生に取り組み、黒字化を達成することで、将来の成長に向けた基盤を築き、スムーズな事業承継を実現できるでしょう。
2. 事業再生ステップ1 現状分析:赤字の根本原因を特定する
事業再生の第一歩は、現状分析です。赤字の根本原因を特定しなければ、効果的な対策を打つことはできません。闇雲にコストカットを行うだけでは、事業の成長を阻害し、かえって状況を悪化させる可能性もあります。事業承継を成功させるためには、現状を正しく把握し、問題点を見つけることが不可欠です。
具体的には、財務諸表の分析、収益構造の分析、市場環境の分析などを行います。これらの分析を通して、会社の内部要因と外部要因の両面から赤字の原因を多角的に探ります。
2.1 財務諸表の分析で会社の現状を把握
財務諸表は、会社の財政状態や経営成績を示す重要な資料です。貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などを分析することで、会社の現状を客観的に把握できます。例えば、売上高の推移、利益率の動向、負債の規模、現金の流れなどを確認し、問題点や改善点を洗い出します。具体的には、以下の項目に着目します。
| 売上高の推移 | 過去数年間の売上高の増減傾向を分析し、市場の成長性や競争環境の変化などを把握します。 |
|---|---|
| 売上総利益率 | 売上高に対する売上総利益の割合を分析し、価格設定や原価管理の適切さを評価します。 |
| 営業利益率 | 売上高に対する営業利益の割合を分析し、本業の収益性を評価します。 |
| 経常利益率 | 売上高に対する経常利益の割合を分析し、企業全体の収益性を評価します。 |
| 自己資本比率 | 総資産に対する自己資本の割合を分析し、財務の健全性を評価します。 |
| 流動比率 | 流動資産と流動負債の比率を分析し、短期的債務返済能力を評価します。 |
| キャッシュフロー | 営業活動、投資活動、財務活動によるキャッシュフローを分析し、資金繰りの状況を把握します。 |
これらの指標を分析することで、財務状況の強みと弱みを把握し、事業再生のための具体的な対策を立てることができます。例えば、売上高が減少傾向にある場合は、その原因を市場の縮小や競争激化などから分析し、新たな市場開拓や競争優位性の構築といった対策を検討します。
2.2 収益構造の分析で問題点を発見
収益構造の分析では、どの事業が利益を生み出し、どの事業が損失を出しているのかを明らかにします。主要製品・サービス別の売上高、利益率、市場シェアなどを分析することで、収益の柱となっている事業や、逆に足を引っ張っている事業を特定できます。
また、顧客層別の売上貢献度を分析することで、優良顧客の維持・拡大や新規顧客の獲得に向けた戦略を立てることができます。例えば、特定の顧客層への依存度が高い場合は、リスク分散のために新たな顧客層を開拓する必要があるかもしれません。
また、特定の製品・サービスの収益性が低い場合は、その原因を分析し、改善策を検討する必要があります。例えば、製造コストが高い場合は、コスト削減策を検討する、あるいは価格の見直しを行う必要があるかもしれません。
2.3 市場環境の分析で外部要因の影響を把握
市場環境の分析では、業界全体の動向や競合他社の状況、顧客ニーズの変化などを調査します。 PEST分析、5フォース分析などのフレームワークを活用することで、外部環境が事業に与える影響を分析し、事業再生に役立てることができます。
例えば、市場の成長性が低い場合は、新たな市場への進出や新製品・サービスの開発を検討する必要があるかもしれません。競合他社が価格競争を仕掛けてきている場合は、コスト削減や差別化戦略を検討する必要があるかもしれません。顧客ニーズの変化を捉えることで、新たなビジネスチャンスを見つけることができるかもしれません。
| 分析項目 | 分析内容 | 活用方法 |
|---|---|---|
| PEST分析 | 政治、経済、社会、技術の各側面から外部環境を分析 | マクロ環境の変化を把握し、事業への影響を予測 |
| 5フォース分析 | 業界内の競争要因を分析(新規参入の脅威、代替品の脅威、供給者の交渉力、買い手の交渉力、既存企業間の競争) | 業界の競争状況を把握し、競争優位性を構築するための戦略を策定 |
| SWOT分析 | 企業の強み、弱み、機会、脅威を分析 | 事業環境を分析し、事業戦略を策定 |
2.4 事業承継前の現状分析で事業再生の成功確率を高める
事業承継前に徹底的な現状分析を行うことで、赤字の根本原因を特定し、効果的な事業再生計画を策定することができます。後継者に健全な事業を引き継ぐためには、現状分析に基づいた適切な対策が不可欠です。これらの分析をしっかりと行うことで、事業再生の成功確率を高め、スムーズな事業承継を実現することができます。
現状分析は、一度行えば終わりではなく、定期的に見直し、必要に応じて軌道修正を行うことが重要です。市場環境や競争状況は常に変化するため、現状分析も継続的に行うことで、変化に柔軟に対応し、事業の成長を維持していくことができます。また、現状分析の結果を後継者と共有することで、後継者の事業理解を深め、スムーズな事業承継につなげることができます。
3. 事業再生ステップ2 再生計画策定:具体的な赤字解消策を立案する
事業再生の中核となるのが、この再生計画策定です。現状分析で見出した問題点を踏まえ、具体的な赤字解消策を立案します。売上向上とコスト削減の両面からアプローチし、事業承継を見据えた持続可能な再生計画を策定することが重要です。
3.1 売上向上のための施策(事業承継前に売上を伸ばす施策例)
売上向上は事業再生の根幹であり、将来の事業承継をスムーズに進めるためにも不可欠です。現状分析の結果を基に、ターゲット顧客に最適な施策を検討・実行します。
3.1.1 新規顧客の獲得新たな顧客層を開拓することで、売上基盤の拡大を図ります。Webマーケティングを活用した集客や、新たな販路開拓などが有効です。
| SEO対策 | 検索エンジン最適化を行い、ウェブサイトへのアクセス数を増加させる。 |
|---|---|
| リスティング広告 | Google広告などを活用し、ターゲットを絞った広告配信を行う。 |
| SNSマーケティング | Facebook、Instagram、Xなどのソーシャルメディアを活用し、情報発信や顧客とのエンゲージメントを高める。 |
| 展示会・セミナーへの出展 | 新たな顧客との接点を創出し、ビジネスチャンスを広げる。 |
| 異業種交流会への参加 | 新たなパートナーシップ構築や販路開拓の可能性を探る。 |
既存顧客との関係強化は、安定的な売上確保に繋がります。顧客ロイヤルティを高める施策が重要です。
| CRMシステムの導入 | 顧客情報を一元管理し、顧客ニーズに合わせたサービス提供を行う。 |
|---|---|
| ロイヤルティプログラムの実施 | ポイント制度や会員限定サービスなど、顧客の継続利用を促進する。 |
| アフターサービスの充実 | 顧客満足度を高め、リピーター獲得につなげる。 |
| 定期的な顧客アンケートの実施 | 顧客の声を収集し、サービス改善に役立てる。 |
市場のニーズを捉えた新商品・サービスの開発は、新たな収益源の創出に繋がります。競合他社との差別化を図り、独自の強みを活かした商品開発が重要です。
| 市場調査の実施 | 顧客ニーズや市場動向を的確に把握する。 |
|---|---|
| 競合分析 | 競合他社の強み・弱みを分析し、自社の優位性を明確にする。 |
| 技術開発への投資 | 革新的な技術開発により、競争力を強化する。 |
| デザイン性の向上 | 商品・サービスの魅力を高め、顧客の購買意欲を高める。 |
3.2 コスト削減のための施策(事業承継前にコストを削減する施策例)
無駄なコストを削減することで、利益率の改善を図ります。固定費、変動費、人件費など、多角的な視点からコスト削減策を検討します。
3.2.1 固定費の削減家賃、光熱費、通信費など、固定的に発生する費用を見直し、削減可能な項目を特定します。
| 項目 | 削減策 |
|---|---|
| 家賃 | オフィス移転、賃貸契約の見直し |
| 光熱費 | 省エネ機器の導入、節電対策 |
| 通信費 | プランの見直し、不要な回線の解約 |
仕入れコスト、販売促進費など、売上高に応じて変動する費用を見直し、効率化を図ります。
| 項目 | 削減策 |
|---|---|
| 仕入れコスト | 仕入先の変更、大量仕入れによる割引交渉 |
| 販売促進費 | 費用対効果の高い広告手法への転換 |
| 外注費 | 内製化、業務委託先の選定 |
業務プロセスを見直し、無駄な作業を省くことで、人件費の削減を図ります。ITツール導入による業務効率化も有効です。
| 業務フローの見直し | 無駄な作業を特定し、効率的なプロセスを構築する。 |
|---|---|
| ITツール導入 | 業務自動化ツール、RPAなどを活用し、作業効率を高める。 |
| テレワーク導入 | 通勤時間を削減し、生産性向上を図る。 |
| スキルアップ研修 | 従業員のスキル向上を図り、生産性を高める。 |
3.3 事業再生計画書の作成(事業承継を見据えた計画書作成のポイント)
策定した再生計画を具体的に落とし込んだ事業再生計画書を作成します。事業承継を視野に入れ、後継者が理解しやすい内容とすることが重要です。
| 現状分析 | 会社の現状と課題を明確に記述する。 |
|---|---|
| 再生計画 | 具体的な売上向上策、コスト削減策、数値目標を記載する。 |
| 実行体制 | 誰が、いつ、どのように計画を実行するかを明確にする。 |
| モニタリング方法 | 計画の進捗状況をどのように把握し、軌道修正を行うかを記載する。 |
| 資金繰り計画 | 再生計画に必要な資金調達方法、返済計画を明確にする。 |
| 事業承継計画との整合性 | 事業再生計画と事業承継計画を連携させ、スムーズな事業承継を実現する。 |
事業再生計画書は、金融機関からの融資を受ける際にも必要となる重要な資料です。説得力のある計画書を作成することで、事業再生への支援を得やすくなります。
【関連】事業承継のための事業計画書作成ガイド|書き方、注意点、成功事例を紹介4. 事業再生ステップ3 実行・モニタリング:計画を着実に実行し、軌道修正を行う
事業再生計画を策定したら、いよいよ実行段階に入ります。しかし、計画通りに進むとは限りません。市場環境の変化や予期せぬトラブルなど、様々な要因によって計画が頓挫する可能性もあります。そのため、計画の実行と並行してモニタリングを行い、必要に応じて軌道修正を行うことが重要です。
このステップを怠ると、せっかく策定した事業再生計画も絵に描いた餅となってしまいます。事業承継を成功させるためには、PDCAサイクルを回し、計画を着実に実行し、モニタリングと軌道修正を繰り返すことで、黒字化への道を着実に歩む必要があります。
4.1 PDCAサイクルを回し、事業再生計画を着実に実行
PDCAサイクルとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の4つのプロセスを繰り返すことで、継続的な改善を目指す経営管理手法です。事業再生においても、このPDCAサイクルを回すことが不可欠です。計画を実行したら、その結果を評価し、問題点があれば改善策を講じ、次の計画に反映させます。このサイクルを繰り返すことで、計画の精度を高め、事業再生の成功確率を高めることができます。
例えば、売上向上のための施策として、新規顧客獲得のための広告キャンペーンを実施したとします。実行後、その成果をアクセス数や問い合わせ数、新規契約数などの指標で評価します。もし、目標値に達していなければ、広告の内容やターゲット層、掲載媒体などを再検討し、改善策を講じます。そして、次の広告キャンペーンでは、その改善策を反映させ、より効果的な施策を実行します。
4.2 モニタリングで進捗状況を把握し、必要に応じて軌道修正
計画の実行中は、定期的にモニタリングを行い、進捗状況を把握することが重要です。モニタリングでは、売上高、利益率、キャッシュフローなどの財務指標だけでなく、顧客満足度、従業員満足度、市場シェアなどの非財務指標も確認します。これらの指標を総合的に分析することで、事業再生計画が順調に進んでいるかを判断できます。
もし、モニタリングの結果、計画から大きく逸脱している場合は、軌道修正が必要です。軌道修正では、当初の計画を見直し、現状に合わせて修正します。例えば、売上高が計画を下回っている場合は、売上向上のための施策を強化したり、コスト削減のための施策を追加したりする必要があります。
また、市場環境が大きく変化した場合は、事業再生計画自体を根本的に見直す必要があるかもしれません。重要なのは、現状を正確に把握し、迅速に軌道修正を行うことです。
モニタリングの頻度は、事業の状況や計画の内容によって異なりますが、少なくとも月次、できれば週次で行うことが望ましいです。また、モニタリングの結果は、関係者間で共有し、今後の対応策を検討することが重要です。事業承継を円滑に進めるためにも、後継者への情報共有も積極的に行いましょう。
4.3 事業承継前に黒字化を達成するためのポイント4.3 事業承継前に黒字化を達成するためのポイント
事業承継前に黒字化を達成するためには、以下のポイントに留意することが重要です。
| ポイント | 詳細 | 具体例 |
|---|---|---|
| 早期に着手する | 事業再生には時間がかかるため、事業承継の数年前から計画的に取り組む必要がある。 | 後継者育成と並行して、事業再生計画を策定し、実行を開始する。 |
| 外部専門家の活用 | 事業再生の専門家である中小企業診断士や税理士、弁護士などに相談することで、客観的な視点からのアドバイスを得ることができる。 | 事業再生計画の策定や実行支援、金融機関との交渉などを依頼する。 |
| 金融機関との連携 | 事業再生には資金が必要となる場合があるため、金融機関との良好な関係を築き、融資などの支援を受けることが重要。 | 事業再生計画を金融機関に提示し、理解と協力を得る。 |
| 従業員とのコミュニケーション | 事業再生は従業員の協力なくしては成功しないため、計画の内容や進捗状況を丁寧に説明し、理解と協力を得ることが重要。 | 定期的に説明会を開催したり、社内報などで情報を発信する。 |
| 後継者への引継ぎ | 事業再生計画の内容や進捗状況を後継者にしっかりと引継ぎ、事業承継後もスムーズに事業を継続できる体制を構築する。 | 後継者を事業再生計画の策定段階から参画させ、実務経験を積ませる。 |
これらのポイントを踏まえ、事業再生を着実に実行し、モニタリングと軌道修正を繰り返すことで、事業承継前に黒字化を達成し、スムーズな事業承継を実現できるでしょう。事業の将来を担う後継者のため、そして企業の永続的な発展のために、早期の事業再生に着手し、健全な経営基盤を築くことが重要です。
5. まとめ
事業承継を成功させるためには、事前の事業再生による黒字化が不可欠です。赤字経営のままでは、後継者への負担が大きく、金融機関からの融資も難しくなるなど、事業承継が困難になる可能性が高まります。この記事では、事業承継前に赤字を解消し、黒字化を実現するための3つのステップをご紹介しました。
ステップ1の現状分析では、財務諸表、収益構造、市場環境を分析することで、赤字の根本原因を特定します。ステップ2の再生計画策定では、売上向上策とコスト削減策を具体的に立案し、事業承継を見据えた事業再生計画書を作成します。ステップ3の実行・モニタリングでは、PDCAサイクルを回し、計画を着実に実行し、進捗状況を把握しながら軌道修正を行います。
これらのステップを踏むことで、事業承継前に黒字化を達成し、スムーズな事業承継を実現できる可能性が高まります。事業承継を控えている経営者は、ぜひこの記事を参考に、早期の事業再生に着手しましょう。帝国データバンクの調査でも、黒字企業の事業承継の方が成功率が高いという結果が出ています。後継者への負担軽減、金融機関からの信頼向上のためにも、事業再生による健全化は重要です。


