M&Aでの役員退職金による賢い節税対策
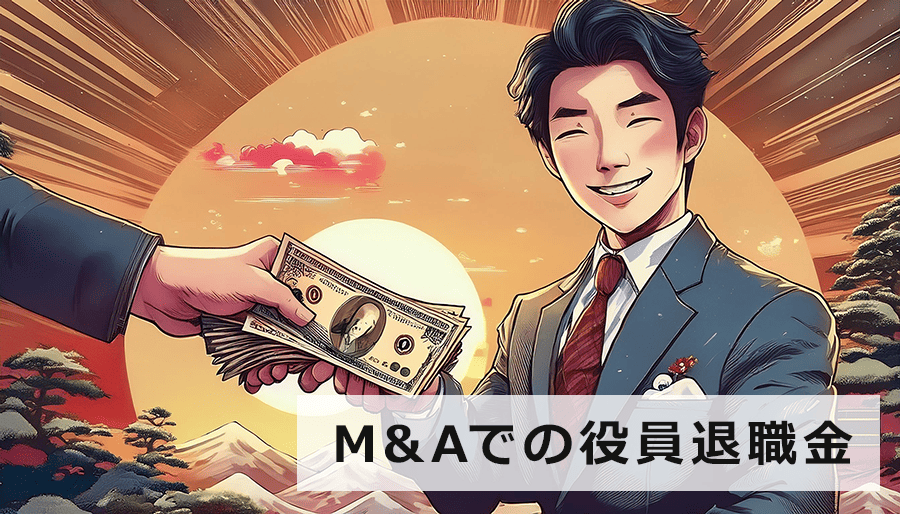
M&Aを検討している企業の役員にとって、退職金の賢い節税対策は重要な関心事です。このページでは、M&Aと役員退職金の関係性、M&Aを活用した節税の仕組み、具体的な節税対策の種類、そして注意点までを網羅的に解説します。M&Aによる株式価値の上昇を最大限に活かし、退職金の税負担を軽減するための具体的な方法を理解することができます。
退職金課税の仕組みやM&A前後の税制優遇措置、退職金規程の見直し、株式による退職金支給、信託の活用など、多角的な視点から最適な節税対策を検討できます。また、税務リスクへの対策や事業承継対策との連携についても言及し、安全かつ効果的な節税を実現するためのポイントを解説。
この記事を読むことで、M&Aという大きな転換期において、役員退職金を適切に設計し、将来の資産形成を有利に進めるための知識と戦略を身につけることができます。スムーズなM&Aと、その後の豊かな人生設計のための第一歩を踏み出しましょう。
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. M&Aと役員退職金の関係
M&A(合併・買収)は、企業の経営環境を大きく変化させるイベントであり、役員報酬、特に退職金にも大きな影響を与えます。M&Aによって企業価値が変動することで、退職金の算定基準となる金額も変動する可能性があるため、M&Aを検討する際には、役員退職金への影響を十分に理解しておく必要があります。また、M&Aは、役員退職金の節税対策を実施する大きな契機となる場合もあります。
1.1 M&Aが役員退職金に与える影響
M&Aが役員退職金に与える影響は、M&Aの形態や対象企業の状況によって異なりますが、一般的には以下のような影響が考えられます。
| M&Aの形態 | 役員退職金への影響 |
|---|---|
| 吸収合併 | 吸収される側の会社の役員は、退職もしくは転籍となる場合があり、その際に退職金が発生します。 |
| 株式交換・株式移転 | 支配権の移動に伴い、経営方針の変更や役員交代が行われる場合があり、退職金が発生する可能性があります。 |
| 事業譲渡 | 譲渡される事業に従事する役員は、退職もしくは転籍となる場合があり、その際に退職金が発生します。 |
また、M&Aによって企業価値が上昇した場合、退職金の算定基準となる金額も増加する可能性があります。逆に、企業価値が下落した場合には、退職金も減少する可能性があります。さらに、M&A後の経営方針によっては、退職金規程自体が見直されるケースもあります。
1.2 退職金の節税対策を考えるタイミング
M&Aにおける役員退職金の節税対策は、M&Aの実行前、つまり検討段階から計画的に進めることが重要です。M&Aの交渉が本格化する前に、自社の退職金規程の内容や役員の状況を把握し、最適な節税対策を検討する必要があります。
M&A前の対策としては、退職金規程の見直しや株式給付信託の導入などが挙げられます。M&A後においても、M&A後の事業計画や組織体制に合わせて、退職金規程を適切に見直すことが重要です。
具体的には、以下のようなタイミングで節税対策を検討することが重要です。
| M&Aの検討開始時 | |
| デューデリジェンス実施時 | |
| 基本合意締結時 | |
| 最終契約締結時 | |
| M&A実行後 |
これらのタイミングで専門家と相談し、適切な節税対策を講じることで、M&Aによる税務リスクを最小限に抑え、スムーズな事業承継を実現することが可能となります。
【関連】会社売却における税金対策|中小企業のM&Aで注意するポイントとは?2. M&Aを活用した役員退職金による節税の仕組み
M&Aは、企業価値を大きく変動させるイベントであり、役員退職金にも大きな影響を与えます。M&Aによる企業価値の変化を理解し、適切なタイミングで退職金制度を見直すことで、大きな節税効果が期待できます。ここでは、M&Aを活用した役員退職金による節税の仕組みについて解説します。
2.1 M&Aによる株式価値の上昇と退職金
M&A、特に買収される側にとっては、株式価値が上昇するケースが多く見られます。これは、買収企業がプレミアムを上乗せして株式を取得するためです。この株式価値の上昇は、株式で退職金を支給している場合、退職金の増額に繋がります。また、M&Aによって企業の業績が向上した場合も、将来的に退職金が増加する可能性があります。
2.2 退職金課税のしくみ
退職金への課税は、退職所得控除額を差し引いた金額に対して行われます。退職所得控除額は、勤続年数に応じて変動し、長期間勤続した役員ほど大きな控除を受けられます。また、退職金の支給方法によっても課税額が異なります。一括で支給される場合は退職所得として課税され、年金形式で支給される場合は公的年金等控除の対象となります。
| 支給方法 | 課税方法 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 一括支給 | 退職所得 | 一度にまとまった資金を受け取れる | 税率が高くなる可能性がある |
| 年金支給 | 公的年金等控除 | 税負担が軽減される可能性がある | 一度にまとまった資金を受け取れない |
2.3 M&A前後の退職金への税制優遇措置
M&Aを契機に、役員退職金に関する税制優遇措置を活用できる場合があります。例えば、M&A前に退職金規程を見直し、退職金の支給額や支給方法を最適化することで、税負担を軽減できる可能性があります。
また、M&A後に自社株を売却し、その売却益を元手に退職金を支給する場合、一定の条件を満たせば税制上の優遇措置を受けられる場合があります。具体的には、株式の譲渡益に対して軽減税率が適用されるケースなどがあります。これらの優遇措置を適切に活用することで、M&Aに伴う税負担を最小限に抑えることが可能です。
ただし、これらの税制優遇措置は、M&Aの形態や企業の状況、適用される法律によって異なるため、事前に専門家へ相談し、適切なスキームを構築することが重要です。例えば、M&A後の事業承継を視野に入れている場合は、事業承継税制との兼ね合いも考慮する必要があります。また、税務上のリスクを回避するためにも、最新の税制改正情報や判例を踏まえた上で、慎重に検討を進める必要があります。
3. M&Aにおける役員退職金の節税対策の種類
M&Aを契機として、役員退職金の節税対策を検討することは、企業にとって重要な戦略となります。ここでは、M&Aにおける役員退職金の節税対策の種類を具体的に解説します。適切な対策を実施することで、役員への適切な報酬を確保しつつ、企業の税負担を軽減することが可能になります。
3.1 退職金規程の見直しによる節税
M&Aの実施は、退職金規程を見直す絶好の機会です。既存の規程では、M&A後の企業規模や事業内容にそぐわない可能性があるため、見直しによって節税効果を高めることができます。
3.1.1 M&A前に役員退職金規程を見直すメリットM&A前に退職金規程を見直すことで、M&A後の企業価値向上による退職金増額分への課税を抑制できます。また、M&Aに伴う組織変更や人事異動に対応した規程にすることで、将来的なトラブルを未然に防ぐ効果も期待できます。
3.1.2 M&Aを機に役員退職金規程を整備する際の注意点退職金規程の変更は、株主総会決議が必要な場合もあります。また、税務上の問題が発生しないよう、国税庁のガイドラインや判例を踏まえた内容にする必要があります。弁護士や税理士等の専門家への相談が不可欠です。
3.2 株式による退職金支給と節税効果
M&Aにより株式価値が上昇した場合、自社株を退職金の一部として支給することで、節税効果が期待できます。具体的には、退職所得として課税される金額を抑え、譲渡所得として扱うことで税負担を軽減できます。ただし、自社株の評価額や譲渡時期など、注意すべき点も存在します。
| メリット | デメリット | 注意点 |
|---|---|---|
税負担の軽減 |
株価変動リスク |
自社株評価の適正性 |
役員の資産形成支援 |
換金性 |
譲渡制限の有無 |
3.3 信託を活用した退職金設計と節税
信託を活用することで、退職金の支払いを柔軟に設計し、節税効果を高めることが可能です。例えば、退職金の一部を信託財産として積み立て、一定期間後に受益者である役員に給付する方法があります。信託の種類やスキームによって、税務上の取扱いが異なるため、専門家との綿密な検討が必要です。
| 信託の種類 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
金銭信託 |
手続きが比較的簡単 |
運用益への課税 |
生命保険信託 |
死亡保障の確保 |
信託報酬等のコスト |
不動産信託 |
不動産の有効活用 |
流動性の低さ |
これらの対策は、M&Aの規模や形態、役員の状況などによって最適な方法が異なります。専門家と連携し、状況に合わせた適切な対策を選択することが重要です。中小企業庁のM&Aガイドラインなども参考に、多角的な視点から検討を進めましょう。
4. M&Aでの役員退職金節税における注意点
M&Aによる役員退職金の節税は、適切なプランニングと実行が不可欠です。税務リスクを理解し、専門家と連携しながら進めることで、思わぬトラブルを回避し、最適な節税効果を実現できます。本章では、M&Aにおける役員退職金節税の注意点と対策、事業承継との連携、専門家活用の重要性について解説します。
4.1 税務リスクと対策
M&Aに伴う役員退職金節税には、税務リスクが潜んでいます。例えば、退職金の支給額が過大であると認められた場合、法人税の否認や役員への所得税の追徴課税といったリスクがあります。また、退職金規程の変更が恣意的と判断されると、税務上のメリットが認められない可能性も。これらのリスクを回避するためには、以下の対策が重要です。
| リスク | 対策 |
|---|---|
| 退職金の過大支給 | 同業他社の役員退職金水準や過去の支給実績を参考に、適正な金額を設定する。経済産業省の「役員報酬・退職金に関する実態調査」などの公的資料も活用する。 |
| 退職金規程変更の恣意性 | M&A以前から退職金規程の見直しを検討し、変更の経緯を明確に記録しておく。M&Aを目的とした一時的な変更ではなく、長期的視点での変更であることを示す。 |
| 株式評価の不適切さ | M&Aにおける株式評価は、適正な評価方法を用いて行う。評価方法の選択理由や評価額の根拠を明確に documentation し、税務調査に備える。 |
| みなし譲渡課税 | 株式を保有する役員が退職し、一定の要件を満たすと、株式を譲渡したとみなされ課税される場合があります。この点も考慮し、退職金の設計を行う必要があります。 |
4.1.1 M&A前の自社株評価の重要性
M&A前の自社株評価は、M&A成立時の株価との差額によって、退職金の節税効果に大きく影響します。M&Aを見据えている場合は、事前に適切な評価を行い、記録しておくことが重要です。
4.2 M&A後の事業承継対策との連携
M&Aと事業承継は密接に関連しています。M&Aを機に後継者への事業承継を検討する場合、役員退職金は事業承継対策の一環として捉えることができます。後継者への株式譲渡や経営権の移譲と合わせて、退職金による資産の移転を計画的に行うことで、スムーズな事業承継を実現できます。例えば、後継者への株式贈与と退職金を組み合わせることで、相続税と贈与税の負担を軽減できる可能性があります。
【関連】事業承継の進め方ガイド|後継者と考える引継ぎ、コスト対策まで徹底解説!4.3 専門家への相談の重要性
M&Aに伴う役員退職金の節税は、複雑な税法や手続きが絡むため、専門家への相談が不可欠です。税理士や弁護士、M&Aアドバイザーといった専門家は、最新の税制や判例を踏まえ、最適な節税プランを提案してくれます。また、税務調査への対応やリスク管理についてもサポートを受けることができます。
M&Aによる役員退職金節税を検討する際は、早期に専門家に相談し、綿密な計画を立てることが成功の鍵となります。特に、M&Aのスキームや会社の状況、個々の役員の状況によって最適な方法は異なるため、専門家のアドバイスは非常に重要です。例えば、株式交換や合併などのM&A手法によって、退職金課税への影響が異なるため、専門家の知見に基づいた判断が求められます。
5. まとめ
M&Aを検討する際には、役員退職金への影響と節税対策を早期に検討することが重要です。M&Aによる企業価値の上昇は、退職金の増額につながる可能性がありますが、同時に税負担も増加する可能性があります。適切なタイミングで退職金規程を見直し、税制優遇措置を活用することで、M&Aによるメリットを最大限に享受しつつ、税負担を軽減することが可能です。
具体的には、M&A前に退職金規程を見直し、退職金の支給額や支給方法を最適化することで、将来の税負担を軽減できます。また、株式による退職金支給や信託を活用した退職金設計も有効な節税対策となります。これらの手法は、税務上のメリットが大きい一方で、複雑な手続きが必要となる場合もあります。そのため、税理士や弁護士などの専門家と連携し、適切なアドバイスを受けることが重要です。
M&A後の事業承継対策との連携も考慮しながら、総合的な視点で退職金制度を設計することで、企業の持続的な成長と円滑な事業承継を実現できるでしょう。税務リスクを最小限に抑え、最適な節税対策を実施するためにも、専門家への相談は不可欠です。


