経営再建と私的整理、その決定的な違いとは?
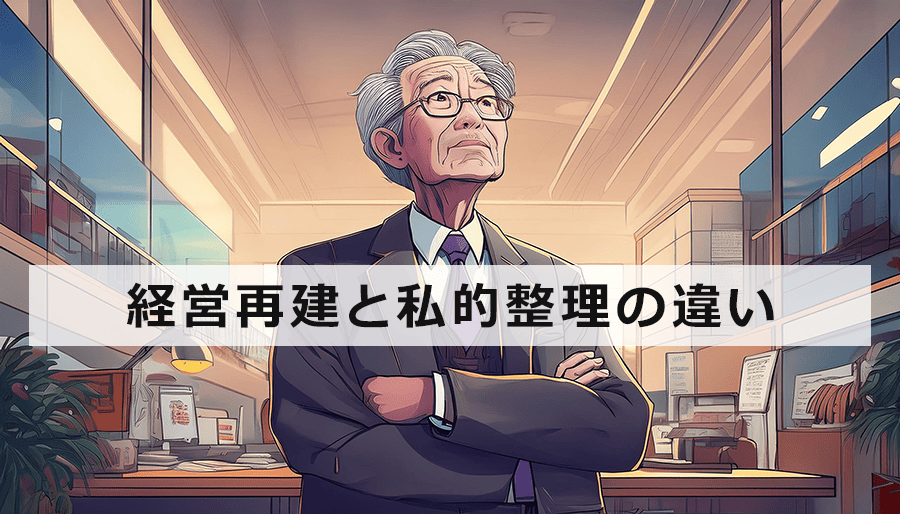
「経営再建」と「私的整理」、どちらも経営危機に瀕した企業が取る手段ですが、その違いを正しく理解していますか? この違いを理解していないと、適切な対策を打てず、事業継続が難しくなる可能性も。本記事では、経営再建と私的整理の定義や目的、手続き、メリット・デメリットなどを分かりやすく解説します。
具体的には、業績悪化や資金繰り悪化といった兆候から、債権放棄、債務免除、リスケジュールといった私的整理の種類、法的拘束力の有無、費用や期間、経営陣の関与の違いまで徹底的に比較。さらに、帝国データバンクの倒産事例なども参考に、それぞれのメリット・デメリットを明確化することで、あなたの会社に最適な選択を見つけるための判断基準を提供します。専門家への相談の重要性についても触れているので、経営に不安を抱えている経営者の方、事業再生コンサルタントを目指す方など、必見の内容です。
「赤字解消(経営再建)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・事業再生などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建とは何か?
経営再建とは、業績が悪化し、事業継続が困難になった企業が、その原因を分析し、抜本的な対策を講じることで、再び収益を上げ、健全な経営状態へと回復させる取り組みのことです。単に一時的な業績の回復を目指すのではなく、中長期的な視点で企業の存続と成長を図ることを目的としています。財務状況の改善だけでなく、事業構造の改革、組織体制の見直し、経営戦略の転換など、多岐にわたる施策が含まれます.
【関連】経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!1.1 経営再建の定義と目的
経営再建は、企業が継続的に事業を営むための重要なプロセスであり、その目的は企業価値の維持・向上、債権者への弁済、雇用の維持などです。単なるコスト削減や資産売却ではなく、事業の収益性向上、競争力の強化、持続可能な成長の実現を目指します。具体的には、新規事業の開発、既存事業の効率化、不採算事業からの撤退、組織のスリム化、人材育成、財務体質の強化など、多角的な取り組みが必要となります。
1.2 経営再建が必要となる兆候
経営再建が必要となる兆候は様々ですが、早期発見と適切な対応が、再建の成功を大きく左右します。主な兆候としては、業績の悪化、資金繰りの悪化、市場シェアの低下などが挙げられます。これらの兆候を見逃さず、迅速な対応を行うことが重要です。
1.2.1 業績の悪化売上の減少、利益率の低下、赤字の継続など、業績が悪化している場合は、経営再建が必要となる可能性が高いです。特に、本業からの収益が減少している場合は、早急な対策が必要です。
| 項目 | 兆候 |
|---|---|
| 売上高 | 前年比で大幅に減少 |
| 営業利益 | 赤字転落、または赤字幅の拡大 |
| 経常利益 | 減少傾向 |
| 純利益 | 大幅な赤字 |
運転資金の不足、借入金の返済困難、手形の不渡りなど、資金繰りが悪化している場合も、経営再建が必要となる兆候です。資金繰りの悪化は、事業の継続を脅かす重大な問題であり、迅速な対応が求められます。
| 項目 | 兆候 |
|---|---|
| 運転資金 | 不足し、日々の事業運営に支障が出る |
| 借入金 | 返済期限に間に合わない |
| キャッシュフロー | マイナスが続く |
| 手形 | 不渡りを出す |
競合他社の台頭、顧客ニーズの変化、製品・サービスの陳腐化などにより、市場シェアが低下している場合も、経営再建の必要性を検討すべきです。市場シェアの低下は、企業の競争力低下を示唆しており、中長期的な成長に悪影響を及ぼす可能性があります。例えば、競合他社に顧客を奪われている、新製品の開発が遅れている、顧客からのクレームが増加しているといった状況は、市場シェア低下の兆候と言えるでしょう。
| 項目 | 兆候 |
|---|---|
| 市場シェア | 競合他社に奪われ、低下傾向 |
| 顧客満足度 | 低下し、クレームが増加 |
| ブランドイメージ | 低下し、顧客からの信頼を失う |
| 製品・サービス | 陳腐化し、競争力を失う |
2. 私的整理とは何か?
私的整理とは、経営難に陥った企業が、裁判所を通さずに債権者との合意に基づいて、債務の減免や返済条件の変更などを行う手続きです。法的整理である会社更生法や民事再生法とは異なり、非公式な手続きであるため、柔軟性が高く、迅速な対応が可能です。私的整理の目的は、企業の事業継続を図りつつ、債権者への弁済を最大限に確保することです。倒産を回避し、再建を目指すための重要な手段となります。
2.1 私的整理の定義と目的
私的整理は、法律で明確に定義された手続きではありません。一般的には、金融機関などの債権者と債務者である企業が、自主的に協議を行い、合意に基づいて債務の処理を行うことを指します。私的整理の主な目的は、以下の2点です。
| 事業の継続 | 企業の活動を停止することなく、事業を継続させることを目指します。 |
|---|---|
| 債権者への弁済 | 債権者への影響を最小限に抑え、可能な範囲で弁済を行うことを目指します。 |
私的整理は、法的整理と比較して、手続きが簡素で、費用や時間も抑えられるというメリットがあります。また、裁判所を介さないため、企業の信用低下を最小限に抑えることができます。一方で、すべての債権者の同意が必要となるため、合意形成が難しい場合もあります。また、法的拘束力がないため、合意後に債権者が翻意するリスクも存在します。
2.2 私的整理の種類
私的整理には、様々な種類がありますが、主なものとしては以下の3つが挙げられます。
2.2.1 債権放棄債権放棄とは、債権者が債権の一部または全部を放棄することで、債務者の負担を軽減するものです。債務超過の状態にある企業にとって、債権放棄は財務状況を改善するための有効な手段となります。ただし、債権者にとっては損失となるため、合意を得ることは容易ではありません。
2.2.2 債務免除債務免除とは、債権者が債務の一部または全部を免除することで、債務者の負担を軽減するものです。債権放棄と同様に、債務超過の状態にある企業にとって、債務免除は財務状況を改善するための有効な手段となります。債権放棄との違いは、債権放棄は債権そのものが消滅するのに対し、債務免除は債務が残ったまま返済義務が免除される点です。
2.2.3 リスケジュールリスケジュール(リスケ、債務返済猶予)とは、債務の返済条件を変更することで、債務者の返済負担を軽減するものです。具体的には、返済期間の延長、返済額の減額、金利の減免などがあります。リスケジュールは、一時的な資金繰りの悪化に陥っている企業にとって、資金繰りを改善し、事業を継続するための有効な手段となります。債権者にとっては、債権回収の可能性を高める効果も期待できます。
| 種類 | 内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 債権放棄 | 債権者の一部または全部の債権を放棄 | 債務者の負担を大幅に軽減できる | 債権者にとって損失が大きく、合意形成が難しい |
| 債務免除 | 債務者の一部または全部の債務を免除 | 債務者の負担を大幅に軽減できる | 債権者にとって損失が大きく、合意形成が難しい |
| リスケジュール | 債務の返済条件を変更(返済期間延長、返済額減額、金利減免など) | 債務者の返済負担を軽減し、事業継続の可能性を高める | 債権回収までに時間がかかる可能性がある |
これらの他にも、DES(デット・エクイティ・スワップ:債務の株式化)や、事業の一部譲渡なども私的整理の一環として行われることがあります。どの方法が適切かは、企業の財務状況や事業内容、債権者の意向などを総合的に判断して決定されます。私的整理を成功させるためには、専門家である弁護士や会計士などのアドバイスを受けることが重要です。
3. 経営再建と私的整理の違い
経営再建と私的整理は、どちらも経営危機に陥った企業が事業を継続するための手段ですが、その手続きや法的拘束力、費用、経営陣の関与などに大きな違いがあります。以下、それぞれの違いを詳しく解説します。
3.1 手続きの違い
経営再建は、主に「事業再生ADR」や「会社更生法」「民事再生法」といった法的手続きを用いて行われます。これらの手続きは裁判所の監督下で行われ、債権者との合意形成や事業計画の策定などが進められます。一方、私的整理は、法的手続きを経ずに、企業と債権者が直接交渉して合意を形成する手続きです。そのため、裁判所の関与はなく、手続きも比較的柔軟に進めることができます。私的整理は、法的整理の事前準備として行われる場合もあります。
【関連】経営再建計画書の書き方|金融機関を納得させるためのポイント3.2 法的拘束力の有無
経営再建における法的手続き(事業再生ADR、会社更生法、民事再生法)は、裁判所の決定に基づいて行われるため、法的拘束力があります。債権者は、裁判所の決定に従って債権放棄や債務免除に応じる必要があります。一方、私的整理は、企業と債権者間の合意に基づいて行われるため、法的拘束力は限定的です。
債権者が合意内容を遵守しない場合、法的措置を取ることは難しくなります。そのため、私的整理は債権者との信頼関係が重要になります。メインバンクの存在や、債権者構成がシンプルであるほど、私的整理は成功しやすいと言えます。
3.3 費用と期間の違い
経営再建における法的手続きは、裁判所への申し立てや弁護士費用など、多額の費用がかかる場合があります。また、手続きも複雑で、長期間を要することがあります。一方、私的整理は、法的手続きを経ないため、費用は比較的安く抑えることができます。また、手続きも簡素で、短期間で完了することが可能です。ただし、私的整理の場合、債権放棄や債務免除の交渉が難航すると、長期化することもあります。
3.4 経営陣の関与
会社更生法や民事再生法といった法的手続きによる経営再建では、裁判所が選任した管財人が経営権を握り、既存の経営陣は経営から退くケースが多いです。一方、事業再生ADRや私的整理では、既存の経営陣が経営権を維持したまま再建を進めることができます。ただし、事業再生ADRや私的整理においても、金融機関などから経営改善のための指導や助言を受けることが一般的です。場合によっては、ターンアラウンドマネージャーなどの外部人材が経営に参画することもあります。
| 項目 | 経営再建(法的手続き) | 私的整理 |
|---|---|---|
| 手続き | 事業再生ADR、会社更生法、民事再生法など 裁判所の監督下 |
企業と債権者の直接交渉 |
| 法的拘束力 | あり | 限定的 |
| 費用 | 高額 | 比較的安価 |
| 期間 | 長期間 | 比較的短期間 |
| 経営陣の関与 | 管財人が経営(会社更生法、民事再生法の場合) 既存経営陣が主導(事業再生ADRの場合) |
既存経営陣が主導 |
| 債権者との関係 | 債権者全体の同意が必要な場合あり (会社更生法、民事再生法) |
主要債権者との合意が重要 |
| 情報公開 | 裁判所への報告義務あり 情報公開の範囲が広い |
情報公開の範囲が限定的 |
このように、経営再建と私的整理にはそれぞれ特徴があります。企業の状況や債権者との関係などを考慮し、最適な方法を選択することが重要です。専門家である弁護士や会計士などに相談し、適切なアドバイスを受けることが不可欠です。
4. 経営再建と私的整理のメリット・デメリット
経営再建と私的整理は、どちらも企業の危機を乗り越えるための手段ですが、それぞれにメリットとデメリットがあります。企業の状況や目指す将来像によって、適切な手段を選択することが重要です。
4.1 経営再建のメリット・デメリット 4.1.1 経営再建のメリット
| 事業の継続が可能 | 経営再建は、事業を継続しながら財務体質を改善することを目指します。そのため、雇用を維持し、取引先との関係を継続できる可能性が高くなります。 |
|---|---|
| 企業価値の維持・向上 | 再建計画が成功すれば、企業価値の維持または向上につながり、将来的な成長も見込めます。 |
| ステークホルダーの信頼維持 | 再建に成功することで、従業員、取引先、株主など、ステークホルダーの信頼を維持・回復できます。 |
| 経営陣の主導権維持 | 経営陣が主導権を維持したまま再建を進めることができます。 |
4.1.2 経営再建のデメリット
| 長期的な取り組みが必要 | 経営再建には、長期間の厳しいリストラクチャリングが必要となる場合があり、迅速な解決が難しい場合があります。 |
|---|---|
| 成功の保証がない | 計画通りに進まない場合、再建が失敗に終わる可能性もあります。 |
| 多大な労力と費用が必要 | 経営改善計画の策定、実行、モニタリングなど、多大な労力と費用が必要です。専門家の支援が必要となる場合もあり、そのための費用も発生します。 |
| ステークホルダーの協力が不可欠 | 従業員、取引先、金融機関など、ステークホルダーの協力が得られない場合、再建は困難になります。 |
4.2 私的整理のメリット・デメリット 4.2.1 私的整理のメリット
| 法的拘束力が弱く柔軟性が高い | 裁判所を介さないため、法的拘束力が弱く、債権者との交渉による柔軟な対応が可能です。状況に応じて、債務の減免や返済猶予などの措置を講じることができます。 |
|---|---|
| 手続きが比較的簡便で迅速 | 裁判所を介さないため、手続きが比較的簡便で迅速に進めることができます。法的整理に比べて時間と費用を抑えることができます。 |
| 企業イメージの低下を抑制できる可能性 | 法的整理に比べて公的な手続きではないため、企業イメージの低下を抑制できる可能性があります。 |
| すべての債権者の同意が必要 | すべての債権者の同意が得られない場合、私的整理は成立しません。主要債権者との交渉が難航する可能性もあります。 |
|---|---|
| 法的保護がない | 法的整理のような法的保護がないため、債権者が個別に債権回収の手続きを進める可能性があります。 |
| 再建に失敗した場合、法的整理に移行する可能性 | 私的整理が失敗した場合、法的整理に移行せざるを得ない状況になる可能性があります。その場合、時間と費用がさらに増大する可能性があります。 |
| 項目 | 経営再建 | 私的整理 |
|---|---|---|
| 手続き | 事業を継続しながら財務体質を改善 | 債権者との合意に基づき債務を整理 |
| 法的拘束力 | なし | 債権者との合意による |
| 費用 | 高額になる可能性あり(コンサルタント費用など) | 比較的安価 |
| 期間 | 長期 | 比較的短期 |
| 経営陣の関与 | 主導権を維持 | 債権者との交渉が必要 |
| メリット | 事業継続、企業価値維持・向上、ステークホルダーの信頼維持 | 柔軟性が高い、手続きが簡便、企業イメージ低下抑制 |
| デメリット | 長期的な取り組み、成功の保証なし、多大な労力と費用、ステークホルダーの協力必須 | 全債権者の同意が必要、法的保護がない、失敗時は法的整理へ移行の可能性 |
このように、経営再建と私的整理にはそれぞれメリット・デメリットがあります。どちらを選択するかは、企業の置かれた状況、財務状況、将来展望、そして債権者との関係性などを総合的に判断する必要があります。専門家である弁護士や会計士などのアドバイスを受けることが重要です。
5. 経営再建と私的整理、どちらを選択すべきか?
経営再建と私的整理、どちらも経営危機に陥った企業が取る手段ですが、その特性は大きく異なります。どちらを選択すべきかは、企業の置かれた状況、将来展望、そしてステークホルダーへの影響などを総合的に判断する必要があります。
5.1 企業の状況による判断基準
企業の状況によって、適切な手段は異なります。以下の表を参考に、現状を分析し、最適な選択を行いましょう。
| 状況 | 経営再建 | 私的整理 |
|---|---|---|
| 業績悪化の程度 | 軽度~中程度。将来的な収益性回復が見込める場合。 | 重度。事業継続が困難で、債務圧縮が必要な場合。 |
| 財務状況 | 債務超過ではない、もしくは軽度の債務超過。 | 深刻な債務超過。 |
| 金融機関との関係 | 良好。金融機関の支援を得られる見込みがある。メインバンクが存在し、協力的である。 | 悪化。金融機関からの追加融資は困難。 |
| 取引先との関係 | 良好。取引継続への理解と協力が得られる。 | 悪化。取引継続が困難な場合もある。 |
| 従業員の状況 | 雇用維持に一定の目処が立つ。 | 人員整理が必要となる可能性が高い。 |
| 事業の将来性 | 高い成長性が見込まれる、または中核事業に競争力がある。 | 事業の継続性自体が不透明。 |
例えば、一時的な業績悪化で、中核事業に競争力があり、金融機関の支援も得られる見込みがある場合は、経営再建が適切な選択肢となります。一方、深刻な債務超過に陥り、事業継続が困難な場合は、私的整理を選択せざるを得ないケースが多いでしょう。また、私的整理の中でも、事業の一部を売却することで資金を調達し、残りの事業を継続する「事業再生ADR」や、裁判所を利用しない「私的整理ガイドライン」に基づく手続きなど、状況に応じて最適な方法を選択する必要があります。
5.2 専門家への相談の重要性
経営再建と私的整理は、複雑な手続きと専門的な知識を必要とします。どちらを選択すべきか迷う場合は、弁護士、公認会計士、税理士などの専門家に相談することが不可欠です。専門家は、企業の状況を客観的に分析し、最適な再建策を提案してくれます。また、金融機関や取引先との交渉もサポートしてくれるため、円滑な手続きを進めることができます。
特に、私的整理は、債権者との合意形成が重要となるため、専門家の交渉力が大きく影響します。また、経営再建においても、事業計画の策定や資金調達など、専門家のサポートは大きな力となります。早期に専門家に相談することで、再建の可能性を高め、企業の再生をスムーズに進めることができるでしょう。
弁護士法人やコンサルティングファームなど、実績豊富な専門家を選ぶことが重要です。帝国データバンクや東京商工リサーチなどの信用調査機関の情報も参考にすると良いでしょう。
6. まとめ
経営再建と私的整理は、どちらも経営困難に陥った企業が事業を継続するための手段ですが、その手続きや法的拘束力、費用、期間、経営陣の関与などに大きな違いがあります。経営再建は、裁判所を介さない自主的な再建であり、法的拘束力はなく、柔軟な対応が可能です。
一方、私的整理は、債権者との合意に基づく手続きであり、法的拘束力を持つため、債権者からの協力が不可欠です。費用と期間は、経営再建の方が比較的少なく済みますが、私的整理は、債権者との交渉や手続きに時間がかかる場合があります。また、経営陣の関与についても、経営再建は既存の経営陣が主導しますが、私的整理では、場合によっては外部の専門家が関与することもあります。
どちらを選択すべきかは、企業の財務状況、事業の将来性、債権者との関係などによって異なります。一般的に、比較的軽度の経営困難で、債権者との関係が良好な場合は、経営再建が適しています。一方、深刻な経営危機に陥っており、債権者との合意形成が難しい場合は、私的整理を選択せざるを得ない場合もあります。
いずれにしても、早急に専門家、例えば弁護士や公認会計士などに相談し、適切なアドバイスを受けることが重要です。迅速かつ適切な対応が、企業の再生の成否を大きく左右します。


