経営再建の方法・手順|再建計画策定から実行までを分かりやすく解説!
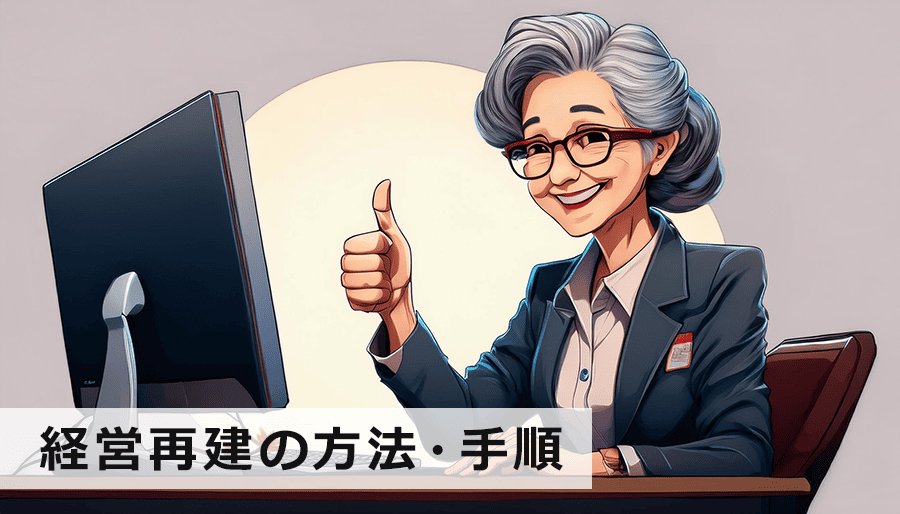
業績悪化に直面し、経営再建の必要性を感じている経営者様、経営幹部様へ。資金繰りが苦しい、売上が伸び悩んでいる、債務超過に陥っているなど、様々な経営課題に頭を悩ませていませんか?本記事では、経営再建の方法と手順を、現状分析から再建計画の策定・実行、そしてモニタリングまで、分かりやすく丁寧に解説します。
再建計画の策定に必要な財務分析、事業分析、SWOT分析はもちろんのこと、実行段階における事業構造改革、財務リストラクチャリング、組織改革についても具体的に説明。さらに、経営再建を成功に導くためのポイントとして、経営者のリーダーシップ、ステークホルダーとのコミュニケーション、弁護士や会計士などの専門家活用についても言及します。
帝国データバンクの倒産速報などを見ても、厳しい経済環境下で、多くの企業が経営の危機に直面している現状があります。この記事を読むことで、経営再建の全体像を把握し、自社に最適な再建計画を策定するための具体的な方法を理解することができます。具体的な事例も紹介することで、実践的な知識を習得し、企業の再生、そして成長へと繋げるための第一歩を踏み出しましょう。
「赤字解消(経営再建)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・事業再生などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建とは何か
企業経営において、業績が悪化し、事業の継続が困難になった場合に、その企業を再生させ、再び収益を上げられる状態に戻すための取り組みを「経営再建」といいます。単に赤字を解消するだけでなく、持続的な成長を実現できるような企業体質に変革していくことを目指します。
1.1 経営再建の定義
経営再建とは、経営危機に陥った企業が、その原因を分析し、事業の継続または清算に向けた計画を策定し、実行していく一連のプロセスです。財務状況の改善だけでなく、事業構造や組織、経営戦略など、企業経営のあらゆる側面を見直し、企業価値の向上を図ります。法的整理を伴う場合と、伴わない場合があります。
1.2 経営再建が必要なサイン
早期に経営再建に着手することが、成功の鍵となります。以下の兆候が見られる場合は、経営再建の必要性を検討すべきです。
1.2.1 売上高の減少市場の縮小、競争の激化、製品・サービスの陳腐化など、様々な要因で売上高が減少することがあります。一時的な減少であれば問題ありませんが、長期的な減少傾向は経営悪化のサインです。特に、同業他社と比較して売上高の減少幅が大きい場合は、早急な対策が必要です。
1.2.2 債務超過負債総額が資産総額を上回る状態を債務超過といいます。債務超過は、企業の支払い能力に問題があることを示す重要な指標です。短期間の債務超過であれば問題ない場合もありますが、長期間にわたる債務超過は、資金繰りの悪化や倒産のリスクを高めます。
1.2.3 キャッシュフローの悪化企業活動によって実際に得られた収入と支出の差をキャッシュフローといいます。黒字であっても、キャッシュフローが悪化している場合は、資金繰りが逼迫している可能性があります。売掛金の回収遅延や在庫の増加、設備投資の失敗などがキャッシュフロー悪化の要因となります。手元の資金が不足すると、運転資金の確保が困難になり、事業の継続が危ぶまれる可能性があります。
| サイン | 具体的な状況 | 対応策の例 |
|---|---|---|
| 売上高の減少 | 前年比で20%以上の減少、競合他社に大きくシェアを奪われている | 新製品開発、新規市場開拓、営業戦略の見直し、コスト削減 |
| 債務超過 | 長期間にわたり債務超過の状態が続いている、金融機関からの融資が困難になっている | 債務のリスケジュール、資産売却、増資 |
| キャッシュフローの悪化 | 運転資金の不足、支払いの遅延が発生している | 売掛金回収の早期化、在庫削減、不要な支出の見直し |
これらのサイン以外にも、従業員のモチベーション低下、取引先からの信用低下、不良在庫の増加など、様々な兆候があります。これらのサインを早期に察知し、適切な対策を講じることが、経営再建の成否を大きく左右します。重要なのは、問題を先送りせず、現状を正確に把握し、迅速に行動することです。
【関連】経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!2. 経営再建の手順
経営再建は複雑なプロセスであり、適切な手順を踏むことが重要です。以下に、一般的な経営再建の手順を解説します。
2.1 現状分析
まずは、企業の現状を客観的に把握する必要があります。以下の3つの分析手法を用いることが一般的です。
2.1.1 財務分析財務諸表(貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書)を分析し、収益性、安全性、効率性、成長性などを評価します。売上高の推移、利益率、負債比率、流動比率、自己資本比率などを確認し、問題点を明確にします。例えば、売上高の減少傾向が続いている場合、その原因を特定する必要があります。また、債務超過に陥っている場合は、負債の構成や返済能力を精査する必要があります。
2.1.2 事業分析市場環境、競合状況、製品・サービスの競争力、販売チャネル、顧客基盤などを分析し、事業の強みと弱みを把握します。PEST分析、5フォース分析、バリューチェーン分析などを活用することで、事業環境の変化や競争優位の源泉を分析できます。例えば、市場の縮小や競合の激化によって売上が減少している場合は、新たな市場への参入や新製品の開発などを検討する必要があります。
2.1.3 SWOT分析財務分析と事業分析の結果を踏まえ、企業の強み(Strengths)、弱み(Weaknesses)、機会(Opportunities)、脅威(Threats)を洗い出し、経営戦略策定の基礎資料を作成します。SWOT分析によって、企業が抱える課題と将来の可能性を明確にすることができます。例えば、強みを活かして機会を捉える戦略や、弱みを克服して脅威を回避する戦略などを検討することができます。
2.2 再建計画の策定
現状分析に基づき、具体的な再建計画を策定します。計画には、目標設定、経営戦略の見直し、財務計画の策定が含まれます。
2.2.1 目標設定再建計画の最終的な目標を設定します。目標は具体的かつ測定可能である必要があります。例えば、「3年以内に債務超過を解消する」「5年以内に売上高を前年比10%増とする」といった目標を設定します。目標設定においては、SMARTの原則(Specific:具体的、Measurable:測定可能、Achievable:達成可能、Relevant:関連性、Time-bound:期限設定)を意識することが重要です。
2.2.2 経営戦略の見直し既存の経営戦略を再評価し、必要に応じて見直します。事業の選択と集中、新規事業の開拓、コスト削減、業務効率化などを検討します。例えば、不採算事業からの撤退、成長が見込める事業への投資、固定費の削減、IT化による業務効率化などを検討します。また、顧客ニーズの変化や市場動向を踏まえ、製品・サービスの改良や新たなマーケティング戦略の策定なども必要となる場合があります。
2.2.3 財務計画の策定経営戦略に基づき、財務計画を策定します。資金調達計画、収支計画、キャッシュフロー計画などを策定し、財務の健全化を目指します。資金調達においては、金融機関からの融資、増資、資産売却などを検討します。また、収支計画においては、売上高の予測、コスト削減目標、利益目標などを設定します。キャッシュフロー計画においては、資金繰り表を作成し、資金ショートのリスクを回避するための対策を講じます。
2.3 再建計画の実行
策定した再建計画に基づき、具体的な行動を起こします。事業構造改革、財務リストラクチャリング、組織改革などが含まれます。
2.3.1 事業構造改革不採算事業の整理・縮小、成長事業への投資、新規事業の開拓などを行います。コア事業の強化、事業ポートフォリオの見直し、アウトソーシングの活用などを検討します。例えば、市場シェアの低い事業からの撤退、競争優位性のある事業への集中投資、間接業務の外部委託などを実施します。
2.3.2 財務リストラクチャリング債務の圧縮、資金調達、資産売却などを行います。デット・エクイティ・スワップ、返済猶予、金利の引き下げなどを交渉します。金融機関との良好な関係構築が重要となります。例えば、長期借入金を短期借入金に借り換える、担保を提供して融資を受ける、遊休資産を売却して資金を調達するなどの方法があります。
2.3.3 組織改革人員削減、部門再編、人事制度改革などを行います。組織のスリム化、意思決定の迅速化、従業員のモチベーション向上などを目指します。例えば、早期退職制度の導入、部門の統合、成果主義型賃金制度の導入などを実施します。組織改革においては、従業員との丁寧なコミュニケーションが重要となります。
2.4 モニタリングと評価
再建計画の実行状況を定期的にモニタリングし、必要に応じて計画を修正します。主要業績評価指標(KPI)を設定し、進捗状況を管理します。売上高、利益率、負債比率、キャッシュフローなどを定期的に確認し、目標達成度を評価します。計画が順調に進捗していない場合は、その原因を分析し、改善策を講じます。モニタリングと評価は、PDCAサイクルを回し続ける上で重要なプロセスです。
【関連】経営再建 手法とは?|種類別解説と企業再生の成功戦略3. 経営再建を成功させるためのポイント
経営再建を成功させるためには、以下の3つのポイントが重要です。
3.1 経営者のリーダーシップ
経営者の強いリーダーシップが不可欠です。明確なビジョンを示し、従業員を鼓舞し、ステークホルダーとの信頼関係を構築する必要があります。困難な状況においても、冷静な判断力と迅速な意思決定が求められます。
3.2 ステークホルダーとのコミュニケーション
金融機関、取引先、従業員、株主などのステークホルダーとの円滑なコミュニケーションが重要です。透明性のある情報開示を行い、理解と協力を得る必要があります。ステークホルダーのニーズを把握し、適切な対応をすることで、信頼関係を維持・強化することができます。
3.3 専門家の活用
弁護士、会計士、コンサルタントなどの専門家の知見を活用することが有効です。専門家は、法務、財務、事業戦略など、様々な分野における専門知識と経験を有しており、客観的なアドバイスを提供することができます。
| 専門家 | 役割 |
|---|---|
| 弁護士 | 法的アドバイス、債権者との交渉、法的書類の作成など |
| 会計士 | 財務分析、財務デューデリジェンス、会計監査など |
| コンサルタント | 事業戦略策定、事業再生計画策定、組織改革支援など |
4. 経営再建の事例
以下に、経営再建の事例を2つ紹介します。
4.1 事例1 XYZ株式会社のV字回復
XYZ株式会社は、主力製品の販売不振により業績が低迷し、債務超過に陥っていました。しかし、新製品の開発とコスト削減に注力することで、V字回復を達成しました。新製品は市場で高い評価を受け、売上高が大幅に増加しました。また、固定費の削減や在庫管理の効率化などにより、収益性が改善しました。これらの取り組みが功を奏し、XYZ株式会社は短期間で債務超過を解消し、黒字化を達成しました。
4.2 事例2 ABC株式会社の事業再生
ABC株式会社は、過剰な設備投資と多角化経営の失敗により、経営危機に陥っていました。そこで、事業の選択と集中を行い、不採算事業からの撤退を決定しました。また、金融機関との交渉により、債務の返済猶予と金利の引き下げを実現しました。これらの事業再生 efforts により、ABC株式会社は財務体質を改善し、経営の安定化を図ることができました。再生計画に基づき、コア事業の強化に注力し、新たな成長戦略を策定することで、持続的な成長を目指しています。
5. よくある質問(FAQ)
経営再建に関するよくある質問をまとめました。
5.1 経営再建にかかる期間は?
経営再建にかかる期間は、企業の状況や再建計画の内容によって異なります。一般的には、数ヶ月から数年かかることが多いです。早期に再建計画を策定し、実行に移すことが重要です。
5.2 経営再建に成功する確率は?
経営再建の成功確率は、一概には言えません。企業の状況、経営者の手腕、ステークホルダーの協力など、様々な要因が影響します。綿密な現状分析と実現可能な再建計画の策定が成功の鍵となります。
5.3 公的支援制度は活用できる?
経営再建においては、公的支援制度を活用できる場合があります。中小企業再生支援協議会や信用保証協会などの機関が、相談や支援を行っています。これらの制度を活用することで、資金調達や経営改善のサポートを受けることができます。
6. 経営再建を成功させるためのポイント
経営再建は、困難な状況を乗り越え、企業を再び成長軌道に乗せるための重要なプロセスです。その成功には、様々な要素が絡み合い、綿密な計画と確実な実行が求められます。ここでは、経営再建を成功に導くための重要なポイントを解説します。
6.1 経営者のリーダーシップ
経営再建において、経営者のリーダーシップは不可欠です。明確なビジョンと戦略を策定し、従業員、債権者、株主など、すべてのステークホルダーを巻き込み、一体感を醸成する必要があります。困難な状況下でも、冷静な判断力と強い意志を持ち、組織を導くことが求められます。具体的には、以下の点を意識することが重要です。
| 明確なビジョンの提示 | 再建後の企業の姿を具体的に描き、ステークホルダーに共有する。 |
|---|---|
| 迅速な意思決定 | 変化の激しい状況においては、迅速かつ的確な意思決定が不可欠です。 |
| 責任感と透明性 | 現状を正確に把握し、ステークホルダーに対して透明性の高い情報開示を行う。 |
| 強い意志と実行力 | 困難な状況に屈することなく、再建計画を着実に実行していく。 |
6.2 ステークホルダーとのコミュニケーション
経営再建は、企業に関わるすべてのステークホルダーの協力なしには成し遂げられません。従業員、債権者、株主、取引先、地域社会など、それぞれの立場や状況を理解し、誠実なコミュニケーションを図ることが重要です。具体的には、以下の点を意識することが重要です。
| 情報共有 | 経営状況や再建計画について、正確かつタイムリーな情報をステークホルダーに提供する。 |
|---|---|
| 双方向コミュニケーション | ステークホルダーからの意見や要望に耳を傾け、真摯に対応する。 |
| 信頼関係の構築 | 誠実な対応を通じて、ステークホルダーとの信頼関係を築き、協力を得られるように努める。 |
6.3 専門家の活用
経営再建は、専門的な知識と経験が求められる複雑なプロセスです。弁護士、会計士、コンサルタントなど、外部の専門家を積極的に活用することで、より効果的な再建計画を策定し、実行することができます。それぞれの専門家の役割を理解し、適切なタイミングで協力を仰ぐことが重要です。
| 専門家 | 役割 | 活用例 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 法的アドバイス、債権者との交渉、法的書類作成 | 会社更生法、民事再生法などの法的手続き、債務整理、訴訟対応 |
| 会計士 | 財務分析、再建計画策定支援、財務デューデリジェンス | 財務状況の把握、事業計画の策定、資金調達支援 |
| コンサルタント | 事業戦略策定、事業構造改革支援、組織改革支援 | 新規事業開発、コスト削減、業務プロセス改善、人事制度改革 |
これらの専門家は、客観的な視点から現状を分析し、最適な解決策を提案してくれます。また、専門家を活用することで、経営陣の負担を軽減し、再建に集中できる環境を整えることも可能です。それぞれの専門家の得意分野を理解し、適切な専門家を選ぶことが重要です。
経営再建は、企業の存続をかけた重要な取り組みです。経営者のリーダーシップ、ステークホルダーとのコミュニケーション、専門家の活用という3つのポイントを踏まえ、綿密な計画と迅速な実行によって、再建を成功に導きましょう。
【関連】経営再建計画の成功事例と失敗事例から学ぶ!V字回復のための5つのステップ7. まとめ
この記事では、経営再建の方法・手順について、再建計画の策定から実行、モニタリングまでを解説しました。経営再建とは、業績が悪化した企業が、事業の継続を図るために行う一連の取り組みです。売上高の減少、債務超過、キャッシュフローの悪化といった兆候が見られた場合は、早急な対応が必要です。
再建を成功させるためには、現状分析に基づいた綿密な再建計画の策定が不可欠です。財務分析、事業分析、SWOT分析などを活用し、客観的な状況把握に努めましょう。その上で、具体的な目標を設定し、経営戦略や財務計画を見直す必要があります。
計画の実行段階では、事業構造改革、財務リストラクチャリング、組織改革など、多岐にわたる施策が必要となる場合もあります。そして、計画実行後も定期的なモニタリングと評価を行い、必要に応じて軌道修正を行うことが重要です。経営者のリーダーシップ、ステークホルダーとの良好なコミュニケーション、弁護士や会計士などの専門家の活用も成功の鍵となります。
帝国データバンクの調査結果などを見ると、すべての企業が再建に成功するとは限りません。しかし、適切な手順を踏むことで、再建の可能性を高めることができます。


