AI事業の譲渡価格を自分で企業価値算定する方法|概算の売却価格を把握してみよう!
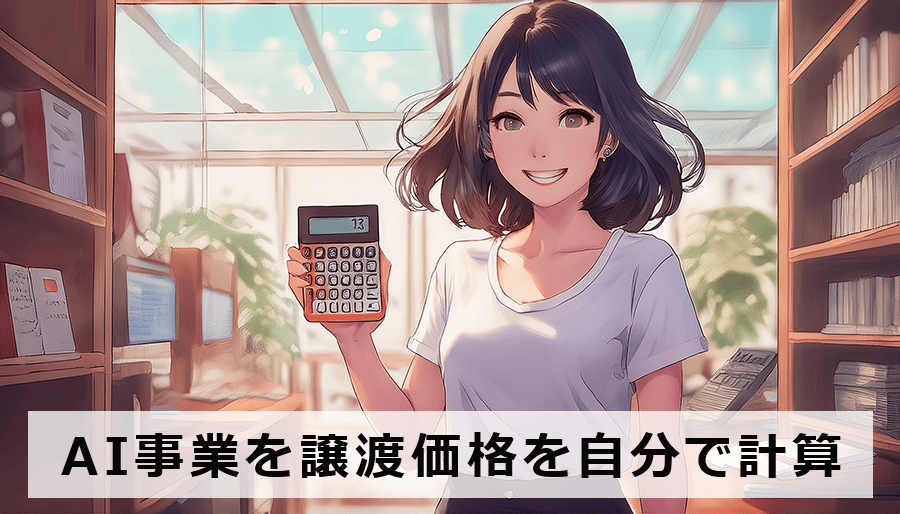
AI事業の売却を検討中の方へ。譲渡価格や企業価値算定は専門家任せと思われがちですが、概算であればご自身で算出可能です。この記事では、AI事業のM&Aが注目される背景から、自社の価値を左右する要素、そしてEBITDAマルチプルを使った具体的な算定方法までを解説。
あなたが売却価格の目安を把握し、高値売却を実現するための実践的な情報を提供します。専門家を賢く活用する方法も紹介し、納得のいくM&A実現への一歩をサポートします。
【無料】会社売却・事業承継のご相談はコチラ
「M&Aは何から始めればいいかわからない」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・経営再建業務などを10年経験し、多くの企業の業績改善を行ったM&A・PMIの専門家。3か月の経営支援にて期首予算比で売上1.8倍、利益5倍などの実績を持つ。
1. AI事業のM&Aが注目される理由
近年、人工知能(AI)技術は私たちの社会やビジネスに急速に浸透し、その市場規模は目覚ましい成長を遂げています。AI技術の進化は、企業の生産性向上、新たなサービス創出、顧客体験の変革など、多岐にわたる価値を生み出しており、多くの企業がAIを自社の成長戦略の中核に据えています。
このような背景から、AI事業のM&A(合併・買収)は、単なる事業再編の手段に留まらず、企業が競争優位性を確立し、未来を切り拓くための重要な戦略として、かつてないほど注目を集めています。
AI事業のM&Aが活発化する理由は多岐にわたりますが、特に技術革新のスピードが速いAI分野においては、自社でゼロから技術開発や市場開拓を行うよりも、既存のAI事業を買収する方が効率的かつ迅速に目的を達成できるケースが増えています。
本章では、なぜ今AI事業が売却の対象となり、買い手企業から熱い視線が注がれているのか、その背景とAI事業ならではのM&Aの特徴について深掘りしていきます。
AI技術の社会実装が進むにつれて、多くの企業がその恩恵を受けようとしています。しかし、AI開発には高度な専門知識、膨大なデータ、そして優秀な人材が不可欠です。
これらのリソースを自社で一から揃えるのは容易ではなく、時間もコストもかかります。そこで、既にこれらの要素を持ち、実績を上げているAI事業を買収するという選択肢が、非常に魅力的になっているのです。
かつてM&Aといえば、大企業同士の事業統合や、規模の拡大を目的としたものが主流でした。しかし、AI分野においては、中小企業やスタートアップが持つ特定のニッチな技術、ユニークなデータセット、あるいは特定の業界に特化したソリューションが、大手企業にとって非常に価値あるものとして評価されるようになりました。
大企業が自社で開発するには時間やコストがかかりすぎる専門性の高い技術や、特定の顧客基盤を持つAI事業は、高値で売却されるチャンスを秘めています。
また、事業承継や後継者不足といった中小企業特有の課題を解決する手段としても、AI事業の売却は注目されています。創業者が引退を考える際、事業を存続させつつ、適切な評価を得て売却することは、従業員の雇用維持や技術の継承にも繋がり、双方にとってメリットのある選択肢となり得るのです。
1.1.2 大手の買い手が探しているのは「技術」より「実績」AI技術は日々進化しており、新しいアルゴリズムやモデルが次々と登場しています。しかし、買い手企業が本当に求めているのは、単に最新の「技術」を持っていることだけではありません。それ以上に重視されるのは、その技術が実際に市場でどのように機能し、どのような「実績」を上げているか、そして将来的にどれだけの「収益」を生み出す可能性があるかという点です。
具体的には、PoC(概念実証)段階で止まっている技術よりも、既に顧客を獲得し、安定した導入実績や利用実績があるAIソリューションが評価されます。買い手は、投資した資金が確実にリターンを生むことを期待しているため、リスクの少ない、実用化された事業を求めているのです。
したがって、売却を検討するAI事業者は、自社の技術力だけでなく、具体的な顧客事例、導入後の効果、そして継続的な収益モデルを明確に提示できるかどうかが、譲渡価格を左右する重要な要素となります。
AI事業のM&Aは、従来の製造業やサービス業のM&Aとは異なる独特の評価軸と特徴を持っています。無形資産の価値が大きく、将来の収益性を予測する上で特有の視点が必要となるため、これらの特徴を理解しておくことが成功の鍵となります。
1.2.1 資産よりも「ストック型の売上」が鍵従来のM&Aでは、土地、建物、機械設備といった有形固定資産が企業価値算定の重要な要素でした。しかし、AI事業においては、これらの有形資産よりも、無形資産である「技術(アルゴリズム、ソースコード)」「データ」「知財」「優秀な人材」そして「継続的な収益を生み出すビジネスモデル」が遥かに高い価値を持ちます。
特に重視されるのが「ストック型の売上」です。単発の受託開発やプロジェクト型の収益(フロー型)よりも、月額課金制のSaaS(Software as a Service)モデルや、サブスクリプション型のサービス、継続的なライセンス収入など、安定して繰り返し発生する収益源がある事業は、企業価値が非常に高く評価されます。これは、将来の収益予測が立てやすく、事業の安定性や成長性が担保されるためです。
| 収益モデル | 特徴 | M&Aにおける評価 |
|---|---|---|
| ストック型(SaaS、サブスクリプションなど) | 毎月または毎年、継続的に収益が発生する。顧客維持率(チャーンレート)が重要。 | 将来の収益予測が安定しており、高い企業価値がつきやすい。 |
| フロー型(受託開発、単発プロジェクトなど) | プロジェクト完了ごとに収益が発生。次の案件獲得が必要。 | 収益の変動性が高く、企業価値算定においては慎重な評価が必要。 |
ストック型収益の割合が高いほど、安定した事業基盤と将来の成長性が評価され、結果として譲渡価格も高くなる傾向にあります。
1.2.2 M&Aの成功例に見る共通点AI事業のM&A成功事例には、いくつかの共通点が見られます。これらを把握することで、自社のAI事業を売却する際の強みや改善点を見つけるヒントになります。
- 特定のニッチ市場での優位性:汎用的なAI技術だけでなく、特定の業界(医療、製造、金融など)や特定の課題解決に特化したAIソリューションは、その専門性と実績から高く評価されます。
- 強力なデータ基盤:AIの学習に不可欠な高品質で豊富なデータセットを保有していることは、大きな強みとなります。特に、他社が容易に模倣できない独自のデータは価値が高いです。
- 優秀な人材と組織体制:AI開発や運用に携わるエンジニア、データサイエンティスト、プロジェクトマネージャーなどの専門人材の存在は、M&A後の事業継続性や成長性を担保する上で極めて重要です。属人性が低い組織体制も評価されます。
- スケーラビリティ:現在の顧客数や売上だけでなく、将来的に事業をどれだけ拡大できるか、他の市場や分野に応用できるかといったスケーラビリティも評価の対象となります。
- 顧客維持率と顧客満足度:既存顧客が継続してサービスを利用しているか、顧客からの評価が高いかどうかも、事業の安定性と将来性を測る重要な指標です。
これらの共通点を自社のAI事業に照らし合わせることで、買い手企業が何を重視し、どのような事業を求めているのかが明確になり、より効果的な売却戦略を立てることに繋がります。
【関連】AI業界のM&A動向を掴む!市場変化への対応と企業戦略2. まずはここから!譲渡価格を左右する基本要素 2.1 事業の価値は何で決まる? 2.1.1 収益性(EBITDA)を整理する
AI事業の譲渡価格を算定する上で、最も基本的な要素の一つが「収益性」です。特に買い手が重視するのが、事業が本業でどれだけの利益を生み出しているかを示す指標であるEBITDA(イービットディーエー)です。
EBITDAは「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization」の略で、税金、利息、減価償却費、のれん償却費を差し引く前の利益を指します。
これにより、企業の真の事業活動によるキャッシュ創出能力を把握できます。AI事業においては、研究開発費や先行投資が多額になりがちですが、EBITDAはそれらの影響を排除して事業本来の収益力を示すため、比較評価に適しています。
自社のEBITDAを正確に把握し、その推移を説明できるように準備することが、買い手への信頼性向上につながります。
| 項目 | 説明 | AI事業におけるポイント |
|---|---|---|
| EBITDA | 税引前利益に、支払利息、減価償却費、のれん償却費を加算した値。事業本来の収益力を示す。 | 先行投資が多く、会計上の利益が低くても、EBITDAが高ければ評価されやすい。 |
| 売上高 | 事業活動によって得られた収益の総額。 | 売上高の成長率や安定性が評価の対象となる。特にストック型売上が重視される。 |
| 売上総利益(粗利) | 売上高から売上原価を差し引いた利益。 | AI開発・運用における人件費やクラウド費用が原価となる。粗利率の高さは事業の効率性を示す。 |
譲渡価格は、単に現在の収益性だけで決まるわけではありません。事業が将来にわたってどれだけの収益を生み出し続ける可能性があるか、そしてその実現に対するリスクがどれくらいあるかという「リスクと将来性のバランス」が非常に重要になります。
AI事業は技術の進化が速く、市場環境も変化しやすいため、以下の要素がリスクと将来性の評価に大きく影響します。
- 技術的な優位性と陳腐化リスク:保有するAI技術がどの程度独自性があり、将来にわたって陳腐化しにくいか。
- 市場の成長性と競合環境:対象とする市場がどれくらい成長が見込めるか、競合他社との差別化ができているか。
- 顧客基盤の安定性:特定の顧客への依存度が高くないか、安定した顧客層を確保できているか。
- 法規制・倫理的リスク:AI特有の法規制や倫理的な問題に対する対応ができているか。
- 人材の確保と流出リスク:AIエンジニアなど専門人材の確保状況や、主要人材の流出リスク。
これらのリスクを適切に管理し、将来的な成長戦略を具体的に示すことで、事業の評価を高めることができます。
2.2 AI事業の「見られ方」チェックリスト 2.2.1 SaaS型?受託開発型?で変わる評価軸AI事業は、そのビジネスモデルによって買い手からの評価軸が大きく異なります。主に「SaaS(Software as a Service)型」と「受託開発型」の2つに大別され、それぞれ異なる強みと評価ポイントがあります。
SaaS型AI事業は、サブスクリプション形式でAIサービスを提供し、継続的な収益(ストック型売上)が見込めるため、高い企業価値がつきやすい傾向にあります。一方で、受託開発型AI事業は、プロジェクトごとに収益を上げるため、売上が単発的になりがちですが、特定の専門技術や実績、顧客との強固な関係性が評価の対象となります。
| ビジネスモデル | 特徴 | 評価されやすいポイント |
|---|---|---|
| SaaS型AI事業 | AI機能を搭載したソフトウェアをサブスクリプション形式で提供。 | 継続的なストック売上、高い粗利率、スケーラビリティ、顧客維持率(チャーンレートの低さ)。 |
| 受託開発型AI事業 | 顧客の課題に合わせてAIシステムやソリューションを個別に開発・提供。 | 特定の技術領域における専門性、豊富な開発実績、大手顧客との取引実績、安定したリピート案件。 |
自社のビジネスモデルがどちらに該当するか、あるいは複合型であるかを明確にし、それぞれのモデルにおける強みを具体的にアピールできるように準備しましょう。
2.2.2 「属人性の低さ」は高評価につながるAI事業の評価において、特に重要視されるのが「属人性の低さ」です。事業が特定の個人、特に創業者や主要なAIエンジニア、研究者に過度に依存している場合、その人材が抜けることで事業継続が困難になるリスクがあると見なされ、評価が下がる可能性があります。
買い手は、M&A後に事業を安定して運営できるかを重視するため、以下の要素を通じて属人性の低さを示すことが高評価につながります。
- 技術の標準化とドキュメント化:AIモデルの構築プロセス、コード、開発環境などが適切にドキュメント化され、誰でも理解・引き継ぎ可能な状態になっているか。
- チーム体制の確立:特定の個人に依存せず、複数のメンバーで技術やノウハウが共有され、チームとして機能しているか。
- ナレッジマネジメント:過去のプロジェクト経験や技術的な知見が組織内で共有され、蓄積される仕組みがあるか。
- 顧客関係の分散:特定の担当者に顧客関係が集中せず、組織として顧客と関係を構築できているか。
属人性を低減させるための取り組みは、事業の持続可能性を高めるだけでなく、M&Aにおける譲渡価格の向上にも直結する重要な要素です。
【関連】IT業界でM&A仲介を検討中の方へ。企業価値最大化を実現する戦略とは?3. 譲渡価格を自分で算定してみる|M&Aの概算評価法
AI事業の売却を検討する際、まず気になるのが「いくらで売れるのか」という譲渡価格ではないでしょうか。専門家に依頼する前に、ご自身で概算の企業価値を算定することで、売却の意思決定や専門家との交渉をスムーズに進めることができます。
ここでは、AI事業のM&Aで最も一般的に用いられる評価手法の一つ、「EBITDAマルチプル法」を中心に、ご自身で概算の売却価格を算出する方法を解説します。
AI事業のM&Aでは、将来の成長性や技術の優位性が重視される一方で、無形資産の評価が難しいため、事業が「稼ぐ力」を客観的に示すEBITDA(イービットディーエー)を用いた評価手法がよく採用されます。この方法は、企業の収益力をベースに、業界の特性や成長性に応じた倍率(マルチプル)を掛けて企業価値を算出するものです。
3.1.1 EBITDAって何?自社の数値を出してみようEBITDAとは、「Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization」の略で、日本語では「金利・税金・減価償却費控除前利益」と訳されます。
これは、金利や税金、減価償却費といった会計上の操作や財務戦略に左右されず、事業そのものが生み出すキャッシュフローに近い利益を示す指標です。企業の本来の収益力を測るのに適しており、異なる会計基準や財務構造を持つ企業間での比較が容易になります。
EBITDAの計算式は以下の通りです。
| 項目 | 計算式 |
|---|---|
| EBITDA | 税引前利益 + 支払利息 + 減価償却費 |
まずは、直近の決算書や試算表から、自社のEBITDAを算出してみましょう。AI事業の場合、研究開発費や先行投資が多額になることがありますが、これらもEBITDAでは加味され、事業の潜在的な収益力を示す上で重要な指標となります。
3.1.2 マルチプルは何倍が妥当?相場の見方マルチプルとは、EBITDAに掛け合わせる「倍率」のことで、企業の成長性、安定性、市場でのポジショニング、将来性などを総合的に評価して決定されます。同じEBITDAであっても、事業の特性や市場環境によってマルチプルは大きく変動します。
AI事業におけるマルチプルの相場は、一般的なIT企業と比較して高めに設定される傾向がありますが、その範囲は非常に広いです。例えば、安定したストック型収益を持つSaaSモデルのAI事業は高評価を受けやすく、単発の受託開発中心の事業は低めに評価されることがあります。
マルチプルを決定する主な要素は以下の通りです。
- 成長性:売上高や利益の成長率、将来的な市場拡大の可能性。
- 収益の質:月額課金などのストック型収益の割合、顧客の継続率、解約率の低さ。
- 技術力・競合優位性:独自のアルゴリズム、特許、データ資産、参入障壁の高さ。
- 顧客基盤:優良顧客の数、多様性、特定顧客への依存度の低さ。
- 事業の安定性:収益のブレの少なさ、市場の安定性。
- 経営体制:属人性の低さ、組織体制の整備状況。
複数の要素を考慮し、類似するM&A事例や業界レポートを参考にしながら、自社のAI事業に合ったマルチプルを見積もることが重要です。これにより、「EBITDA × マルチプル = 概算の企業価値」を算出することができます。
3.2 バリュエーションの落とし穴に注意EBITDAマルチプル法は簡便で分かりやすい評価方法ですが、いくつかの落とし穴も存在します。これらの注意点を理解しておくことで、より現実的で信頼性の高い概算評価が可能になります。
3.2.1 一時的な売上アップをそのまま信じない過去の業績を見る際、一時的な要因による売上や利益の急増があった場合は注意が必要です。例えば、特定の大型プロジェクトの受注や、期間限定のキャンペーンによる特需などがこれに当たります。買い手は、このような一時的な要因を除外した「正常収益力」を重視します。
持続性のない売上は企業価値に大きく寄与しないため、過去数年間の業績を多角的に分析し、継続的に生み出せる収益力を見極めることが重要です。異常値があれば調整し、より実態に即したEBITDAを算出するようにしましょう。
3.2.2 買い手が重視する「継続性」とは買い手が最も重視するのは、事業が将来にわたって安定的に収益を生み出し続ける「継続性」です。特にAI事業においては、技術の陳腐化リスクや競合の出現、キーパーソンへの依存度などが継続性を左右する重要な要素となります。
継続性を評価する上でのポイントは以下の通りです。
- 顧客との契約形態:月額課金などのストック型契約の割合が高いか。
- 技術の優位性:競合に模倣されにくい独自の技術やノウハウがあるか。
- データ資産:独自の学習データや蓄積されたデータが競争優位性になっているか。
- 組織体制:特定の個人に依存せず、組織として事業を運営できる体制が整っているか。
- 市場の成長性:事業が属する市場自体が将来的に拡大していく見込みがあるか。
これらの継続性に関する要素は、EBITDAマルチプルの「マルチプル」の部分に大きく影響します。高い継続性を示すことができれば、より高いマルチプル、ひいては高い譲渡価格に繋がる可能性が高まります。
【関連】会社売却の譲渡価格を自分で計算する方法|M&Aの基礎知識4. AI事業の価値を高める実践ポイント
AI事業の売却を成功させ、より高い譲渡価格を実現するためには、M&Aプロセスに入る前から計画的に準備を進めることが重要です。買い手が魅力的に感じる事業へと磨き上げ、適切な情報開示を行うことで、企業価値は大きく向上します。
4.1 事前にできる改善で譲渡価格が変わる事業の譲渡価格は、単に現在の収益性だけで決まるわけではありません。将来性やリスクの低減、そして事業運営の透明性が高く評価されます。M&Aの検討段階から、以下のポイントに注力することで、買い手からの信頼を得て、有利な条件を引き出すことが可能になります。
4.1.1 毎月の数字管理を整えるだけで印象が違う買い手が最も重視する情報の一つが、事業の財務状況です。特にAI事業の場合、技術先行型で先行投資が大きく赤字が続くケースも少なくありませんが、それでも財務管理の質は評価に直結します。正確でタイムリーな月次決算の実施はもちろん、事業の成長を裏付けるKPI(重要業績評価指標)を明確にし、その推移をデータで示すことが重要です。
例えば、SaaS型AI事業であれば「月間経常収益(MRR)」「顧客獲得単価(CAC)」「顧客離反率(チャーンレート)」、受託開発型であれば「プロジェクトごとの収益性」「リピート率」などがKPIとして有効です。これらの数値を定期的に管理し、予実管理を徹底することで、事業の健全性と将来の収益性を買い手に具体的にアピールできます。
| 財務管理のポイント | AI事業における具体例 | 買い手へのアピール |
|---|---|---|
| 月次決算の早期化と正確性 | 会計ソフトの活用、経費精算の徹底、売掛金・買掛金の適時管理 | 事業の実態を正確に把握し、迅速な意思決定が可能であること |
| KPIの明確化と追跡 | MRR、CAC、チャーンレート、AIモデルの精度向上率、データ蓄積量、API利用数など | 事業の成長ドライバーが明確で、再現性のある収益モデルであること |
| 予実管理の徹底 | 売上・費用予測と実績の比較、差異分析、その要因分析 | 経営計画の精度が高く、将来の収益予測に信頼性があること |
AI事業の価値を構成する要素は、目に見える資産だけではありません。むしろ、顧客との契約関係、開発したAIモデルやアルゴリズム、学習データなどの知的財産が事業価値の大部分を占めます。これらの権利関係が不明確であることは、デューデリジェンスにおいて大きなリスク要因と見なされ、譲渡価格の減額やM&Aの中止につながる可能性があります。
特に重要なのは、顧客とのサービス利用契約やNDA(秘密保持契約)の内容、従業員との雇用契約における知的財産権の帰属、外部ベンダーとのライセンス契約などです。これらが適切に整備され、いつでも開示できる状態にあることで、買い手は安心してM&Aを進めることができます。AI事業では物理的な在庫は少ないですが、データセットや学習済みモデル、ソフトウェアライセンスなどが「資産」として扱われる場合があるため、それらの管理も重要です。
| 整理すべき項目 | 確認ポイント | AI事業における具体例 |
|---|---|---|
| 顧客契約 | 契約期間、解約条件、料金体系、SLA(サービス品質保証)、データ利用許諾 | SaaS利用規約、受託開発契約書、データ利用許諾契約、個人情報保護に関する同意書 |
| 従業員契約 | 知的財産権の会社帰属、競業避止義務、秘密保持義務、退職時の対応 | 雇用契約書、就業規則、機密保持誓約書、職務発明規程 |
| 外部ベンダー契約 | ライセンス利用許諾、SaaS利用規約、共同開発契約における権利帰属、データ連携に関する合意 | クラウドサービス利用契約、オープンソースライセンス、データ提供契約、API利用規約 |
| 知的財産権 | 特許、商標、著作権(ソースコード、AIモデル、学習データ)の登録状況と帰属、不正競争防止法上の秘密管理性 | 特許出願書類、商標登録証、ソースコード管理台帳、データ管理ポリシー、秘密管理規定 |
M&A交渉の過程で、買い手はあなたのAI事業について徹底的な調査を行います。これがデューデリジェンス(DD)です。この段階でスムーズかつ正確な情報開示ができるかどうかは、M&Aの成否だけでなく、最終的な譲渡価格にも大きく影響します。
4.2.1 デューデリジェンスに備えた準備とはデューデリジェンスは、財務、法務、事業、人事、ITなど多岐にわたる分野で行われます。事前に必要な資料をリストアップし、データルーム(仮想データルームVDRを含む)を構築しておくことで、買い手からの質問に迅速かつ体系的に対応できます。特にAI事業では、データプライバシー保護体制、AIモデルの透明性・公平性、セキュリティ対策、技術スタックの詳細、開発体制なども重要な評価項目となります。
資料の準備だけでなく、各担当者がDDの目的を理解し、質問に対して誠実に回答できる体制を整えることも不可欠です。隠し事なく、しかし戦略的に情報を開示することが、買い手との信頼関係を築き、リスクを適切に評価してもらう上で重要となります。
| デューデリジェンスの準備項目 | AI事業における留意点 | |
|---|---|---|
| 財務資料 | 過去3〜5年分の決算書、月次試算表、資金繰り表、売上予測、原価計算書、損益分岐点分析 | 研究開発費の扱いや、先行投資による赤字の理由を明確に説明できるか、収益認識基準の妥当性 |
| 法務資料 | 各種契約書(顧客、従業員、ベンダー)、許認可、訴訟の有無、知的財産権リスト、プライバシーポリシー | 個人情報保護法、不正競争防止法、著作権法など、AI・データ関連法規への準拠状況、利用規約の適法性 |
| 事業資料 | 事業計画書、組織図、主要顧客リスト、製品・サービス概要、市場分析、競合分析、技術ロードマップ | AIモデルの技術的な優位性、開発体制、データ収集・活用戦略、今後の製品開発計画と市場展開 |
| 人事資料 | 従業員名簿、就業規則、給与規定、評価制度、キーパーソンのリストと定着率、人材育成計画 | AIエンジニアやデータサイエンティストの専門性、採用計画、人材流出リスクとその対策 |
| IT・セキュリティ資料 | システム構成図、セキュリティポリシー、データ管理規程、インフラ費用、災害対策計画 | 利用クラウドサービス、データ暗号化、アクセス制御、脆弱性診断結果、ログ管理体制、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)認証の有無 |
M&Aにおける情報開示資料は、単なる事実の羅列であってはなりません。あなたのAI事業の魅力、成長性、そして将来性を買い手に効果的に伝える「ストーリー」が必要です。特にインフォメーションメモランダム(IM)や事業計画書は、買い手の最初の印象を大きく左右します。
資料作成においては、以下の点を意識することで、信頼性を高め、買い手の理解を深めることができます。曖昧な表現を避け、具体的なデータや事例を豊富に盛り込むことが重要です。
- **正確性と網羅性:** 記載する情報はすべて事実に基づき、漏れがないようにします。根拠となるデータや資料を必ず添付または参照できるように準備します。
- **一貫性:** 複数の資料間で矛盾がないようにします。財務数値、事業計画、組織体制など、全体で整合性が取れていることが重要です。
- **分かりやすさ:** 専門用語は避け、図表やグラフを多用して視覚的に訴えかけます。AI技術の説明は、技術者でなくても理解できるよう平易な言葉で記述し、そのビジネス価値を明確に示します。
- **ストーリー性:** 事業の強み、市場における優位性、将来の成長戦略を論理的かつ魅力的に伝えます。なぜ今、この事業を売却するのか、買い手にとってどのようなメリットがあるのかを明確にします。
- **リスクの開示と対策:** 潜在的なリスク(例:特定の顧客への依存、技術的な課題、法規制の変更など)も隠さずに開示し、それに対する具体的な対策や解決策を提示することで、むしろ信頼性が高まります。
- **将来予測の根拠:** 売上や利益の予測には、具体的な市場データ、顧客獲得計画、製品開発ロードマップ、競合との差別化戦略など、明確な根拠を示すことが求められます。絵空事ではない、実現可能性の高い計画を提示します。
5. M&Aの専門家をうまく活用するには
AI事業の譲渡価格を自分で概算できるようになったら、次に考えるべきはM&Aの専門家をどう活用するかです。自分で企業価値算定を行うことは、売却の意思決定や専門家との対話において非常に役立ちますが、実際の交渉や契約プロセスは複雑であり、専門知識が不可欠です。適切な専門家を見極め、効果的に協業することで、AI事業の売却を成功に導く可能性が飛躍的に高まります。
5.1 どこまで自分でやる?どこからプロに頼る?AI事業のM&Aは、一般的な事業譲渡とは異なる特性を持つため、どこまでを自力で行い、どこから専門家の支援を仰ぐべきかを見極めることが重要です。自分で算定した企業価値は、専門家との議論の出発点となり、売却の意思決定を支援する強力なツールとなります。
5.1.1 初期評価と売却判断は自力でもOKAI事業の売却を検討する際、まずは自社の事業内容、収益性、将来性などを客観的に見つめ直し、概算の企業価値を自分で算定してみることは非常に有効です。
この初期評価を通じて、売却価格の目安や、売却によって得られる対価のイメージを具体的に持つことができます。また、事業の強みや弱み、改善点なども明確になり、売却の是非やタイミングを判断する上での重要な材料となります。
自分で算定した企業価値は、M&A仲介会社やアドバイザーに相談する際の基礎情報となり、より建設的な議論を進める上で役立ちます。例えば、希望売却価格を明確に伝えたり、自社の評価ポイントを効果的にアピールしたりすることが可能になります。
5.1.2 交渉・契約は専門家のサポートをM&Aのプロセスにおいて、買い手との交渉や最終的な契約締結は、専門的な知識と経験が最も要求される局面です。特にAI事業の場合、技術評価、知的財産権の移転、データ利用に関する取り決め、従業員の処遇、競業避止義務など、多岐にわたる専門的な論点が存在します。
専門家は、企業価値評価の精緻化、買い手候補の探索と選定、秘密保持契約(NDA)の締結、条件交渉、法務・税務デューデリジェンスへの対応、最終契約書(SPA)の作成・レビューなど、複雑なプロセス全体をサポートします。彼らの専門知識と交渉力は、売却価格の最大化だけでなく、売却後のトラブルを未然に防ぎ、スムーズな事業承継を実現するために不可欠です。
5.2 相談相手の選び方で失敗リスクは減らせるM&Aの専門家を選ぶことは、AI事業の売却成功に直結する重要な要素です。適切なパートナーを見つけることで、予期せぬリスクを回避し、より有利な条件での売却を実現できます。
5.2.1 AI事業に詳しい仲介・アドバイザーとは?AI事業のM&Aは、その技術的な特性やビジネスモデルの多様性から、一般的なM&Aとは異なる専門性が求められます。AI事業に精通した仲介会社やアドバイザーを選ぶことは、適正な企業価値評価、適切な買い手候補の探索、そして専門的な交渉を可能にする上で極めて重要です。
彼らは、AI技術のトレンド、市場におけるAIソリューションの価値、知的財産権の評価方法、SaaS型ビジネスモデルや受託開発モデルにおける収益性の見方など、AI事業特有の評価軸を深く理解しています。また、AI業界内のネットワークを持っていることが多く、より多くの買い手候補の中から最適なパートナーを見つける手助けをしてくれます。
| 項目 | 具体的な内容 | 理由・メリット |
|---|---|---|
| 専門性 | AI/IT業界に特化した知識とM&A経験 | AI事業の特性を正確に評価し、適切な買い手を見つけるため |
| 実績 | AI関連M&Aの成功事例や取引実績 | 信頼性と交渉力の裏付け、類似案件の知見活用 |
| ネットワーク | AI業界内外の買い手候補との幅広い繋がり | 選択肢を広げ、最適なマッチングを実現するため |
| 評価能力 | AI技術、知財、データ資産の価値を適切に評価できるか | 適正な譲渡価格の算定と交渉の基盤となるため |
| 提供サービス | 企業価値評価、交渉支援、デューデリジェンス対応など、包括的なサポート | 売却プロセス全体を円滑に進め、リスクを低減するため |
M&A仲介会社の中には、とにかく売却を成立させることを優先するケースも存在します。しかし、AI事業の売却は、単に事業を売却するだけでなく、経営者の想いや従業員の将来、そして事業の成長戦略を考慮したものであるべきです。そのため、「売却ありき」ではなく、あなたの事業の将来や経営者の意向を尊重し、真に「伴走」してくれる専門家を選ぶことが重要です。
伴走型の支援を提供する専門家は、売却以外の選択肢(例えば、事業提携や資金調達など)も視野に入れ、あなたの事業にとって最善の出口戦略を共に考えてくれます。また、売却後の事業統合(PMI)や従業員の処遇についても、売却前から具体的なアドバイスを提供してくれるでしょう。信頼できるパートナーと出会うことで、後悔のないM&Aを実現し、売却後の新たなステージへとスムーズに移行することが可能になります。
【関連】AI事業の企業価値を正しく見極める評価基準と投資戦略とは?6. まとめ
AI事業の売却は、技術だけでなく実績と継続性が評価される時代です。譲渡価格の算定には、まずEBITDAを把握し、マルチプルを用いて概算値を出すことができます。
SaaS型や属人性の低さは高評価につながるため、事業の特性を理解し、事前に数字管理や契約関係を整えることが重要です。これらの準備を自力で行いつつも、最終的な交渉や複雑なデューデリジェンスには、AI事業に精通したM&A専門家を賢く活用することで、売却成功の可能性を大きく高めることができるでしょう。


