経営再建 手法とは?|種類別解説と企業再生の成功戦略
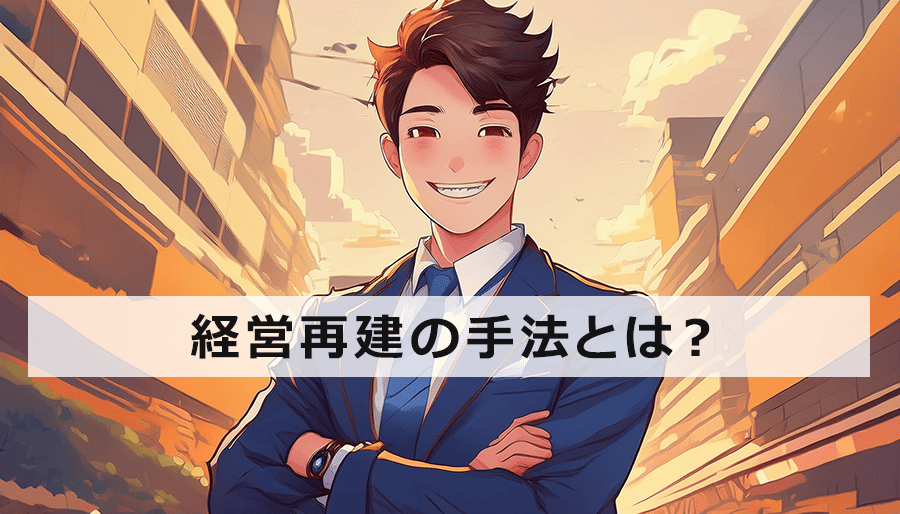
「経営再建 手法」で検索し、このページにたどり着いたあなたは、おそらく会社の業績悪化に直面し、具体的な解決策を探しているのではないでしょうか。この記事では、まさにその悩みに応えるべく、経営再建の具体的な手法を種類別に分かりやすく解説します。
財務リストラ、事業リストラ、組織リストラといった主要な手法を網羅的に取り上げ、それぞれの具体的な方法、メリット・デメリット、成功事例などを詳しく説明することで、あなたの会社に最適な手法を選択するための判断材料を提供します。
さらに、経営再建を成功に導くための戦略として、現状分析の重要性、経営計画の策定、そして金融機関、従業員、取引先といった主要なステークホルダーとの連携についても解説。帝国データバンクの倒産件数増加の現状や、コロナ禍、原材料費高騰、急激な円安といった経済状況も踏まえ、迅速かつ効果的な経営再建を実現するための具体的なステップを理解することができます。
この記事を読み終える頃には、経営再建の全体像を把握し、具体的な行動計画を立てるための確かな知識と自信が得られるはずです。
「赤字解消(経営再建)してからM&Aしたい」という経営者からも数多くのご相談をいただいています。M&Aを成功に導くはじめの一歩は無料のオンライン相談から。お気軽にご相談ください。
365日開催オンライン個別相談会
編集者の紹介

株式会社M&A PMI AGENT
代表取締役 日下部 興靖
上場企業のグループ会社の取締役を4社経験。M&A・PMI業務・事業再生などを10年経験。3か月の経営支援サポートで、9か月後には赤字の会社を1億円の利益を計上させるなどの実績を多数持つ専門家。
1. 経営再建とは何か?
経営再建とは、業績が悪化し、倒産の危機に瀕している企業が、事業の継続を図るために行う一連の改革活動のことです。単に倒産を回避するだけでなく、中長期的な視点で企業の収益性や競争力を回復させ、持続的な成長を実現することを目指します。企業価値の向上を図ることも重要な目的です。
1.1 経営再建の定義と目的
経営再建は、企業の財務状況、事業構造、組織体制など、多岐にわたる領域を対象とし、抜本的な改革を伴います。その定義は厳密に定められているわけではありませんが、一般的には「経営危機に陥った企業が、その原因を分析し、適切な対策を講じることで、再び健全な経営状態に戻すプロセス」と理解されています。主な目的は以下の通りです。
| 倒産の回避 | |
| 収益性の回復と向上 | |
| 財務基盤の強化 | |
| 企業価値の向上 | |
| 競争力の強化 | |
| 持続的な成長の実現 |
これらの目的を達成するため、経営再建は、ステークホルダー(利害関係者)である金融機関、従業員、取引先、株主などとの協力が不可欠です。透明性の高い経営と、各ステークホルダーとの良好なコミュニケーションが、再建を成功させるための重要な要素となります。
【関連】経営再建 とは? 倒産寸前の会社を再生させる方法を徹底解説!1.2 経営再建が必要な兆候
経営再建が必要な兆候は、財務指標の悪化だけではありません。非財務的な兆候にも注意を払う必要があります。早期発見と対応が、再建の成功確率を高めるため、以下の兆候に注意が必要です。
| 財務指標の悪化 | 非財務指標の悪化 |
|---|---|
売上高の減少 |
従業員のモチベーション低下 |
営業利益の減少 |
顧客からのクレーム増加 |
債務比率の増加 |
市場シェアの低下 |
流動比率の低下 |
新製品開発の停滞 |
自己資本比率の低下 |
意思決定の遅延 |
キャッシュフローの悪化 |
社内コミュニケーションの不足 |
これらの兆候は、単独で現れることもありますが、複数の兆候が同時に現れる場合もあります。これらの兆候が見られた場合は、経営状況を詳細に分析し、必要に応じて専門家の助言を得ながら、迅速に経営再建に着手することが重要です。放置すれば、事態は深刻化し、再建が困難になる可能性が高まります。
2. 経営再建の手法の種類とは?
経営再建には、企業の状況に合わせて様々な手法が用いられます。大きく分けて「財務リストラ」「事業リストラ」「組織リストラ」の3つの種類があり、これらを組み合わせることで効果的な再建を目指します。それぞれのリストラ手法について詳しく見ていきましょう。
2.1 財務リストラの手法とは
財務リストラは、企業の財務体質を改善するための手法です。負債の圧縮や資産の効率化を図り、財務の健全化を目指します。主な手法は以下の通りです。
2.1.1 債務免除債権者に対して、債務の一部または全部を免除してもらう手法です。企業の返済能力を超える債務を抱えている場合に有効ですが、債権者の同意が必要となるため、交渉が難航することもあります。リスケジュールと併用されるケースも多いです。
2.1.2 デット・エクイティ・スワップ(DES)企業の債務を株式に転換する手法です。債務が減少し、財務体質が改善される一方、既存株主の株式価値が希薄化する可能性があります。DESは、債権者が企業の将来性に期待を持っている場合に有効な手法です。
2.1.3 資産売却保有資産を売却し、資金を調達する手法です。遊休資産や非中核事業を売却することで、負債の返済や事業への投資資金を確保できます。ただし、将来の収益源となる資産を売却する場合は、慎重な検討が必要です。売却対象としては、不動産、子会社株式、設備などが挙げられます。
| 手法 | メリット | デメリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 債務免除 | 債務負担の軽減 | 債権者の同意が必要 | 交渉が難航する可能性あり |
| DES | 財務体質の改善 | 既存株主の株式価値希薄化 | 企業の将来性への期待が必要 |
| 資産売却 | 資金調達 | 将来の収益源を失う可能性 | 売却対象の選定が重要 |
2.2 事業リストラの手法
事業リストラは、企業の事業構造を改革するための手法です。収益性の低い事業の縮小や廃止、成長が見込める事業への集中などを図り、収益力の向上を目指します。
2.2.1 事業の選択と集中中核事業に経営資源を集中し、非中核事業を売却・撤退する手法です。選択と集中により、経営効率の向上や競争力の強化を図ります。どの事業を中核事業とするか、綿密な市場分析と将来予測に基づいた判断が必要です。例えば、パナソニックは家電事業に集中するため、プラズマディスプレイパネル事業から撤退しました。
2.2.2 新規事業の開発新たな収益源を確保するために、新規事業を開発する手法です。既存事業で培った技術やノウハウを活用した新規事業や、市場のニーズを捉えた革新的な新規事業などが考えられます。新規事業の開発には、リスクも伴いますが、企業の成長には不可欠な取り組みです。例えば、ソニーはゲーム事業に参入し、プレイステーションを開発することで、新たな収益源を確保しました。
2.2.3 アウトソーシングの活用一部の業務を外部企業に委託する手法です。間接部門や非中核業務をアウトソーシングすることで、コスト削減や業務効率化を図り、中核事業への経営資源集中を可能にします。例えば、経理業務や人事管理業務などをアウトソーシングする企業が増えています。適切なアウトソーシング先を選定することが重要です。
2.3 組織リストラの手法
組織リストラは、企業の組織構造や人事制度を改革するための手法です。組織のスリム化や効率化、人材の最適配置などを図り、組織全体の活性化を目指します。
2.3.1 人員削減余剰人員を削減する手法です。早期退職優遇制度の導入や配置転換などが行われます。人員削減は、コスト削減に効果的ですが、従業員のモチベーション低下や企業イメージの悪化につながる可能性もあるため、慎重な対応が必要です。適切な退職支援策を講じることも重要です。
2.3.2 組織改編組織構造を見直し、業務プロセスを改善する手法です。部門の統廃合や階層の削減などを行い、意思決定の迅速化や組織の柔軟性を高めます。組織改編は、企業の戦略変更や事業環境の変化に対応するために必要となる場合もあります。例えば、事業の多角化に伴い、事業部制を導入する企業が増えています。
2.3.3 人事制度改革評価制度や賃金制度などの人事制度を見直し、従業員のモチベーション向上や人材育成を促進する手法です。成果主義の導入や能力開発プログラムの実施など、様々な取り組みがあります。人事制度改革は、従業員の能力を最大限に発揮させ、企業の競争力を高めるために重要です。例えば、ジョブ型雇用を導入する企業が増えています。
3. 経営再建の成功戦略
経営再建を成功させるためには、闇雲に手法を実行するのではなく、綿密な戦略に基づいた計画と実行が必要です。ここでは、成功戦略の重要な要素を解説します。
3.1 現状分析の重要性
現状分析は、経営再建の出発点であり、その後の戦略策定の基礎となります。現状を正確に把握することで、問題点の特定とその解決策を明確にすることができます。財務状況、事業の収益性、市場環境、組織体制など、多角的な視点からの分析が不可欠です。
具体的には、以下の項目を分析します。
| 財務諸表分析 | 貸借対照表、損益計算書、キャッシュフロー計算書などを分析し、財務状況の健全性を評価します。安全性、収益性、効率性、成長性といった指標を用いて、企業の財務体質を多角的に分析します。 |
|---|---|
| 事業ポートフォリオ分析 | 各事業の市場シェア、成長性、収益性などを分析し、事業の強みと弱みを把握します。PPM分析やBCGマトリクスなどを活用することで、どの事業に資源を集中投下すべきか、どの事業から撤退すべきかを判断します。 |
| 市場環境分析 | 市場規模、競合状況、顧客ニーズの変化などを分析し、市場における自社のポジションを把握します。PEST分析やファイブフォース分析などを用いることで、市場における機会と脅威を分析します。 |
| 組織体制分析 | 組織構造、意思決定プロセス、人事評価制度などを分析し、組織の効率性や問題点を明らかにします。組織図や従業員へのアンケート調査などを活用することで、組織の現状を把握します。 |
3.2 経営計画の策定
現状分析に基づき、具体的な経営計画を策定します。目標設定、実行計画、評価指標などを明確にすることで、再建プロセスを可視化し、関係者間で共有することができます。計画は具体的かつ現実的で、かつ柔軟性を持つ必要があります。
経営計画には、以下の要素を含める必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 目標設定 | 具体的な数値目標を設定します。売上高、利益率、債務償還率など、定量的な目標を設定することで、進捗状況を客観的に評価できます。 |
| 実行計画 | 目標達成のための具体的な施策を策定します。財務リストラ、事業リストラ、組織リストラなど、具体的な行動計画を立てます。 |
| スケジュール | 各施策の実施時期や期間を明確にします。ガントチャートなどを活用することで、進捗状況を視覚的に管理できます。 |
| 評価指標 | 目標達成度を測るための指標を設定します。KPI(重要業績評価指標)を設定することで、計画の有効性を評価し、必要に応じて修正することができます。 |
| リスク管理 | 計画実行におけるリスクを洗い出し、対応策を検討します。想定されるリスクとその影響度、発生確率、対応策を明確にすることで、リスク発生時の迅速な対応が可能になります。 |
3.3 ステークホルダーとの連携
経営再建は、企業単独では成し遂げられません。金融機関、従業員、取引先など、様々なステークホルダーとの連携が不可欠です。透明性のある情報開示と誠実なコミュニケーションによって、信頼関係を構築することが重要です。
3.3.1 金融機関との交渉リスケジュールや債務免除など、金融機関の協力は不可欠です。経営状況を正確に伝え、再建計画への理解と協力を得ることが重要です。返済計画の提示や担保提供など、金融機関の立場も考慮した交渉が必要です。メインバンクとの関係構築は特に重要です。
3.3.2 従業員とのコミュニケーション従業員の理解と協力なくして、経営再建は成功しません。経営状況や再建計画を丁寧に説明し、不安や疑問に真摯に対応することで、モチベーションの維持と協力体制の構築を図ります。説明会や社内報などを活用し、透明性の高い情報開示を行うことが重要です。
3.3.3 取引先との協力取引先との良好な関係は、事業継続に不可欠です。支払条件の変更や納期の調整など、取引先に協力を求める場面も出てきます。状況を丁寧に説明し、長期的な関係維持を念頭に置いた交渉が必要です。取引先との信頼関係が、再建を支える大きな力となります。
4. 経営再建における注意点
経営再建を成功させるためには、手法の選択や実行だけでなく、様々な注意点に留意する必要があります。適切なタイミングで適切な対応を行うことが、企業の存続と成長に不可欠です。
4.1 早期対応の重要性
経営再建において最も重要な点の一つは、問題の兆候を早期に察知し、迅速に対応することです。業績悪化の兆候を放置すると、事態は深刻化し、再建がより困難になります。小さな問題でも見逃さず、早急な対策を講じることで、再建の可能性を高めることができます。
具体的には、売上の減少、利益率の低下、キャッシュフローの悪化、債務比率の上昇など、財務指標の悪化に注意を払う必要があります。これらの兆候が見られた場合は、すぐに原因を分析し、適切な対策を検討する必要があります。また、市場の変化や競合他社の動向にも常に注意を払い、将来的なリスクを予測することも重要です。早期に対応することで、より多くの選択肢を確保し、柔軟な対応が可能になります。
4.2 専門家への相談
経営再建は複雑なプロセスであり、専門的な知識と経験が必要です。弁護士、公認会計士、経営コンサルタントなどの専門家は、客観的な視点から現状を分析し、最適な再建計画の策定を支援してくれます。また、金融機関や取引先との交渉、従業員とのコミュニケーションなど、様々な場面で専門家のサポートを受けることで、再建プロセスをスムーズに進めることができます。
特に、法的整理や財務デューデリジェンス、事業再生ADR、M&Aなど、専門的な知識が必要な場合には、専門家への相談が不可欠です。彼らは、企業の状況に合わせて、最適な手法を提案し、実行をサポートしてくれます。また、専門家は、中立的な立場から助言を行うため、経営判断の精度を高めることにも繋がります。
専門家を選ぶ際には、実績や経験だけでなく、企業の状況やニーズに合った専門家を選ぶことが重要です。例えば、中小企業の再建に強い専門家や、特定の業界に精通した専門家など、様々な専門家がいます。複数の専門家に相談し、比較検討することで、最適な専門家を見つけることができます。
| 専門家 | 得意分野 | 相談内容例 |
|---|---|---|
| 弁護士 | 法的整理、債権者との交渉 | 会社更生法、民事再生法の申請、債務免除交渉 |
| 公認会計士 | 財務デューデリジェンス、財務リストラ | 財務状況の分析、債務削減計画の策定 |
| 経営コンサルタント | 事業再生計画策定、事業リストラ | 事業の選択と集中、新規事業の開発、組織改革 |
専門家への相談には費用がかかります。費用は、専門家の種類や相談内容、時間などによって異なります。事前に費用を確認し、予算に合わせて相談することが大切です。また、一部の自治体では、中小企業の経営相談を無料で受け付けている場合もあります。これらの制度を活用することも検討しましょう。
4.3 経営再建計画の柔軟な見直し
策定した経営再建計画は、状況の変化に応じて柔軟に見直す必要があります。市場環境や競合他社の動向、社内の状況などは常に変化するため、当初の計画通りに進まない場合も想定されます。定期的に計画の進捗状況を確認し、必要に応じて計画内容を修正することで、再建の成功確率を高めることができます。
また、計画の見直しにあたっては、ステークホルダーとのコミュニケーションを密にすることが重要です。金融機関や取引先、従業員など、関係者と情報を共有し、理解と協力を得ることで、スムーズな計画変更が可能になります。計画の柔軟な見直しは、変化への対応力を高め、企業の持続的な成長に貢献します。
5. まとめ
経営再建は、企業が厳しい経営状況から脱却し、再び成長軌道に乗るための重要なプロセスです。本記事では、経営再建の定義と目的、必要となる兆候、そして具体的な手法を種類別に解説しました。財務リストラでは、債務免除、デット・エクイティ・スワップ、資産売却など、企業の財務体質を改善するための手法を紹介しました。
事業リストラでは、事業の選択と集中、新規事業の開発、アウトソーシングなど、収益性を向上させるための戦略を解説しました。組織リストラでは、人員削減、組織改編、人事制度改革など、組織の効率化と活性化を図るための手法を説明しました。
成功する経営再建には、現状分析に基づいた綿密な経営計画の策定と、金融機関、従業員、取引先といったステークホルダーとの連携が不可欠です。特に、金融機関との交渉は資金繰りの安定化に直結するため、慎重に進める必要があります。また、従業員とのコミュニケーションを密にすることで、再建への協力を得ることが重要です。
取引先との協力も、事業継続性を確保する上で欠かせません。早期に対応し、必要に応じて弁護士や会計士などの専門家に相談することで、再建の可能性を高めることができます。経営再建は困難な道のりですが、適切な手法を選択し、関係者と協力することで、企業の再生は可能です。


